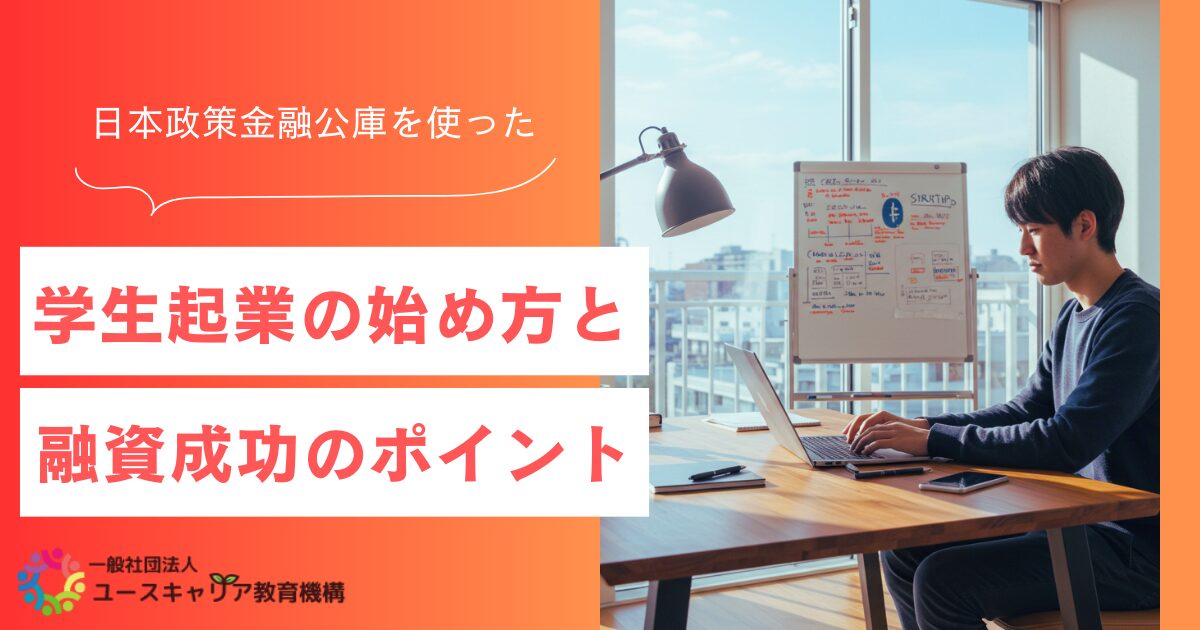「学生でも起業して資金調達できるのか?」
そんな不安を抱えながら、この記事にたどり着いたあなたはすでに一歩を踏み出そうとしています。
起業に挑戦する大学生にとって、「資金」の問題は大きな壁。
クラウドファンディングや親からの支援には頼りにくく、公的な支援制度に望みをかけている人も多いはずです。
中でも日本政策金融公庫の融資制度は、自己資金が少ない学生でも利用できる数少ない手段のひとつ。
しかし「本当に借りられるのか?」「審査の通し方は?」といった情報が少なく、行動に移せないままの人も多く見受けられます。
本記事では、日本政策金融公庫の制度概要から審査の通過ポイント、さらには実際に融資を受けた学生の事例までを徹底解説。
さらに、学生起業を支える支援環境や仲間づくりの情報も紹介します。
読み終える頃には、あなたの「やってみたい」が「やってみる」に変わっているはずです。

学生起業で使える日本政策金融公庫の主な融資制度

学生という立場でも利用できる融資制度として、日本政策金融公庫にはいくつかの選択肢があります。
中でも代表的なのが、「新規開業・スタートアップ支援資金」と「女性・若者/シニア起業家支援資金」です。
これらの制度は、創業間もない個人や法人を対象としており、まだ実績や信用が十分にない学生起業家でも利用できる可能性があります。実際に、ビジネスモデルや事業計画の完成度次第で、学生が審査に通過している事例も少なくありません。
民間の金融機関と比べて、低金利で、無担保・無保証の条件が設定されている点も大きな特徴です。創業初期においてリスクを最小限に抑えながら資金調達を進められるため、多くの若手起業家に選ばれています。
もちろん、制度ごとに年齢制限や事業の対象条件などはありますが、学生でも十分に要件を満たせる内容になっており、計画次第で融資獲得の現実性は高いといえるでしょう。
| 項目 | 新規開業・スタートアップ支援資金 | 女性・若者/シニア起業家支援資金 |
| 対象者 | 新規創業者または創業後7年以内の個人事業主・法人代表者(学生含む) | 女性、または35歳未満/55歳以上の新規創業者・創業後7年以内の事業者 |
| 資金用途 | 設備資金・運転資金 | 設備資金(開業費含む)・長期運転資金 |
| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 直接貸付:7.2億円代理貸付:1.2億円 |
| 返済期間 | 設備資金:20年以内(自宅設置5年以内)運転資金:10年以内(自宅設置5年以内) | 設備資金:20年以内(自宅設置2年以内)運転資金:7年以内(自宅設置2年以内) |
| 利率 | 特別利率A(年2.50~4.00%)※対象条件:女性、35歳未満、55歳以上、創業塾修了者等 | 2.7千万円まで(土地除く)→学生は特別利率A(年2.50~4.00%)2.7千万円超→基準利率 |
| 担保・保証人 | 原則不要(必要に応じて相談可) | 要相談(無担保・無保証も相談可能) |
| 必要書類 | 借入申込書、創業計画書、居住・学歴証明など(学生の場合) | 申込書、創業計画書、年齢確認資料など |
| 特徴・ポイント | 学生も対象で、創業直後から最大7年以内まで利用可能。無担保・無保証での融資も比較的通りやすい。 | 年齢・性別による特化制度で、限度額が大きい。条件次第で特別利率が適用されやすい。 |
参照:日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」
参照:日本政策金融公庫「女性、若者/シニア起業家支援資金」
学生起業家が日本政策金融公庫の制度で融資を獲得するまでの6つのステップ

学生であっても、日本政策金融公庫の制度を活用すれば、事業資金を調達することが可能です。ただし、融資を受けるまでにはいくつかの準備と手順が必要になります。ここでは、学生起業家が融資を獲得するまでの6つのステップをご紹介します。
ステップ1. 事前準備・相談
まずは、自分の事業内容に合った融資制度を調べましょう。
制度ごとの要件や利率、返済条件などを把握した上で、最寄りの日本政策金融公庫(JFC)支店やビジネスサポートプラザにて「創業相談」を受けることができます。
ここでは、専門スタッフから制度の特徴や審査のポイントについて直接アドバイスを受けることができ、申請に向けた準備の質を高めることが可能です。
ステップ2. 必要書類・事業計画の作成
次に、申請に必要な書類を準備します。主なものは以下の通りです:
- 創業計画書(公庫の公式テンプレートを活用)
- 本人確認書類(学生証、住民票など)
- 資金使途の見積書や資料
創業計画書には、ビジネスモデルの概要だけでなく、売上や費用の見通し、根拠となる市場調査、将来の展望なども記載する必要があります。特に学生の場合は、数字の根拠やリスク管理の視点を加えることで、説得力のある計画書になります。
ステップ3. 申込む
必要書類がそろったら、いよいよ申し込みです。
日本政策金融公庫では、インターネットからの24時間申請に対応しており、郵送や窓口での申請も可能です。オンラインの場合、書類をアップロードする形式になります。
ステップ4. 審査・面談
書類審査を通過すると、融資担当者との面談が行われます。
面談は対面またはオンラインで実施され、事業の内容や資金使途、本人の経験・熱意などについて詳しく確認されます。学生であっても、「生活費の管理状況」や「収支の見通し」、「事業に対する本気度」などが丁寧にチェックされます。
ステップ5. 融資決定・契約手続き
面談の内容と書類をもとに審査が行われ、融資可否の結果が通知されます。
承認された場合は、契約手続きに進みます。この段階で、実際の融資額や金利、返済スケジュールが確定し、細かな条件を公庫と合意します。
ステップ6. 資金実行
契約が完了すると、指定の銀行口座に資金が振り込まれます。
ここからが本格的な事業のスタート。融資された資金は、事業計画書に記載した内容に沿って正しく使うことが求められます。
これらのステップを丁寧に踏めば、学生でも日本政策金融公庫の制度を活用して、事業資金を確保することが可能です。初めての融資申請に不安を感じる方は、経験者や専門家からのアドバイスを得ながら進めることをおすすめします。
学生起業で日本政策金融公庫の融資制度を活用するときの条件
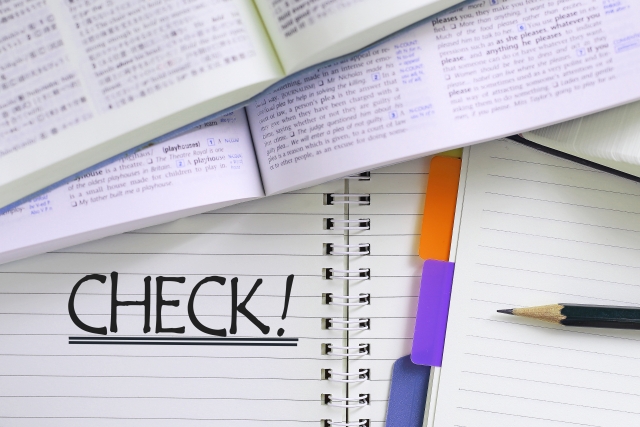
「本当に学生でも日本政策金融公庫の融資を受けられるのか?」という疑問を持つ方は多いかもしれません。結論から言えば、学生の起業アイデアであっても、審査に通る可能性は十分にあります。その鍵となるのが、事業計画の具体性と実行力です。
日本政策金融公庫の融資制度には、業種ごとの制限がありますが、EC(ネット通販)、ITサービス、飲食、教育関連など、学生にも取り組みやすいジャンルが広く対象とされています。
たとえば、学生の間で関心の高い「SNS発信」や「インフルエンサー活動」も、収益モデルが明確であれば融資対象となることがあります。単なる趣味やフォロワー数だけでは難しいですが、「どうやってマネタイズするか」「どれだけ実現可能か」を示せれば、評価されるケースもあるのです。
もちろん、実績が乏しい学生にとってはハードルもありますが、それを補うために重要なのが、仮説検証・市場調査・自己資金の準備です。これらを踏まえたうえで、説得力のある事業計画を立てることが、審査通過の近道になります。
実際に、海外向けのECサイトを展開した学生や、地域活性化に貢献するサービスを立ち上げた学生など、ユニークな事業でも融資を獲得している事例があります。
学生であっても、「起業家」としての本気度と準備があれば、日本政策金融公庫は力強い支援先となるのです。

学生起業で日本政策金融公庫の審査に通るための3つのポイント

ポイント1. 事業計画書の完成度が審査通過の鍵になる理由と準備の仕方
日本政策金融公庫の審査では、事業計画書の完成度が最重要ポイントとなります。審査官は、提出された計画書を通じて「この事業に実現性はあるか?」「数字に信頼性はあるか?」「起業家本人の本気度はどれくらいか?」を読み取ろうとします。
そのためには、事業の概要、ターゲット層、競合との違い、収益モデル、資金の使い道などを具体的に、論理的に説明する必要があります。学生であっても、内容に一貫性と具体性があれば、売上実績がなくても十分に信用される可能性があります。
さらに、単にフォーマットに沿って埋めるだけではなく、自分なりの図解や参考資料を添えることで、説得力を高めることができます。

<メンターコメント>
事業計画書は“書く技術”ではなく“考え抜く力”が問われます。
単にテンプレを埋めるのではなく、「なぜこの顧客に、なぜこの方法で届けるのか?」を言語化できる学生は、審査通過率も高いです。
実際、壁打ちを通じて構想が洗練された学生は、より自信を持って面談に臨めています
ポイント2. 自己資金の準備の仕方と見せ方のコツ
自己資金の有無は、本気度を測る重要な指標として審査で見られます。学生でも、アルバイトやインターンを通じて数十万円~200万円程度を貯めた事例は少なくありません。
また、審査では単に「いくら持っているか」だけでなく、その資金の出どころや通帳履歴も確認されます。急に入金された大金や、説明のつかない金額はリスクとみなされるため、計画的に積み立てたことを説明できるようにしておくことが大切です。
「見せかけの自己資金」とは、直前に親や友人から一時的に借りたお金を、あたかも自分の資金であるかのように見せる行為です。これは通帳履歴ですぐに見抜かれ、審査での信頼を大きく損なうリスクがあります。
たとえバレなかったとしても、返済能力や事業の持続性を疑われる可能性があるため、自己資金は誠実に、時間をかけて準備することが前提です。

<メンバーコメント>
自己資金の準備は、ただお金を貯めればいいわけではないと実感しました。
僕はマーケティング企業の長期インターンを続け、継続的な収入を得ながら、その経験を創業動機としても活かしました。審査でも「どれだけ本気で準備してきたか」が見られていると感じました。
ポイント3. 自分自身の見せ方
最終的に審査官が判断するのは、「この人にお金を貸して大丈夫かどうか」です。そのため、自分自身の熱意や姿勢、準備してきた経験をどう伝えるかが大きなカギとなります。
書類だけでなく、面談での受け答えや話の一貫性もチェックされます。たとえ実績がなくても、「なぜこの分野で」「どんな想いで」「どうやって実現するのか」を自分の言葉で語れるかが信頼を生むのです。
関連する学びや経験(インターン、アルバイト、ゼミ研究など)があれば、それを「どう活かすか」を明確に伝えることで、計画の説得力が増します。
テンプレ的な回答ではなく、自分の経験や気づきに基づく動機が理想的です。「なぜこの事業か」「なぜ今なのか」「なぜ自分がやるのか」という3点を軸に構成してみてください。

<メンバーコメント>
僕は大学のゼミで地方の観光プロジェクトに関わっていた経験を、「地域活性×EC」という自分の事業構想に結び付けて書きました。
一見関係なさそうな経験でも、「どう活かせるか」を具体的に示すことで、面談官に納得してもらえたと思います。
必要なのは、特別なスキルや実績ではなく、「なぜ自分がやるのか」を丁寧に伝え切る準備です。誠実に積み重ねた行動こそが、審査官の心を動かします。
日本政策金融公庫と併用できる学生起業家向け資金調達手段

日本政策金融公庫(JFC)の融資制度は、学生起業において最もよく知られる公的資金調達手段のひとつです。低金利かつ無担保で借りられる点は大きな魅力ですが、それだけに頼るのはリスクがあるというのが実際の声です。
たとえば、「希望額の融資が通らなかった」「審査基準が想定より厳しかった」というケースも少なくありません。特に学生の場合、社会的信用や事業実績がない分、融資額や審査通過率に不安が残ることもあります。
だからこそ重要なのは、複数の資金調達手段を理解し、併用する視点です。たとえば、返済義務のない助成金・支援金、出資型のベンチャーキャピタルやエンジェル投資家、さらにはプレマーケティングを兼ねたクラウドファンディングなど、学生でも活用できる選択肢は複数あります。
ポイントは、「どの手段を、どのタイミングで、どの目的で使うか」という視点です。それによって、事業のスピード感や自由度が変わり、戦略的なスタートアップ資金計画が可能になります。
ここでは、日本政策金融公庫と併用しやすい代表的な資金調達手段を3つに絞り、それぞれの特徴、メリット、注意点を具体的に紹介していきます。起業準備中の方は、資金戦略を立てるうえでの判断材料として、ぜひ参考にしてください。
| 項目 | 大学・自治体・NPOの助成金・支援金 | ベンチャーキャピタル・エンジェル投資家 | クラウドファンディング |
| 特徴 | 地域や大学単位で実施される起業支援制度。返済不要。 | 将来の成長を見越して出資を受ける形式。株式の一部を提供。 | ネットを通じて支援者から少額ずつ資金を集める仕組み。購入型・寄付型が主流。 |
| メリット | ・返済義務なし・地域や学生向け特化の制度が多い・起業初期の支援に適している | ・調達額が大きくなる可能性・経営支援やネットワーク提供も期待できる | ・返済不要の形式も多い・共感ベースで支援が集まる・事業のPRにもなる |
| デメリット | ・募集期間や対象が限定的・提出書類が煩雑な場合もある | ・株式の一部を手放す(持分が減る)・審査は厳しく、学生起業家にはハードル高め | ・プロジェクト設計や集客が必要・手数料が高い(10〜20%)・失敗のリスクあり |
| 調達可能な額の幅 | 数万円〜100万円程度が一般的(例外的に200万円以上の事例も) | 数百万円〜数千万円(条件により1億円超も) | 数万円〜300万円程度が一般的 |
| 調達までに必要な準備 | ・申請書類の作成・事業概要・目的の明確化・プレゼンや面接の対策 | ・ピッチ資料や事業計画の完成度・実績やチーム構成・投資家とのマッチング・交渉 | ・プロジェクトページの作成・画像・動画などの訴求素材・SNSや人脈を活用した拡散力 |
学生起業家が日本政策金融公庫を活用するときの3つの注意点

日本政策金融公庫は、学生起業家にとって心強い資金調達手段ですが、制度の活用にはいくつかの注意点があります。希望通りにいかなかったときに備える視点、返済スケジュールへの現実的な設計、そして自己資金とのバランスの理解が必要不可欠です。以下では、失敗しないために知っておきたい3つのポイントを詳しく解説します。
注意点1. 想定より融資額が少なかったときを想定する
希望融資額と実際の融資額に差が出る理由
日本政策金融公庫では、希望額どおりの融資が受けられないこともあります。特に学生起業家の場合、信用実績が乏しいため、計画が緻密でも金融機関側は保守的に判断します。審査では「自己資金とのバランス」「事業計画の妥当性」「返済能力」の3点が評価されます。
希望額が高すぎると、「現実的な計画が立てられていない」とマイナス評価される場合もあり、実際には2〜3割減額されるケースもあります(例:800万円→500万円など)。その前提で、現実的な金額設計を行うことが重要です。
不足分をどう補うかのリスク管理
万が一希望額に届かなかった場合に備えて、代替策を準備しておきましょう。たとえば、返済義務のない助成金・支援金、ビジネスコンテストの賞金、初期費用の見直しなどが有効です。また、「削れない支出」と「調整可能な支出」を事前に分けておくと、修正もしやすくなります。
自己資金の割合が高いと交渉にも有利に働くため、長期的な貯蓄計画も効果的です。

<メンバーコメント>
最初に希望していた金額より100万円ほど少ない融資額で決定しましたが、事前にシミュレーションしていたおかげで慌てずに対応できました。
メンターとの壁打ちで“万が一の資金調達プラン”を用意していたことが、気持ちの余裕にもつながったと思います。
注意点2. 返済を計画的に行う
日本政策金融公庫の融資では、返済の「据置期間」を設定できる場合があります。これは、融資後すぐに元金返済を開始するのではなく、一定期間は利息のみの支払いで済む制度です。学生起業の場合、売上が安定するまで時間がかかるため、この制度を活用することは非常に重要です。
ただし、据置期間が長ければよいというわけではありません。利子は据置中も発生し続けるため、返済開始のタイミングとキャッシュインの時期を事業計画に照らして慎重に判断しましょう。最低でも3〜6ヶ月は収入がなくても回る体制を整えておくのが理想です。
税金やクレジットの引き落としなど、後から発生する出費も想定に入れておきましょう。
注意点3. 融資枠の上限は、自己資金の2~3倍
日本政策金融公庫の審査では、希望融資額に対する自己資金の比率も重視されます。一般的に、自己資金の2〜3倍程度が融資枠の目安とされており、たとえば500万円の融資を希望するなら150〜200万円の自己資金が必要です。
希望額が高すぎると「返済能力に対して過大」と判断され、審査に通りづらくなります。逆に希望額が小さすぎても、「本当にその金額で事業が成立するのか」と疑問を持たれることもあるため、適切な規模感を持つことが大切です。

<メンターコメント>
融資は「通ったから成功」ではありません。審査を突破しても、実行段階で資金が活きなければ意味がないからです。
私たちは「事業を進める中でなぜ融資が必要なのか」「他の資金手段とのバランスはどうか」を徹底的に壁打ちしています。制度に振り回されず、主導権を持つ姿勢が重要です。
こうした注意点を踏まえた上で、日本政策金融公庫の融資制度を戦略的に活用することが、学生起業の成功確率を大きく高めます。制度の特徴だけでなく、想定外の事態にも備えた設計力が、起業家としての信頼につながっていきます。
本気で学生起業に取り組む人へ|日本政策金融公庫と併用したい支援環境の紹介

日本政策金融公庫を活用して起業に挑む学生にとって、資金計画や創業計画書の作成は大きな壁です。「これで合っているのか」「審査に通るのか」など、不安や迷いを抱える場面は少なくありません。特に、初めての起業では身近に相談できる人がいない孤独感も重なり、行動を止めてしまうケースもあります。
ユースキャリア教育機構では、そんな学生起業家を対象に、実践的な支援環境を提供しています。メンターと一緒に事業アイデアを整理し、収支計画やターゲット設定、資金使途の明確化など、融資申請に必要な要素を段階的に整えていくことができます。
また、過去に融資を獲得した卒業生の事例をもとに、「どのように伝えれば審査で評価されるか」「審査官はどこを見るのか」といった具体的な視点も学べます。同じ目標を持つ仲間との出会いや情報共有も、大きな励みになるはずです。
ユースキャリアでは、事業構想が漠然としていても参加できる無料説明会を実施しています。対話の中で、自分の考えが整理され、「次に何をすべきか」が見えてくるはずです。
本気で学生起業に挑戦したい人は、まず一歩踏み出して、無料説明会に参加してみてください。
あなたの挑戦を、経験豊富なメンターと仲間がサポートします。