「学生起業に興味はあるけれど、どの業種を選べばいいのか分からない」「失敗したくないけど、何から調べたらいい?」そんな不安を抱えてこのページに辿り着いた方も多いのではないでしょうか。
この記事では、学生に人気の起業業種や、実際に学生時代から起業し活躍している若手起業家のリアルな事例を紹介しながら、「自分に合った業種の見つけ方」と「スモールスタートのポイント」を丁寧に解説します。
起業の知識がゼロでも、迷っていても大丈夫。読み終える頃には、自分の興味や強みを活かせる業種と、その具体的な始め方がきっと見えてきます。

学生起業で業種を選ぶときの3つのポイント

ポイント1. スモールスタートできるか(初期費用・スキル要件)
学生起業では、初期コストを抑え、自分一人でも始められる業種を選ぶことが、最初の大きな成功要因になります。学業やアルバイトとの両立を考えると、時間やお金に大きな制約があるのは当然です。そのため「小さく始められるかどうか」は業種選びの重要な判断基準になります。
たとえば、動画編集やSNS運用代行、BASEなどを活用したEC販売、ノーコードやプログラミングによる簡易Webサービス開発などは、パソコンとネット環境さえあればスタート可能です。こうした業種は初期投資が少なく、在庫リスクや設備投資も不要。スキル面でも、YouTubeや無料の学習サイト、SNSコミュニティを活用すれば、独学でも十分実践に耐えられる力をつけられます。
一方で、実店舗経営や在庫型の商材販売などは、初期費用やランニングコストが高く、赤字リスクも大きいため、学生起業には不向きです。まずは最小限のリスクでスタートし、試行錯誤しながら徐々に事業をスケールさせる視点が重要です。
ポイント2. 市場ニーズがあるか(継続性と成長性)
起業で成果を出すには、「自分がやりたいこと」だけではなく、その分野に継続的な市場ニーズがあるかどうかを見極めることが不可欠です。ビジネスは誰かの課題を解決することで成り立つため、ニーズのない場所でどれだけ努力しても結果につながらない可能性が高いからです。
たとえば、教育×オンライン、デジタルマーケティング、SaaS領域、パーソナルブランディング支援など、時代の流れに合致し今後も拡大が見込まれる分野は、安定性と将来性の両方を兼ね備えています。一方で、一時的なブームや自分本位のアイデアに頼ると、継続的な収益化が難しくなるリスクがあります。
ニーズを見極めるための手段としては、GoogleトレンドやSNSでの反応調査、クラウドワークスなどの案件数チェックなど、学生でも手軽にできる市場調査手法があります。実際、成功している学生起業家の多くは、自分自身や身の回りの「不便」や「社会課題」に目を向け、それを出発点として事業化しています。起業の種は、意外と身近なところにあるのです。
ポイント3. 自分の関心・経験と接点があるか
起業する業種を選ぶ際は、自分の関心や経験と接点がある分野を選ぶことで、継続的に取り組みやすくなります。興味や体験に根ざした事業は、モチベーションを保ちやすく、他者との差別化にもつながります。
たとえば、「自分が悩んだこと」「周囲によく相談されること」「日常的に工夫してきたこと」などは、実は他の誰かにとって役立つサービスの種になりえます。他人の成功事例を真似るだけでは、続けるのが難しくなったり、思いが発信に乗らなかったりするリスクがあります。
実際に、自身のダイエット体験をもとにした食事指導サービスや、学生時代に作った学習ノートを教材として販売した事例など、「自分だからこそできたビジネス」で成果を出している学生も少なくありません。自分の「当たり前」や過去の経験を掘り下げることが、強みや独自性の源になるのです。

<メンバーコメント>
僕は最初「稼げそうだから」という理由だけで物販に取り組んでいたのですが、全くモチベーションが続かず…。自己分析をやり直して、マーケティング系の案件にシフトしてからは、自分の関心とも重なって結果も出るようになりました。「なぜこの業種か」を考える重要性を痛感しています。
学生に人気の起業業種

IT・Web系(アプリ・Web制作など)
IT・Web系の特徴
IT・Web系は、アプリ開発やWebサイト制作など、プログラミングやデザインのスキルを活かして取り組める業種です。スマホアプリやSaaS(ソフトウェア提供型サービス)のように、スケーラブルなモデルが多く、少人数でも大きな成果を出しやすいのが特徴です。
学生起業では、クライアントワーク(受託型)とプロダクト開発(自社サービス型)の両方の選択肢があり、自身のスキルや目標に合わせた事業展開が可能です。特に実績を積めば、企業との取引や他の起業家とのコラボなど、新たな機会も広がります。
また、収益構造が明確で、市場の成長性も高いため、資金調達やピッチイベントでも注目されやすい分野です。プレゼン資料やサービスのデモを通じて魅力を伝えやすく、起業初期から戦略的に動きやすい業種といえます。

<メンターコメント>
Web系は初期費用が低く、独学でも始めやすい一方で「ちゃんと案件を取れるか」の不安をよく聞きます。実際には、身近な知り合いや学生団体のWeb支援など、最初の受注先は案外近くにあることが多いです。まずは実績作りを重ねることが突破口になります。
学生でも始めやすい理由
IT・Web系は、初期コストの低さとスキル習得のハードルの低さから、学生にとって特に始めやすい分野です。YouTube、Progate、Udemy、N予備校など、無料〜低価格で学べる教材が豊富に揃っており、独学でも一定レベルまで到達可能です。
必要な道具も基本的にノートPC一台とネット環境だけで完結。ポートフォリオや制作物をSNSやGitHubで公開すれば、案件の獲得やフィードバックを受ける機会にもつながります。
さらに、他の活動(インターン、学生団体、講義)と並行しやすい点も魅力です。実際に在学中から月数万円〜数十万円の売上を上げている学生起業家も多く、「まず動いてみる」という第一歩を踏み出しやすい分野といえるでしょう。
コンテンツ系(動画編集・ライティング・SNS運用)
コンテンツ系の特徴
コンテンツ系の仕事は、クライアントの商品やサービスを「どう伝えるか」を形にする仕事です。具体的には、動画編集、SEOライティング、SNS(Instagram・TikTokなど)の運用代行などが代表的な業種で、情報発信力が問われる現代において、今後ますます需要が拡大していく分野といえます。
発信力や構成力、編集スキルといった「伝える力」全般が求められるため、自分の感性や個性を活かしやすい点が特徴です。また、報酬設計も多様で、時間報酬型・成果報酬型・運用コンサルティング型など、働き方に応じた報酬体系を選びやすい柔軟さもあります。
一定の経験と成果が蓄積すれば、自社メディアの立ち上げや、デジタル教材・情報発信ビジネスへの展開も可能で、コンテンツを軸にキャリアの広がりを作ることができます。

<メンバーコメント>
僕は最初にYouTube編集の副業からスタートしました。SNSで編集実績を発信していたら、大学生のYouTuberから依頼が来て、そこから継続案件につながったんです。コンテンツ系は、自分のスキルを“見せる場”を持つと、信頼につながっていくと思います。
学生でも始めやすい理由
コンテンツ系は、スマホやノートPCさえあれば始められる手軽さが魅力です。特別な設備や資金がなくても取り組めるため、初めての起業にも向いています。
また、自身のSNSアカウントやYouTubeチャンネルを使ってスキルや実績を「見せる」ことができるため、営業経験がなくても仕事につながりやすい点も学生には大きなメリットです。
さらに、Z世代である学生はトレンド感覚やSNSリテラシーが高く、企業側から「若者目線での提案や運用」を期待されるケースも多いです。YouTubeの切り抜き編集など、スキルよりも“丁寧な作業量”が求められる案件も多く、初心者でも実績を積みやすい環境が整っています。
教育・イベント系(学習支援・イベント企画)
教育・イベント系の特徴
教育・イベント系のビジネスでは、自身の経験や知識を他者の成長に役立てることができます。具体的には、小中高生向けの学習サポートや、大学生向けのキャリアセミナー、地域コミュニティを活用したイベントの企画・運営などが該当します。
この分野の特徴は、利益追求だけでなく、社会的な価値や意義を感じられること。他者の変化や喜びを直接実感できるため、やりがいやモチベーションの維持にもつながります。
また、活動が軌道に乗れば、単発イベントから定期開催、あるいは月額制サービス(オンライン家庭教師や習い事型イベントなど)へと展開することも可能です。参加者の満足度が高ければ口コミや紹介を通じて自然と広がるため、広告費をかけずに集客しやすい点も魅力です。
学生でも始めやすい理由
教育やイベント分野は、「つい最近まで自分もその立場だった」というリアルな体験こそが価値になります。たとえば、受験で苦労した経験や、就活での悩みを乗り越えた話は、同じ状況にいる人にとって大きなヒントになります。
また、Zoomなどの無料ツールを使えば、場所を借りる必要もなく、手持ちのデバイスだけで始められるため初期コストも最小限。大学内の友人や後輩に声をかけて、小規模なイベントから気軽にテストできる点も強みです。
「先輩の体験共有会」や「後輩向けの勉強のコツセミナー」など、等身大のテーマこそ参加者の共感を得やすく、最初の一歩を踏み出すには最適なジャンルといえるでしょう。
物販・EC系(せどり・ネットショップ)
物販・EC系の特徴
物販・ECは、商品を仕入れて販売する「せどり」や、自作・OEM商品をネットショップで販売する業種です。Amazonや楽天といった大手ECモールはもちろん、BASEやShopifyを使えば個人でも手軽にオンラインショップを立ち上げることができます。
この分野の大きな特徴は、「売れる商品」と「集客導線(SNS・広告)」の設計次第で売上が大きく変わるという点。アイデアと工夫によって短期間で大きな成果を出すことも可能です。
一方で、在庫管理・発送・仕入れといった業務も発生するため、他の業種と比べてオペレーション作業の比重がやや高めです。その分、収益構造は「数量×利益率」と明快で、売上・利益の計算が直感的に理解しやすく、ビジネスの基本を体感するには最適なフィールドといえるでしょう。
学生でも始めやすい理由
物販・EC系は、メルカリやラクマなど、学生にも馴染みのあるフリマアプリから始められる手軽さが魅力です。まずは低単価の商品を少量だけ仕入れて販売することで、リスクを最小限に抑えたテスト運営が可能です。
また、自作のアクセサリーやデザイン雑貨、リメイク商品など、「自分の好き」や趣味を活かしてオリジナル商品を販売できる点も、学生起業に向いている理由のひとつです。
SNSでの発信や共感ストーリーを活用すれば、広告費をかけずに集客することも可能。マーケティングや商品開発に興味がある学生にとっては、実践を通じて試行錯誤できる貴重な学びの場となります。
ソーシャルビジネス系(社会課題×ビジネス)
ソーシャルビジネス系の特徴
教育格差・環境問題・ジェンダー・地域活性などの社会課題を、ビジネスの力で解決することを目指すのが、ソーシャルビジネス系の起業スタイルです。ただのボランティアや寄付活動ではなく、持続可能な収益モデルを組み込んだ形で社会に貢献できる点が大きな特徴です。
社会課題への想いや志に共感が集まりやすく、仲間・支援者・顧客の巻き込みやすさが他業種よりも高いのが魅力。また、インパクト投資やソーシャルグッドを掲げる支援プログラムなど、社会的価値を重視する資金調達の道も開けやすい傾向があります。
さらに、社会性が高いテーマはメディアや行政との親和性が高く、信頼や注目を集めやすいため、認知度向上にもつながりやすい分野です。
学生でも始めやすい理由
ソーシャルビジネスは、学生という立場がむしろ強みに変わる業種です。学校・NPO・地域団体との連携では、若者の視点や行動力が歓迎されることも多く、信頼関係を築きやすい土壌があります。
また、課外活動やボランティア経験から得た気づきや課題意識が、そのまま事業テーマにつながりやすいのも特徴です。「自分だからこそ感じた違和感」を起点にした起業は、説得力と独自性があり、クラウドファンディングやピッチコンテストでの共感も得やすくなります。
「自己実現」と「社会貢献」を同時に叶えたいと考えるZ世代にとって、ソーシャルビジネスは非常に相性の良い挑戦領域です。社会のために何かをしたいという想いを、持続可能な形で実現できる可能性が広がっています。

学生起業で後悔しない業種の選び方

単なる「稼げる業種」では続かない理由
起業で大切なのは「収益性」だけではありません。確かに収益の出やすさは魅力ですが、それだけを基準に業種を選ぶと途中で情熱を失い、継続が難しくなるケースが多いのです。特に学生起業では、学業やサークル、人間関係などとの両立が必要なため、「金銭的リターンだけ」を動機にすると、優先順位が下がって自然にフェードアウトしてしまうことも少なくありません。
たとえば、一時的に収益が見込める「NFT転売」や「無在庫EC」なども、興味や社会的意義を感じられないまま進めていると、やりがいや将来性に不安を感じて撤退することもあるでしょう。
一方で、自分の経験や課題意識に根ざしたテーマで起業した学生は、成果が出ない時期でも改善を重ねて乗り越える力を持っています。「なぜこの事業をやるのか」が明確な人は、行動に軸が生まれ、顧客との信頼や周囲からの共感も得やすくなります。
自己理解から業種を逆算する考え方
後悔しない業種選びの鍵は、自己理解をもとに逆算することです。自分の価値観や得意なこと、過去に夢中になった経験などを棚卸しすることで、より納得感のあるテーマが見えてきます。
たとえば、「後輩に勉強を教えるのが楽しかった」経験からオンライン学習支援を始めたり、「家族の介護をきっかけに高齢者向けのSNSを開発した」など、自分だからこそ気づけた課題が起業テーマになることも珍しくありません。
こうした起業は、事業内容が“自分ごと”であるため、発信にも自然と熱がこもり、仲間や協力者も集まりやすくなります。さらに、たとえ失敗しても「やってよかった」と納得できるため、次のチャレンジにつなげやすいというメリットもあります。

<メンバーコメント>
正直、最初は「起業=派手で特別な人がやるもの」だと思っていました。
でも説明会で「自己理解から考える業種選び」の話を聞いてから、起業って“自分の等身大の課題を事業にする”ことなんだと納得できました。それが一歩踏み出す勇気になりました。
業種別の成功事例から学ぶ、学生起業のリアル
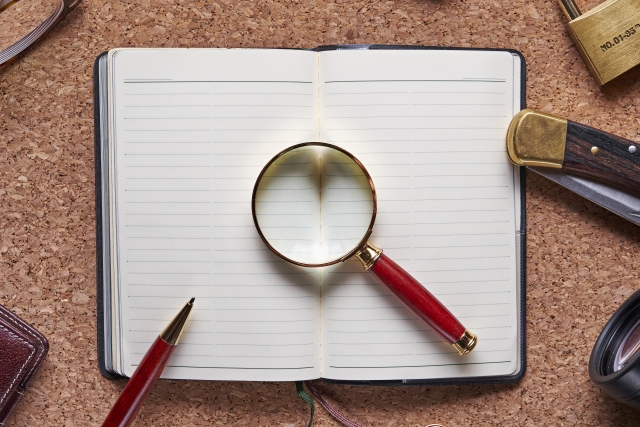
ユースキャリア教育機構の卒業生たちには、在学中から起業に挑戦し、現在も第一線で活躍している方も多いです。ここでは、そんな先輩たちのリアルな起業事例を通じて、業種選びや成功の背景を学んでいきましょう。
成功事例1. 株式会社Rover(Webコンサル・DX支援)
事業の概要と選んだ業種
株式会社Roverは、ユースキャリア教育機構OBの後上航さんが立ち上げた企業です。中小企業やスタートアップ向けに、WebマーケティングやDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進支援、AIの活用コンサルティングを提供しています。
単なる施策の提供ではなく、経営課題の本質に寄り添い、顧客と並走する「パートナー型支援」を信条としているのがRoverの大きな特徴です。
この業種を選んだ背景には、後上さん自身の「人から感謝される体験」や「社会に貢献できたという実感」があります。スキル、社会的意義、市場性のバランスが取れたWeb・DX支援の領域は、まさに学生起業における実践フィールドとして最適だったといえます。
学生時代からどう始めたか
後上さんが起業準備として最初に行ったのは、「身近な経営者3名への無償ヒアリング&伴走支援」でした。報酬を得る前提ではなく、経営者の本音や課題を丁寧に聞き出すことに全力を注ぎ、改善提案を重ねる中で自然と案件化が進んでいきました。
「スキルの売り込み」ではなく、「相手の悩みに本気で向き合う姿勢」が信頼を生んだ好例です。さらに、日単位でPDCAを回しながら改善スピードを上げていったことも、クライアントとの関係性強化に大きく貢献しました。
学生起業で乗り越えた壁と成長のポイント
最初の壁は、やはり「学生」という立場に対する信頼性の低さでした。後上さんはそれを逆手に取り、まずは無料支援からスタートすることで「実力を見せる」戦略を選びました。
また、施策の成果を出すことだけに終始せず、継続的な改善提案によって信頼関係を強化。クライアント企業の顧客とも直接関わるなど、「成果を一緒に創る姿勢」を大切にし、紹介やリピートを自然に生み出す事業構造を築きました。
この事例は、学生であっても本質的な課題解決力があれば、信頼と成果を積み重ねて事業を成長させていけることを示しています。

<後上さんのコメント>
最初は“実績をつくるための挑戦”でした。報酬ゼロで経営者に伴走し、課題を掘り下げて改善提案を重ねる。その積み重ねが信頼になり、次の仕事に自然とつながっていきました。大事なのは、まず目の前の相手の役に立つことに本気で向き合うことだと思います。
成功事例2. 株式会社Heywalk(キャリア支援・地方創生)
事業の概要と選んだ業種
株式会社Heywalkは、ユースキャリア教育機構OBの石原さんが立ち上げた企業で、若者と企業をつなぐキャリア支援・地方創生事業を展開しています。
起業の原点は、幼少期に地元商店街の衰退を目の当たりにし、地域の未来に危機感を抱いた体験でした。
「若者が地域に希望を持って活躍できる仕組みをつくる」ことを軸に、地域企業と若者双方に価値を提供できるキャリア支援の業種を選択。志と社会的意義の両方を兼ね備えたビジネスとして構想されました。
学生時代からどう始めたか
石原さんは、起業以前から学生団体として企業×学生のマッチングイベントや就活相談の活動を積極的に企画・運営しており、実績と信頼を着実に築いた上で、団体活動をベースに個人事業へと発展させていきました。
初期フェーズでは営業・企画・運営まで石原さんが一貫して担い、マッチングの質にこだわることで口コミや紹介が増加。活動の中で得たリアルな課題感をサービス改善に反映し続けたことが事業拡大の土台となりました。
学生起業で乗り越えた壁と成長のポイント
最大の課題は「信頼の獲得」と「協力者の巻き込み」でした。学生という立場への不安を払拭するために、団体時代からの人間関係を活かし、丁寧に提案や対話を重ねる姿勢が信頼構築につながりました。
また、地方事業においては「とにかく現地の人と会い、声を聞く」ことを重視。オンラインでは拾いきれない本音やニーズを把握することで、地域に根ざしたサービス設計が可能となりました。
理念や想いを言葉にして発信し続けたことで、共感を呼び、協力者・支援者の輪も広がっています。

<石原さんのコメント>
学生時代から「地方で若者が希望を持って働ける環境をつくりたい」と考えていました。最初は学生団体の活動として始めましたが、実績と信頼を積み重ねる中で、事業化の道が見えてきました。起業で大切なのは、自分が本気で解決したいと思える課題に取り組むこと。その想いがあるからこそ、仲間や協力者が自然と集まりました。
成功事例3. 株式会社AnnRock(DX・Webコンサルティング業)
事業の概要と選んだ業種
株式会社AnnRockは、ユースキャリア教育機構のOBである清水大河さんが立ち上げた企業です。主に店舗ビジネスを展開する中小企業に対し、WebコンサルティングやDX(業務改善・組織改革)支援を提供しています。
清水さんが注目したのは、「人手不足で新しい取り組みが進まない」「施策が属人的で再現性がない」といった、現場レベルの混乱や非効率さでした。自身が学習塾の運営やWeb支援に携わる中で体感した課題を出発点に、「現場を止めずに変える」ことをコンセプトにした支援スタイルを構築したのです。
特に、Web集客と業務オペレーションの改善を一体的に支援できる業種は、市場ニーズも高く、社会的意義との両立が可能な選択肢でした。
学生時代からどう始めたか
清水さんは、学生時代から学習塾の店舗運営やWebコンサルの現場に積極的に関わり、リアルな経営課題に触れることで事業の方向性を明確にしていきました。
初期フェーズでは、Web施策の提案だけでなく、現場に入り込んで集客導線の整備や業務改善を実行。既存の業務を妨げることなく進める姿勢が、クライアントからの信頼を得る鍵となりました。
また、正社員を抱えず、外部人材や若手フリーランスと柔軟に連携する体制をとることで、コストを抑えつつ成果を出す仕組みを構築。こうした機動力の高いスタイルが、紹介や継続依頼の拡大にもつながりました。
学生起業で乗り越えた壁と成長のポイント
支援先の多くが「外部人材に業務を任せること」への不安を抱えていたため、信頼の獲得が最大のハードルでした。清水さんは単なる提案にとどまらず、Web担当者や実行責任者として深く関わることで、確かな成果を残しながら信頼関係を築いていきました。
現場では「指示できないマネジメント層」や「形骸化したPDCA」など、構造的な問題とも向き合い、コンサルタントとしての視座を高めていきました。こうして磨かれた支援スタイルは、「小さく始めて、確実に変える」実践的なアプローチとして確立され、現在も数多くの現場で成果を上げ続けています。

<清水さんのコメント>
最初は「学生が企業の課題に本当に価値提供できるのか?」という不安もありました。ただ、実際に現場に入ってみると、「手が回っていない業務」や「見えていなかった課題」が山のようにあると分かり、そこにこそ自分の出番があると確信しました。大切なのは「上から提案する」のではなく、相手の立場で考えて一緒に改善していく姿勢。学生でも、伴走と実行力さえあれば信頼は獲得できます。
起業業種に迷っている学生におすすめ!無料説明会のご案内

この記事では、学生起業に向いている業種や先輩たちの成功事例を紹介してきましたが、「自分に合った業種がわからない」「実際にどう動けばいいのか迷っている」と感じている方も多いのではないでしょうか。
ユースキャリア教育機構では、起業に興味を持つ学生に向けて、無料の個別説明会を実施しています。
この説明会では、あなたの「やりたいこと」や「アイデアの種」に合わせて、適した業種の選び方や、具体的にどう動き始めるべきかを一緒に考えます。
また、過去に参加した学生が、どのように事業を立ち上げ、成果を出していったのかといったリアルなエピソードもご紹介します。
「まだ起業するか決めていない」「興味はあるけど何から始めればいいかわからない」という方も歓迎です。
進路選びの一環としての参加や、自己理解を深めたいという目的でも構いません。
一人で悩まず、最初の一歩を一緒に考える機会として、ぜひ無料説明会をご活用ください。



