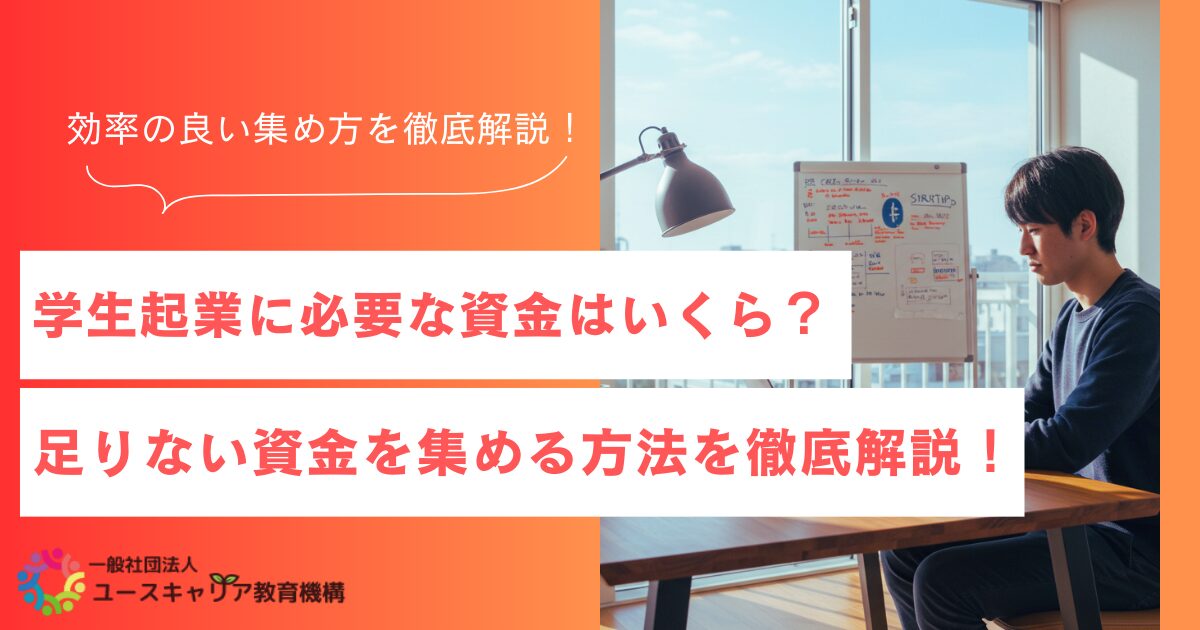この記事にたどり着いた方には将来不安から何かをなしとげたいと感じて、起業に挑戦しようと思ってみたけど資金がない。実際に起業にいくらかかるのかも分からない。
そこで本記事は起業を目指す学生のために、学生起業に必要な資金を解説しながら、実際に資金調達の方法、そしてよくある資金調達の注意点までご紹介します。

学生起業ってどれくらい資金が必要?

学生が起業を考えるとき、最も気になるのは「どのくらい資金が必要か?」という点です。
結論から言えば、起業の業種や規模によって必要な資金は大きく異なります。
一般的には、0円〜100万円程度あれば、十分に起業をスタートできます。
ただし、それはあくまで目安であり、自分が目指すビジネスの内容に合わせた資金計画が必要です。
次のセクションで分野別にかかる資金を解説します!
【アパレル・物販】約0円〜10万円
最もハードルが低く、学生に人気の高い分野です。
ハンドメイド作品やアパレルECなどを、SNS+無料ECサイト(BASE・STORESなど)を活用して販売するスタイルが主流です。
特徴
- 小資本で始めやすく、失敗してもリスクが少ない
- 売上は自分次第で伸ばせるが、時間の投資は必要
- 在庫リスクはあるが、受注生産型ならリスクは最小限
【IT・アプリ開発】約10万円〜100万円
アプリ開発やWebサービスを中心にした起業は、近年人気の分野です。
ただし、開発には専門スキルが必要なため、外注費用がかかるケースも多いです。
特徴
- 形にするまでに時間と資金がかかる
- 自力で開発できればコストは下げやすい
- 成功すればスケール(拡大)しやすい
【サービス業・イベント企画】約10万円〜50万円
イベント企画やコンサルティング、レッスン運営などのサービス業は、初期費用を抑えつつ始めやすい分野です。
特徴
- 最初は自分の人脈・スキルを活かして始めやすい
- 赤字になりにくく、資金回収が早いケースも多い
- スケールさせるには、外部人材や設備投資が必要になる場合も
【飲食業】約50万円〜300万円以上
飲食店の開業は、学生にとっては最も資金ハードルが高い分野です。
特徴
- 高額な初期投資が必要で、失敗リスクも高め
- 保健所の許可など、法規制をクリアする必要あり
- 初期投資を抑えるには、キッチンカーや間借り営業などの工夫が有効
学生起業家が成功しやすい資金調達方法8選

学生起業家は、社会人に比べて資金調達が難しいと言われています。たしかに、信用力や実績、担保といった観点で不利な点が多く、金融機関からの融資や大口出資を得るのは簡単ではありません。
しかし、「学生だから」といって、資金調達が不可能なわけではありません。むしろ、若さゆえの柔軟性や大学リソースの活用、人脈形成のしやすさなど、学生ならではの強みを活かすことで、現実的に資金を確保することも十分に可能です。
この記事では、学生でも比較的チャレンジしやすく、成功事例も多い資金調達方法を紹介していきます。
調達方法1.自己資金によるスタート
学生起業において最も基本的で、安全性が高い資金源が「自己資金」です。自己資金とは、学生自身がこれまでに貯めたお金やアルバイトによる収入、家族からの援助などを指します。
最大の利点は、外部の返済義務が一切ないことです。つまり、万が一事業がうまくいかなかった場合でも、借金としての返済を負う必要がありません。 また、自己資金によるスタートは、自身のビジネスに対する本気度や覚悟を示す意味でも有効です。創業期の多くの投資家や金融機関は、起業家自身がどれだけのリスクを負っているかを重視します。全額ではなくても、一部を自己資金で賄うことにより、信用度を高めることができます。
ただし、自己資金には当然限界があります。開発資金や広告費、法人設立にかかる諸費用、仕入れ・製造などをすべて賄おうとすると、手元資金では足りないケースも少なくありません。そのため、自己資金だけで回せる「スモールスタート型の起業」から始め、徐々に事業規模を広げていく戦略が現実的です。
調達方法2.学生団体への参加で資金チャンスを広げる
学生起業家にとって、資金調達の可能性を広げるうえで「起業団体への参加」は非常に効果的な手段のひとつです。起業団体とは、大学内外で活動する学生起業家のコミュニティや、起業支援を行う民間・公的団体を指します。
これらの団体に所属することで、まず得られるのは「情報」と「人脈」です。資金調達に関する最新の公的支援制度や、ビジネスコンテスト、クラウドファンディングの成功事例などを共有できる環境が整っています。また、実際に起業を経験している先輩からのアドバイスや、投資家とのマッチング機会を得られることもあります。
さらに、起業団体を通じて信頼関係を築けば、団体独自の資金支援制度やピッチイベントへの参加など、通常では得られないチャンスが生まれます。団体によっては、VCやメンターが常駐しているケースもあり、具体的な事業化の支援まで受けられる場合もあります。
調達方法3.ビジネスコンテスト(ビジコン)での賞金獲得
学生起業家にとって、有望な資金調達手段のひとつが「ビジネスコンテスト」です。近年では、学生を対象とした全国規模・大学主催のビジコンが数多く開催されており、優勝や入賞をすることで、数万円から数百万円規模の賞金を得ることが可能です。 この賞金は基本的に返済義務がなく、事業に自由に使えるため、非常に魅力的です。
また、審査員にはベンチャーキャピタルや起業支援者が含まれていることも多く、認知度や人脈の拡大にもつながります。 ただし、注意点として、コンテストによっては賞金の提供と引き換えに一定の出資や株式譲渡を求める条件がある場合もあります。
特に民間主催の大型コンテストでは、受賞と同時に契約義務が発生することもあるため、必ず事前に募集要項や応募規約を精読することが求められます。
調達方法4.クラウドファンディングの活用
クラウドファンディングとは、インターネットを通じて多くの人から資金を募る仕組みです。支援者には、そのお礼として商品やサービスなどのリターンを提供するのが一般的です。また、近年では支援の対価として株式を取得できる「金融型クラウドファンディング」も登場しており、より多様な形での資金調達が可能になっています。
この手法は比較的新しい資金調達方法として注目されており、特に若い世代の間で関心が高まっています。学生起業家にとっても、自身の想いやビジョンに共感してもらいやすいという点で相性が良いと言えるでしょう。
ただし、実施にあたっては仕組みを正しく理解し、魅力的なプロジェクト設計や発信の工夫が必要です。多くの支援を集めるためには、丁寧な準備と戦略が不可欠です。
調達方法5.補助金・助成金
補助金や助成金制度は、国や自治体、各種公的機関が提供する金銭的支援の仕組みです。創業支援や地域活性化、人材育成など、さまざまな目的に応じた制度が用意されており、対象も中小企業から個人事業主、学生まで幅広く設定されています。学生起業家であっても、「若年層の創業支援」や「初めての事業立ち上げ」などをテーマにした制度を選べば、活用のチャンスは十分にあります。
ただし、補助金や助成金は応募すれば必ず受け取れるわけではなく、申請内容に基づく審査を通過する必要があります。予算の上限があるため、毎年多くの申請が集まり、競争率が高くなることもあります。審査では事業の実現性や社会的意義、経済効果などが重視されるため、申請書や事業計画の完成度が合否を大きく左右します。
また、補助金や助成金にはそれぞれ募集期間が設けられており、常に申し込み可能とは限りません。「必要なタイミングに使えるとは限らない」という点にも注意が必要です。自分が希望する時期に適用できる制度があるかを早めに調べておき、条件やスケジュールを確認しておくことが、円滑な資金調達につながります。
調達方法6.公的融資(日本政策金融公庫)を検討
学生起業家は一般的に信用力が低く、民間の銀行や金融機関から融資を受けるのは難しいとされています。事業実績がない、担保や保証人が用意できないといった理由から、融資の審査に通りにくいのが現実です。
しかし、そんな学生でも融資を狙える可能性があるのが、「日本政策金融公庫」です。日本政策金融公庫は100%政府出資の公的金融機関で、創業支援や中小企業の成長支援を目的とした融資制度を多く用意しています。特に「新創業融資制度」は、開業まもない個人や法人を対象にしており、学生起業家にも門戸が開かれています。
この制度の大きな特徴は、無担保・無保証人でも利用可能な点です。また、金利も比較的低く設定されており、返済条件も柔軟なため、民間金融機関よりも利用しやすいと言えます。
調達方法7.家族・知人からの借入
学生起業の資金調達方法として、もっとも身近で現実的な選択肢のひとつが「家族や親しい人からの借入れ」です。特に親からの支援であれば、金融機関のような審査は不要で、借入金額や返済スケジュールについても柔軟に相談しやすいというメリットがあります。急な出費や事業の初期費用など、すぐにまとまった資金が必要な場面では、非常に心強い存在になるでしょう。
しかし、たとえ家族間の貸し借りであっても、そこに「お金」が絡む以上、慎重な対応が必要です。親しい間柄だからこそ、口約束で済ませてしまうケースもありますが、それが後々のトラブルにつながることも珍しくありません。返済が遅れたり、金銭感覚にズレが生じたりすることで、信頼関係に悪影響を与えることもあります。
そうしたリスクを回避するためには、金額や返済期限、返済方法などを明文化し、簡単でもよいので契約書を交わすことが望ましいです。また、返済時には銀行振込など履歴が残る方法を用い、口頭ではなく記録としてやりとりを残しておくと安心です。
調達方法8.VC・エンジェル投資家からの出資
VC(ベンチャーキャピタル)やエンジェル投資家は、主に成長性の高い若い企業や起業家に対して資金を提供する出資者です。ベンチャーキャピタルは投資ファンドの一種で、複数の投資家から集めた資金を使って企業に出資します。一方でエンジェル投資家は、個人として自身の資金でスタートアップに出資する投資家を指します。
どちらも、将来的に大きな成長が見込まれるビジネスに出資を行うため、革新性のあるアイデアや強い実行力を持つ学生起業家に対しても積極的に投資を検討するケースがあります。学生だからといって対象外になるわけではなく、むしろ柔軟な発想や新しい視点を持っている点で、相性が良いと評価されることもあります。
VCやエンジェル投資家から出資を受けたい場合には、まず彼らと接点を持つことが第一歩です。ピッチイベントや起業支援プログラム、大学のアクセラレーター制度などを通じて、投資家と出会うチャンスを積極的に探しましょう。
また、ビジネスモデルや収益計画をまもる事例も増えています。こうした非公式な融資は、法律が守られていないことも多く、金利や取り立てに関して違法性を含んでいる場合もあります。

学生起業家の資金調達で注意したいポイント5選

学生起業は資金調達のハードルが高いため、思うようにいかない場面も少なくありません。しかし、焦って判断を誤ってしまうと、事業にとって致命的なリスクを背負う可能性もあります。
ここでは、学生が資金調達を行う際に、特に注意しておきたいポイントを整理して解説します。
ポイント1.初期費用は最小限に抑えてスタートする
起業初期の段階では、できる限り費用を抑え、身の丈に合った規模でスタートすることが大切です。最初から多額の資金を投入してしまうと、万が一事業がうまくいかなかった場合に、多額の債務だけが残ってしまうリスクがあります。
まずは少額の資金で小さなチャレンジを行い、そこから得た成果や売上をもとに徐々に事業を拡大していくことが、安全かつ現実的な戦略です。実績が積み上がれば信用も生まれ、次の資金調達の際にも有利になります。
ポイント2.個人間融資はトラブルを未然に防ぐ対策をする
家族や友人からの借入れは、学生にとって手軽で柔軟な資金調達方法のひとつです。しかし、親しい間柄だからこそ、口約束で済ませてしまい、後々トラブルになるケースも少なくありません。
また、近年ではSNSや掲示板での「個人融資」など、正体のわからない相手から資金を借りようとして、詐欺やトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
ポイント3.投資は経営の自由度を奪う可能性がある
出資は融資と異なり返済義務がないため、学生にとって魅力的に映ることもあります。しかし、その代償として、出資者から経営への関与や利益の分配を求められる点には注意が必要です。
出資を受ける前には、資金調達額・株式の発行割合・契約内容を慎重に設計し、自社の経営権を守る意識を持つことが必要です。契約時には、弁護士や専門家のサポートを受けることも検討しましょう
ポイント4.VCやエンジェル投資家との契約は慎重に行う
VC(ベンチャーキャピタル)やエンジェル投資家は、起業家にとって頼れる存在ですが、出資を受ける際には細心の注意が求められます。特にVCから出資を受ける場合、1/3以上の株式を持たれると「拒否権」を与えることになり、事業の重要な判断を独自に行えなくなる可能性があります。
また、投資契約書の中に、自社に不利な条項(例:再出資義務や経営交代条項など)が含まれていることもあります。こうした内容は、契約書の読み込みと事前の交渉によって回避できるケースもあります。
ポイント5.ビジネスコンテストの賞金も条件を確認
ビジネスコンテストは、学生が実績を積みながら資金を獲得できる貴重な機会ですが、賞金の条件には注意が必要です。一見自由に使える資金に見えても、実際には「賞金と引き換えに株式の譲渡が必要」といった契約がセットになっている場合もあります。
特に、民間企業が主催するビジネスコンテストでは、支援の裏側に出資や商業利用の意図があることも多いため、応募時には賞金の性質・条件・契約内容を必ず確認しましょう。
資金ゼロの学生も起業に挑戦できる「ユースキャリア教育機構」

ここまで、学生起業家が資金調達に苦戦しやすい理由と、現実的な資金調達手段について紹介してきました。信用力の低さや担保の不足、実績や人脈のなさは、若くして挑戦を始めた人にとって大きなハードルです。しかし、だからといって、挑戦を諦める必要はありません。
むしろ、今は「何もない」からこそ、挑戦する価値があります。最初の一歩に必要なのは、完璧なビジネスモデルでも、潤沢な資金でもなく、共に挑戦できる“環境”です。そこで注目したいのが、「ユースキャリア教育機構」の存在です。
ユースキャリア教育機構は、学生のための起業支援・実践コミュニティです。起業アイデアの壁打ち、事業化に向けたブラッシュアップ、ピッチイベントやコンテスト出場のサポート、さらにはクラウドファンディングやVCとの接点づくりまで、現実的な行動を後押しするプログラムがそろっています。
あなたの挑戦を、ユースキャリア教育機構が全力でサポートします。
興味のある方は、実際に起業経験を持つアドバイザーとの無料面談にぜひお申込みください。