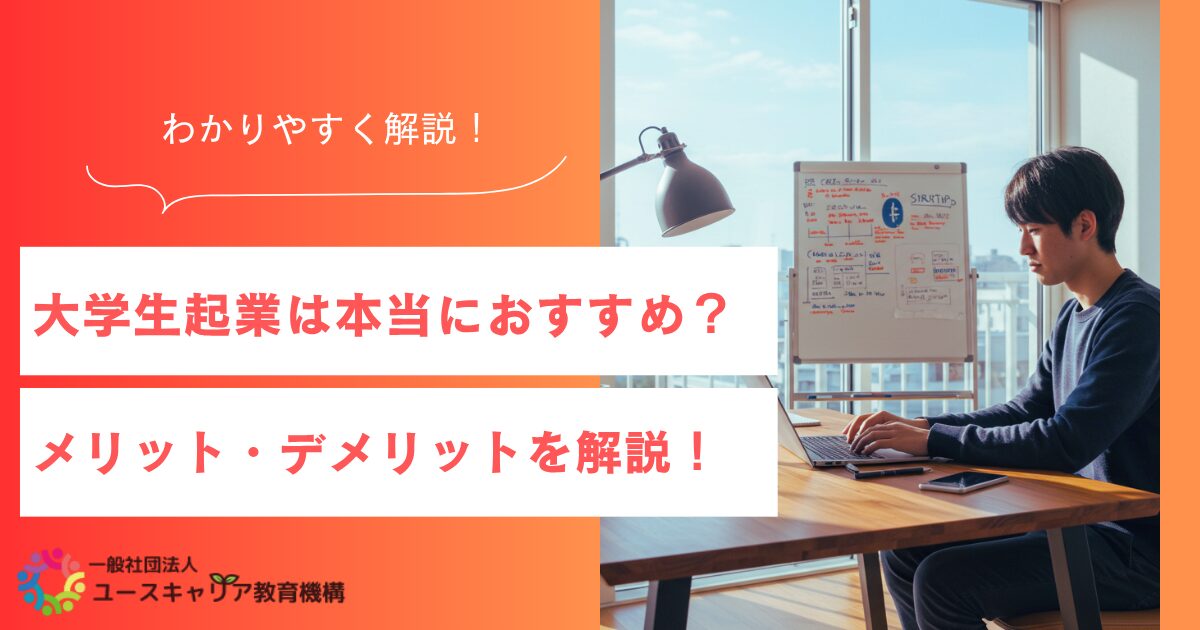この記事にたどり着いた方には将来の不安から何かをなしとげたいと感じて、起業に挑戦しようと思ってみたが、その選択がいいのか分からない。実際に学生起業がおすすめなのかも分からない。
そこで本記事は起業を目指す学生のために、大学生が起業におすすめな理由を解説しながら、実際に大学生起業のメリット・デメリット、そして大学生起業するための方法までご紹介します。

大学生起業をおすすめする5つの理由
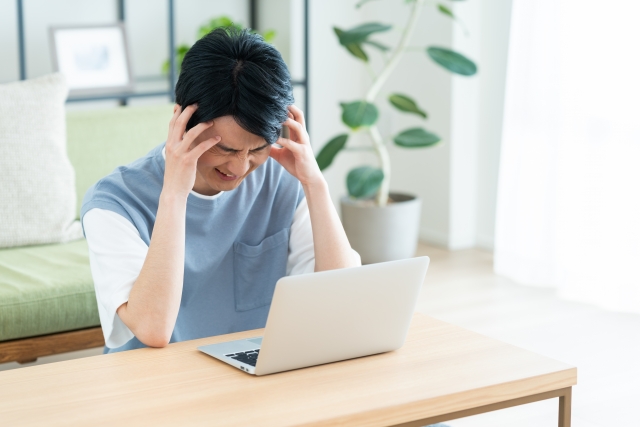
「今だからこそ、大学生が起業に挑戦するのは大いにおすすめ」です。時代の変化が大学生にとって有利に働いているからです。今回はその理由を5つ紹介します。
おすすめ1.若いことが武器
かつては「若さ=未熟」と見られていましたが、今の時代は違います。
多様な価値観や感性が尊重される社会において、大学生だからこそ持てる視点や悩みへの共感力が、ビジネスの価値になります。
「自分たちの世代に向けたサービス」や「学生だからこそ気づける課題」は、むしろ今の時代に求められているのです。
近年では、大学生はもちろん、中高生や小学生が起業する例も増えています。
例えば、重たいランドセルの不便さに着目して誕生した「サンポセル」は、小学生の気づきから生まれた商品。
大人では見落としがちなニーズに、若い視点が光った好例です。
このように、起業に必要なのは「経験」よりも「課題に気づく力」や「一歩踏み出す行動力」。
だからこそ、大学生という立場は、起業において決して不利ではなく、むしろ強みになり得るのです。
おすすめ2.時間とエネルギーに余裕がある
社会人は日々の業務に追われ、朝から晩まで会社に拘束される生活を送るのが一般的です。自分の時間を確保するのが難しく、起業の準備を進めるには早朝や深夜に作業する必要があり、精神的にも体力的にも大きな負担がかかります。
その点、大学生は授業やゼミ、バイトなどの予定をある程度コントロールできる柔軟性があります。春休みや夏休みなど長期休暇も活用できるため、起業アイデアの構想からテストマーケティングまで、腰を据えて取り組むことが可能です。
また、若さは最大の資産です。体力があり、睡眠時間を削ってでも熱中できるエネルギーがあるのは、大学生ならではの強みです。さらに、初めての挑戦に対して怖がるよりも「ワクワク感」で動けるのも、大学生のうちだからこそ持てる感覚です。
おすすめ3.失敗を恐れずに挑戦できる
起業にはリスクがつきものですが、それを恐れていては何も始まりません。大学生は社会に出る前の余白がある時期。たとえ失敗しても、学びに変えて立ち直る時間と環境が十分にあります。
また、若い世代の挑戦には、社会全体としてもポジティブな空気があります。クラウドファンディング、起業支援制度、メディアでの特集など、「若者×挑戦」に対する応援ムードが高まっており、それが後押しになるケースも多いです。
一方、社会人になると、住宅ローンや家族の扶養、肩書きの責任など、「失敗できない理由」が増えていきます。そのため、リスクを取る決断自体が難しくなるのが現実です。リスクを取れる今この瞬間こそ、最も挑戦に向いているタイミングとも言えます。
おすすめ4.大学ならではの支援制度がある
多くの大学では、起業を目指す学生を支援する制度が整備されつつあります。起業に関する授業やセミナーが開講されていたり、専任のアドバイザーが相談に乗ってくれるインキュベーション施設を持つ大学も増加中です。
さらに、学生限定のビジネスコンテストやアイデアピッチイベントも数多く開催されています。これらは資金獲得のチャンスであると同時に、事業内容へのフィードバックをもらいながら、実践力を磨く貴重な場です。
大学という環境には、共に学び・切磋琢磨できる仲間がいることも大きな魅力です。起業を目指す同世代とつながり、チームを組んだり、刺激を受け合うことで、成長スピードは格段に上がります。
おすすめ5.経験と実績が将来につながる
大学時代に起業し、成功すればそのまま事業をスケールさせて卒業後も続けることができます。学生ベンチャーからスタートして、実際に上場まで果たした起業家も数多く存在します。
仮にビジネスとしては途中でクローズしたとしても、その経験値や挑戦の過程は、確実に自分の武器になります。起業経験を通じて得られる「課題発見力」「意思決定力」「対人コミュニケーション能力」は、就職後にも大きく活かされます。
企業側も、「大学時代に起業していた経験」を高く評価する傾向が強まっています。書類や面接でも目を引くエピソードになるため、差別化された就職活動ができるのも大きなメリットです。
大学生起業をおすすめしない3つの理由

大学生のうちに起業することには数多くのメリットがある一方で、もちろんおすすめしない理由も存在します。安易に「若いから挑戦しよう」と突き進む前に、慎重に検討しておきたいポイントを確認しておきましょう。
理由1. 学業との両立が難しい
大学生が起業する最大のハードルのひとつは、学業との両立の難しさです。
日々の授業、課題、テスト、ゼミ、研究など、学生としての本分を果たしながら、ビジネスの立ち上げや運営に取り組むのは想像以上にハードです。
特に、長期的に時間を取られるビジネス(例:アパレルEC、サービス業、開発系スタートアップなど)の場合、「起業がメイン」「学業が二の次」になってしまうリスクもあります。大学生の本分はあくまで「学び」。
起業を成功させるためには、生活資金の管理、スケジューリング、健康面の維持など、総合的なセルフマネジメント力が求められます
理由2.資金調達のハードルが高い
大学生という立場は、金融機関や投資家にとっては信用力が低い存在と見なされやすく、資金調達において不利に働くことがあります。
「社会経験が浅い」「実績がない」「事業プランが抽象的」などの理由から、融資や出資を受けるのが難しいケースも少なくありません。
とはいえ、完全に道が閉ざされているわけではありません。
たとえば以下のような選択肢があります:
- 大学生向けの補助金・助成金(地方自治体や政府系機関が提供)
- 起業コンテストでの賞金やサポート
- 初期費用の少ないスモールビジネスからのスタート(例:SNS発信/委託販売/小ロットOEM)
最初から大きく稼ぐ必要はなく、スモールスタートで徐々に成長させるという戦略も有効です。
小さく始めて実績を積むことで、資金調達の信頼性も徐々に高まっていきます。
理由3.覚悟がないと途中で挫折しやすい
大学生は自由な時間や柔軟な発想を持っていますが、中長期で責任を負う覚悟や、事業を継続する粘り強さに欠けるケースもあります。
SNSの成功者や話題の若手起業家の影響で「起業=キラキラ」というイメージを持ちやすく、本当の意味での事業運営の泥臭さに直面したときに挫折してしまうことも。
そのため、起業を検討する際は自己分析やメンタルの準備も不可欠です。
「なぜ起業したいのか?」「1年後・3年後も続けたいと思えるのか?」を自問自答しながら、無理なく続けられるかを冷静に考える必要があります。
大学生起業におすすめの業種4選

大学生が起業を目指すとき、限られた資金や経験でもスタートしやすいビジネスモデルを選ぶことが大切です。ここでは、学生でも無理なく始められる起業アイデアを紹介します。自身のスキルや興味に合わせて選び、アイデアを膨らませてみましょう。
業種1.Webサイト制作
もっともスタンダードかつ将来性のあるビジネスが「Webサイト制作」です。HTML/CSSやWordPress、デザインソフトなどを学べば、企業や個人の依頼を受けてサイトを制作し、収益を得ることが可能です。
特に在宅で作業できるため、授業やアルバイトとの両立がしやすく、Webスキルそのものも就職活動や他の事業展開にも活かせる資産となります。最初の1件を獲得するハードルはありますが、実績を積めば安定した収入を得ることも十分可能です。
業種2.ブログ広告ビジネス(アフィリエイト)
低リスクで始められるビジネスとして、「ブログ広告ビジネス」も人気です。特定のジャンルについて記事を書き、そこに企業の広告リンク(アフィリエイト)を設置することで、商品が売れた際に報酬が入ります。初期費用がほとんどかからず、スキルも徐々に習得できるため、初心者でも挑戦しやすいのが特徴です
業種3.家庭教師・個人塾事業
教育系の起業を目指すなら、「家庭教師」や「個人塾」の運営も選択肢になります。大学生という身近な存在だからこそ、生徒や保護者からの信頼を得やすく、同じ大学を目指す後輩への指導など、独自の価値を提供できます。
小規模でも地道に評判を積み上げれば、紹介や口コミで広がる可能性もあります。
業種4.セミナー主催
自分でセミナーを企画・運営するというスタイルも、学生起業にはおすすめです。特別な設備は必要なく、企画力と講師の手配ができればすぐに始められます。
大学生という立場を活かせば、普段は会えない著名人や企業経営者にも「学生だからこそ」でアプローチしやすいのが大きな利点です。

大学生起業をしたい人におすすめする3つの方法
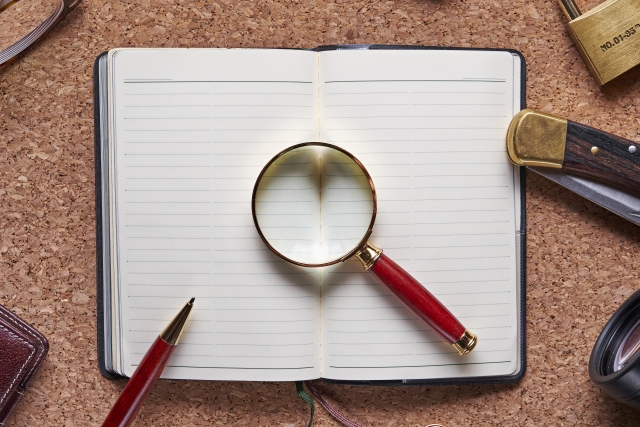
大学生が起業を目指すとき、限られた資金や経験の中でどのように一歩を踏み出すかが重要です。やみくもに始めるのではなく、正しい環境や知識、経験を得ながら進めることで、失敗のリスクを抑えながら成長できます。
ここでは、大学生でも無理なく実践できる「起業の始め方」を3つ紹介します。自分のスキルや目標に合わせて、最適な方法を選びましょう。
方法1.起業団体に入る
まず最初におすすめしたいのは、起業を志す仲間が集まる学生団体に参加することです。大学内外には、起業家育成を目的とした団体やコミュニティが数多く存在しています。こうした団体では、実際にビジネスに取り組む学生や、経験豊富なメンターと出会える機会が多く、自分一人で学ぶ以上のスピードで成長できます。
また、チームでプロジェクトに取り組む中で、企画力・実行力・リーダーシップなど、起業に必要なスキルも実践的に学べます。定期的にピッチイベントや勉強会も開催されており、フィードバックを受けながら自分のアイデアをブラッシュアップできる点も大きなメリットです。
方法2.本を読む
次に紹介するのは、起業やビジネスに関する本を積極的に読むことです。成功した起業家のノウハウや失敗談、事業計画の立て方、資金調達の方法など、書籍には濃縮された知識と経験が詰まっています。
特に、大学生にとってありがちな「何から始めたらいいか分からない」という状態には、本が最適な道しるべになります。
たとえば、『ゼロから始める起業の教科書』や『起業1年目の教科書』『STARTUP』などは、起業初心者にもわかりやすくおすすめです。
方法3.ビジネスコンテストに参加する
そして最後に紹介するのが、学生向けのビジネスコンテストへの参加です。これは起業前に自分のアイデアを試す絶好の機会であり、評価やフィードバックを得ながら事業の精度を高めることができます。
コンテストによっては、優勝すると賞金や支援金、企業とのマッチング機会が得られるケースもあります。また、審査員として起業家・ベンチャーキャピタル・自治体の担当者などが参加していることもあり、今後の人脈形成にもつながります。
大学生起業したい人におすすめの起業団体「ユースキャリア教育機構」

これまで、大学内外のさまざまな起業学生団体を紹介してきましたが、「どこから始めればいいかわからない」「自分に合った環境が見つからない」と感じた方にこそおすすめしたいのが、ユースキャリア教育機構です。
ユースキャリア教育機構は、29歳以下の学生・若手社会人を対象とした実践型のキャリア&起業支援団体で、全国から集まる仲間とともに、リアルな挑戦ができる場が整っています。起業体験プログラム、ビジネスの壁打ち、ピッチイベント、メンター制度、さらには“起業家シェアハウス”まで──まさに「本気で動きたい人」にとって必要なものがすべて揃っています。
大学という枠にとらわれず、全国規模で仲間と出会える点でも、起業志向の学生にとって理想的なスタート地点になるでしょう。
一歩踏み出すなら、ここから始めてみませんか?
興味のある方は、実際に起業経験を持つアドバイザーとの無料面談にぜひお申込みください。