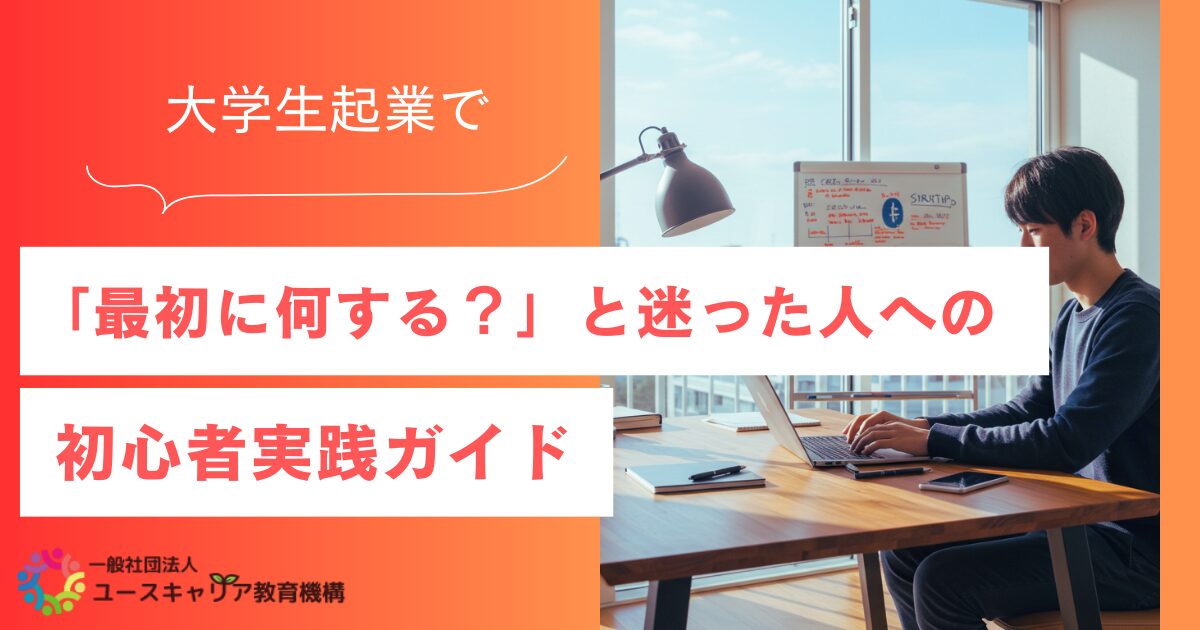大学生のうちに起業に挑戦してみたい。でも「最初に何から始めればいいの?」「一人で考えていても不安で進めない」と感じる人は少なくありません。ネットや本には情報があふれているのに、具体的にどう動けばいいのかは誰も教えてくれないからです。
本記事では、実際に起業を始めた先輩大学生たちが最初にどんな一歩を踏み出したのかを紹介しながら、仲間を見つける方法や大学・自治体の支援制度の活用法まで、実践的に学べるヒントをまとめました。読み終えたときには「自分も小さく始められる」というイメージが描け、漠然とした不安が行動に変わるはずです。

大学生起業で最初に「何する?」と迷う人は多い

なぜ「最初の一歩」でつまずくのか
「大学生のうちに起業してみたい」と思っても、多くの人が最初の一歩で立ち止まってしまいます。起業には明確な正解があるわけではなく、さまざまな道筋が存在します。そのため「事業計画から始めるべきか」「資金を集めるべきか」「仲間を探すべきか」と、同時に複数の要素を考えてしまい、優先順位がつけられなくなるのです。
さらに、身近にロールモデルが少なく、相談できる相手が限られていることも大きな要因です。自己完結で悩みが深まり、「失敗したらどうしよう」という心理的な不安も重なって、なかなか行動に移せません。実際には「小さく試す」「仲間と動く」といった具体的な方法から始められるのですが、そのイメージが持てないために足踏みしてしまう学生が多いのです。
本や動画だけでは限界がある理由
起業の情報は、本やYouTubeなどで簡単に手に入ります。知識を得る上ではとても役立ちますが、実際に行動する段階になるとそれだけでは十分ではありません。本や動画の多くは「一般論」や「成功者の後日談」であり、読者自身の状況にどう当てはめればよいのか分かりづらいからです。
また、情報収集に偏りすぎると「もっと調べなければ不安」という気持ちが強くなり、逆に行動が遅れてしまうこともあります。起業は実際に動きながら試行錯誤して学ぶもの。多くの先輩起業家も「本で得た知識より、実際に行動して得た学びの方が大きかった」と口をそろえています。インプットはあくまで出発点にすぎず、次は「小さくやってみる」経験が必要なのです。
起業イベントやOB訪問で感じる物足りなさ
大学内の起業イベントや1日限りのワークショップは、刺激やきっかけとしては有効です。しかし、長期的な成長や実践力の習得につながるケースは多くありません。先輩OBの体験談も参考にはなりますが、それはあくまで「その人にとっての成功ストーリー」であり、自分の状況にどう落とし込むかは見えにくいものです。
その結果、イベント参加後は一時的にモチベーションが高まっても、翌日から「結局何をすればいいのか」と再び迷ってしまう学生も少なくありません。根本的には「同じ志を持つ仲間と継続的に学び合う場」が不足しており、孤独感が強まるのです。こうした背景から「もっと実践的で、伴走してくれる環境が必要だ」と感じる人が増えています。
大学生に起業前に身に着けてほしい考え方
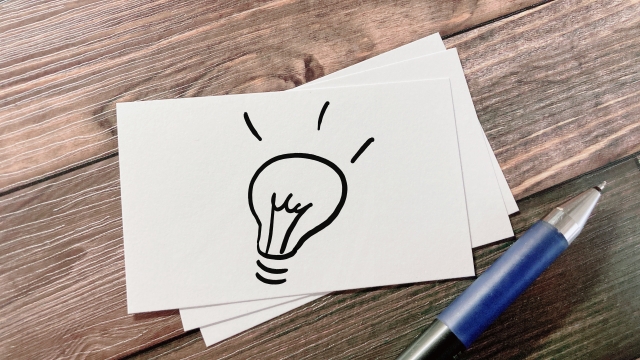
起業は「ゴール」ではなく「手段」
「起業=夢の達成」と考える学生は少なくありません。しかし、本来の起業は夢を叶えるため、あるいは社会の課題を解決するための“手段”に過ぎません。 会社をつくること自体をゴールにしてしまうと、資金調達や法人化の手続きばかりに時間を取られ、肝心の事業が前に進まないという本末転倒な状況に陥りがちです。
特に大学生の場合、「起業=かっこいい」「名刺に“代表取締役”と書きたい」といった肩書きへの憧れから、サービスを動かす前に法人化を急いでしまうこともあります。実際に成功している先輩起業家の多くは、まずサービスやプロダクトを動かし、必要になったタイミングで法人化してきました。
大切なのは「法人化した先に何を実現したいのか」という問いを常に持ち続けることです。この視点があれば、多少の困難にぶつかっても軸がブレず、着実に前進できます。
小さく試し、失敗から学ぶ姿勢
起業を考えると「まずは準備をしっかりしなきゃ」と思いがちですが、準備に時間をかけすぎると市場に出る前に熱量が冷めたり、アイデアが古くなったりしてしまいます。大切なのは、完璧さを求める前に小さな行動から試すことです。
たとえば、SNSでアイデアを発信して反応を見てみる、友人にサービスを試してもらう、簡単なWebサイトを作って問い合わせを受けてみる──そうした小さな一歩が大きな学びになります。多くの学生起業家も、最初は小規模な挑戦からスタートし、フィードバックをもとに改良を重ねながら事業を育ててきました。
失敗は恐れるものではなく、むしろ「早く小さく失敗する」ことで将来の大きなリスクを避けることができます。実際にやってみないと分からないことばかりだからこそ、勇気を持って一歩を踏み出す姿勢が、次の成長につながるのです。
大学生起業で必ず押さえるべき5つのステップ

起業というと「いきなり会社をつくらなきゃいけないの?」と身構えてしまう学生も多いかもしれません。しかし実際には、一気に大きなことをする必要はありません。段階を踏んで進めることで、リスクを抑えながら学びを積み重ねることができます。
ここでは、学生でも取り組みやすく、しかも安心して進められる「5つのステップ」を紹介します。「この順番で動けばいいんだ」とイメージできれば、迷いや不安もずっと小さくなるはずです。
ステップ1. 起業の目的を明確にする
最初に立ち止まって考えるべきなのは「なぜ起業したいのか」という目的です。ここが曖昧なままでは、仲間を集めるときも、資金調達をするときも説得力を欠いてしまいます。
「お金を稼ぎたい」「有名になりたい」という動機でも出発点にはなりますが、その奥にある「なぜそうしたいのか」を掘り下げることが大切です。社会の課題解決につなげたいのか、自分の強みを活かしたいのか──目的がはっきりすれば、アイデア選びや困難に直面したときの判断軸になります。
先輩起業家も「動機が弱いと途中で折れてしまう」と口を揃えます。だからこそ、最初に時間をかけてでも「自分の起業の意味」を言語化しておきましょう。
ステップ2. アイデアを形にする
身近な課題から考える
優れたビジネスの種は、意外にも日常の「ちょっと不便」「ここを変えたい」に隠れています。授業・サークル・アルバイトの中で感じた課題を出発点にすると、同世代の共感を得やすいです。実際、学生生活の中での“不満”を解決するサービスからスタートした成功事例は数多くあります。
既存サービスの改善点を探す
ゼロから新しいものを生み出す必要はありません。既にあるサービスの「もっとこうしたら便利になるのに」という改善点を見つけることが、実現可能性の高い一歩になります。ユーザーの声やレビューを調べると、改善の余地は必ず見つかります。
ステップ3. 事業計画を作る
6W2Hで整理する
「誰に・何を・なぜ・どこで・いつ・どのように・誰が・いくらで」というフレームワーク(6W2H)を使えば、漠然としたアイデアを具体的な計画に落とし込めます。頭の中だけに置かず、紙やスライドに書き出して仲間や支援者に共有できる形にするのがポイントです。
資金計画・収支シミュレーション
「どのくらいのお金が必要か」「いつ黒字になるのか」は避けて通れません。学生起業ではスモールスタートを前提に、現実的な数字を立てることが信頼につながります。無理のない収支計画があれば、親や金融機関からの理解も得やすくなります。
ステップ4. 資金を調達する
自己資金・クラウドファンディング
最初はアルバイト収入や貯金といった自己資金から始めるのが安心です。さらに、クラウドファンディングを活用すれば「本当に需要があるか」を試しつつ、支援者を集めながら資金を得ることができます。
補助金・助成金・大学支援制度
国や自治体、大学には学生起業向けの制度も整っています。「学生だから信用がない」と不安になるかもしれませんが、こうした制度はまさにその不安を補うための仕組みです。申請には事業計画が必要になるので、ステップ3と連動して考えるとスムーズです。
ステップ5. 開業して事業をスタートする
個人事業主と法人設立の違い
小規模に始めるなら、手続きも簡単でコストがかからない個人事業主がおすすめです。法人化は信用度や資金調達の面で有利ですが、登記や維持費がかかるため「必要になってから」で十分です。
まずはスモールスタートから
いきなり大規模に始める必要はありません。身近な人に試してもらいながら改良していくほうが、リスクは小さく、学びも多く得られます。先輩起業家たちも、最初は小さな実験からスタートし、その積み重ねが後の大きな成長につながっています。

先輩大学生は最初に何をして起業したか|事例紹介

鶴岡裕太さん BASE株式会社
鶴岡裕太さんは、大分県出身。大学在学中に、母親の「ネットショップを作りたい」という一言をきっかけに、誰でも簡単にネットショップを持てるサービス「BASE」を立ち上げました。当初は、家入一真さんや仲間と一緒に活動していたプロジェクト「Liverty」の中の一つのサービスにすぎず、「遊びで終わるかもしれない」という雰囲気もあったといいます。
最初の一歩は、2012年にサービスを公開したこと。Twitterで「作ったよ」と告知しただけで、想定以上のユーザーが集まり、サーバーがダウンするほどの反響がありました。鶴岡さんはこのときから「数字を伸ばすこと」に強く意識を置き、明確なKPIを設定して事業を進めていきます。
しかし、立ち上げ当初は法人化もされておらず、資金も不安定。消えてしまってもおかしくない状況の中で踏ん張れたのは、家入一真さんの伴走や、East Ventures・サイバーエージェント・グローバルブレインといった著名投資家の存在でした。彼らが「残すべき事業」と信じて出資してくれたことは、資金面以上に大きな支えになりました。
さらに2015年には、決済サービス「PAY.JP」を開始。ネットショップ作成だけでなく、売上や決済といったお金の流れまでカバーできるようになり、事業の収益基盤が強化されました。その後も数字を着実に積み上げ続け、BASEは2019年に東証マザーズへの上場を果たします。
この事例から学べるのは、起業のきっかけは意外にも身近な課題から生まれるということ。そして、完璧を目指して準備するのではなく、まず公開して反応を見ながら改善する姿勢が大切です。また、事業を継続するには仲間や投資家など「信じて支えてくれる存在」の力が欠かせません。鶴岡さんの歩みは、大学生起業のリアルな成功プロセスを示しています。
【参照:THE BRIDGE「大学生と起業家が作った『BASE』という奇跡」】
福島良典さん 株式会社Gunosy
福島良典さんは、東京大学大学院工学系研究科に在学中の学生エンジニアでした。データマイニングを専門に研究しながら、「研究成果を実装して社会で役立てたい」という思いを持ち、関喜史さん・吉田宏司さんと3名体制で開発に挑みました。
立ち上げたのは、ユーザーの“行動履歴”を解析し、その人に最適化したニュースを届けるキュレーションサービス「Gunosy」。従来のようにTwitterやFacebookのフォロー関係から話題を拾うのではなく、本人のツイートや「いいね」といったデータをもとに興味関心を抽出する点が特徴でした。最初は「1日1回メールで記事を届ける」というシンプルな形でスタートし、効率的な情報収集を実現しました。
最初の一歩は2011年夏。学内の20〜30人を対象にテストを行い、フィードバックを収集しました。その後10月にサービスを公開し、Twitterで告知すると、予想を超えるアクセスが集中してサーバーがダウンする事態に。早い段階から「メールの開封率やクリック率」といった指標をKPIに設定し、ユーザーにとって価値があるかどうかを徹底的に検証しました。
しかし、順風満帆ではありません。研究で「良い」とされたアルゴリズムが、必ずしも現実のユーザーに受け入れられなかったのです。そこで2012年5月、大幅なリニューアルを実施。UIを改善し、カテゴリ分けを廃止して「総合ニュース」として多様な情報を届けられるようアルゴリズムを刷新しました。UI/UX面ではGoodpatchと協業し、研究成果と現場ニーズを橋渡しする取り組みを進めました。その結果、ユーザー数は6,000人から7,500人以上に増加し、利用が安定的に定着しました。
福島さんの事例から学べるのは、完璧を目指すよりも「まず出す→測る→直す」を高速で繰り返すことの重要性です。また、データやAIの精度に頼るだけでなく、ユーザーの声に耳を傾けて修正する姿勢も欠かせません。さらに、KPIはPVや機能数ではなく、ユーザー価値に直結する数値に絞ることが成長を加速させます。仲間の強みを補完し合い、専門家を早期に巻き込むことも大きな推進力になります。
「まず公開してみる」勇気と、そこから改善を積み上げる柔軟さ。これがGunosyが成長した最大の理由であり、大学生起業に挑戦する人が学べるポイントといえるでしょう。
【参照:THE BRIDGE「情報の新しい流れをつくりたい–東大のエンジニア集団が立ち上げた次世代のマガジンサービスGunosy(グノシー)」】
小川嶺さん 株式会社タイミー
小川嶺さんは立教大学出身の学生起業家。学生時代に最初の事業「Recolle(アパレル系)」を立ち上げましたが、思うように成果が出ず撤退。その経験を踏まえて「次は自分が心からワクワクできる事業を」と再挑戦を決意しました。アルバイトを繰り返す中で、求人応募から面接・採用決定までにかかる時間の長さや不便さを痛感。「働きたいときにすぐ働ける仕組みが必要だ」と直感し、2017年に「タイミー」を創業しました。
立ち上げたのは、スキマ時間に働き、報酬も即日受け取れるスキマバイトアプリ。従来のレガシーな求人フローを取り払い、働き手に寄り添ったUXを実現しました。さらに人手不足に悩む事業者にとっても、即戦力をすぐ確保できるという利点がありました。
最初の一歩は、アイデアを一人で抱え込むのではなく、投資家や経営者に積極的に相談すること。複数の案を提示し、最もポジティブな反応を得られた「タイミー」に絞り込みました。開発初期はLINEを使った試作品で、事業者と学生を手動でマッチング。サービスを公開した2018年にはすでに5,000人を超える学生ユーザーを集めることに成功しましたが、事業者はわずか3店舗からのスタート。小川さん自身が地道に営業活動を重ね、価値検証を続けました。
ただ、ローンチ初月のマッチングは約20件と苦戦。当初の「ワーカーが空き時間を投稿→事業者がオファー」という仕組みでは利用が広がらず、公開からわずか1か月で「事業者が求人を出す→ワーカーが応募する」という現在の方式に全面転換しました。さらに戦略を飲食業界に絞り込み、週末の人手不足という切実な課題にフィットさせたことで高いリピート利用を獲得。数か月でトラフィックを一気に伸ばし、早期のPMF(プロダクト・マーケット・フィット)を実現しました。
創業初年度には3度の資金調達を実施し、数億円を確保。資本政策を積極的に進めることで、スピード感ある事業拡大に成功しました。その結果、2024年には登録ワーカー770万人、事業者25万拠点を突破し、東京証券取引所グロース市場に上場を果たしました。
小川さんの事例から学べるのは、まず「原体験から課題を発見する」ことの大切さ。さらに、完璧を待たずにMVP(最小限の実用的プロダクト)で検証し、反応を見ながら素早く方向転換する柔軟さが成長を加速させます。特に1か月でUIを全面刷新した判断力とスピード感は象徴的です。加えて、初期はターゲットを狭く絞り(渋谷区・飲食業界)、深く価値を提供することで確かな支持を得ることができました。
小川さんは「アイデアに価値はない。大事なのは実行と速度」と語ります。投資家や業界のキーパーソンを巻き込みながら、共感と熱意を持つ仲間と走り抜く姿勢こそが、タイミー急成長の原動力だったといえるでしょう。
【参照:TORYUMON「急成長タイミーの礎はいかにして作られたか。小川代表と振り返る「タイミー創業期」の物語」】
ユースキャリア教育機構 馬上大地さん(オンライン塾)
馬上大地さんは13歳で起業を志し、高校時代には100人規模の部活動を率いるリーダーシップを経験しました。大学進学後は「机上の学び」だけでなく、実践の中で経営を学びたいと考え、ユースキャリア教育機構に参加します。しかし19歳の時、父が急病で倒れ、経営していた20店舗規模の飲食チェーンを借金5,000万円ごと引き継ぐことに。学生でありながら経営の第一線に立たざるを得ず、倒産寸前からの再建に挑むことになりました。
最初の挑戦は、ユースキャリアの先輩から「準備ばかりせず、すぐ始めろ」と背中を押されて取り組んだ中学生向けオンライン塾。仲間とともに短期間でホームページやチラシを整え、スピード感をもって開業しました。小さな試みでしたが、「走りながら形を整える」という実践の姿勢を身につける貴重な経験になりました。
大きな転機は、父の経営していた飲食チェーンを引き継いだことです。引き継いだ当初は赤字だらけで、3ヶ月以内に倒産してもおかしくない状況。そこでコスト削減や店舗運営の改善を徹底し、半年で黒字化に成功します。その過程で税務・法務・経営判断などをユースキャリアの先輩に助けてもらいながら、現実的な打ち手を積み重ねていきました。家庭や学業も不安定になる中で、仲間や専門家の支えがなければ続けられなかったと振り返ります。結果的にM&Aによる再出発を果たし、10代で経営の修羅場を生き抜く経験をしました。
この経験から学べるのは、まず「仲間の存在」が最大の支えになるということ。先輩の知見、同期との切磋琢磨、後輩からの刺激という三層の関わりが、起業の孤独を和らげてくれます。さらに、完璧を求めず「まず小さくやる」ことで学びが加速すること。そして、苦境は一人で抱え込むのではなく、仲間・専門家・家族と共に乗り越えていくことが重要だということです。馬上さんは「経営は個人プレーではなくチーム戦」であり、人を育て、組織をつくり、文化を築く力こそが長期的な成功につながると語ります。
関連記事:「先輩・同期・後輩が絶えず居る環境で、経営/起業を学ぶべき」馬上大地インタビュー【The Specialist紹介】
ユースキャリア教育機構 清水大河さん(DX推進・Webマーケ)
清水大河さんは、学生時代に学習塾の運営責任者を務め、組織マネジメントや現場の課題に向き合ってきました。卒業後はWEBコンサルタントとして活動し、2021年10月に株式会社AnnRockを設立。DX推進や業務改善、WEB集客を軸に、企業の新規取組を支援するコンサルティング事業を展開しています。
最初の一歩は、机上のプランニングではなく、店舗経営者や中小企業の経営者に直接ヒアリングすることから始まりました。「人材不足」「集客の停滞」「業務改善の停滞」といった現場の生の声を拾い上げ、課題解決の糸口を探ります。そのうえで、正社員を抱え込むのではなく「優秀な若手人材×外部リソース」を組み合わせ、プロジェクト単位で支援できる仕組みを形にしました。
大きな転機となったのは、多くの企業が「感覚頼みの集客」や「古い慣習的な業務」に依存して改善が進まない現実に直面したときです。従来型の「外部顧問」のように助言だけをしても、社内で戦略が回らず成果が出ないことを痛感しました。そこでAnnRockは「プロジェクトメンバーとして伴走する」スタイルを選択。単なる指導ではなく実務を共に担いながら改善を進めることで、差別化を実現しました。実際、店舗集客の落ち込みに悩むクライアントに対しては、データ分析に基づいたWEB施策を導入し、広告費削減と売上改善を同時に実現した事例も生まれています。
清水さんの取り組みから学べるのは、起業アイデアは「現場の困りごと」から生まれるということ。そして、戦略を描くだけでなく、現場で一緒に回す仕組みを持つことが成果につながるという点です。また、集客や業務改善は一度で大きく変えるのではなく、データをもとに小さな改善を積み重ねていく姿勢が重要です。さらに、デジタルに強い若手世代が実務に入り込むことで、既存企業に新しい価値をもたらせるという強みも示しています。
【参照:清水大河 / 株式会社AnnRock代表「株式会社AnnRockのご紹介」】
成功した先輩が共通してやっていた「最初の行動」
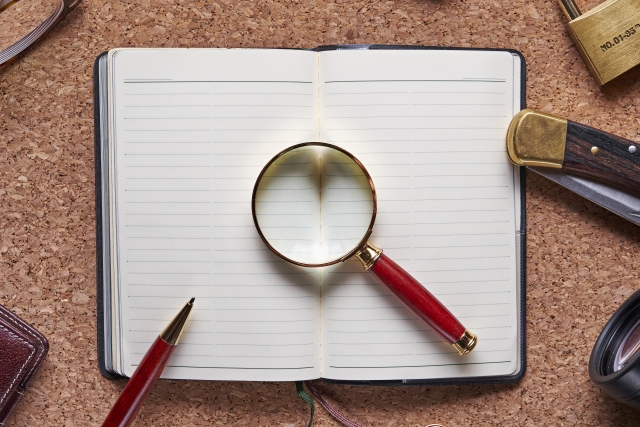
大学生起業で成果を出した先輩たちの事例を見ていくと、最初の一歩にはいくつかの共通点があることがわかります。
共通点1. 小さくても形にして公開した
多くの先輩起業家は「まず出してみる」ことを最優先にしています。Gunosyは学内で数十人にテスト公開し、すぐにフィードバックを得ました。BASEは「誰でも簡単にネットショップを作れる」というコア機能を公開し、最低限の決済ができる状態からスタートしました。馬上さんも、中学生向けオンライン塾を未完成のまま開業し、走りながら整えていきました。完璧さを求めるより、早く世に出して反応を得ることが、次につながる第一歩になっています。
共通点2. ユーザーや仲間からの声を早く取り入れた
サービスを公開した後は、一人で考え込むのではなく、外の声を積極的に取り入れる姿勢が共通しています。Twitterでの告知や口コミを通じて、予想以上の需要を知った起業家もいます。また、先輩や同期、後輩といった仲間のリアルな声を聞きながら改善を進めていくことで、独りよがりにならず、実際に必要とされるサービスへと近づけていきました。
共通点3. 小さな成功体験を積み上げた
最初の成功は決して大きなものではありません。「少額の決済が通った」「初めての受講生が来てくれた」といった小さな出来事が、自信と次の挑戦の原動力になっています。この積み重ねこそが、学生という立場でも事業を成長させていける理由の一つです。
自分だけで何をするか考えるのが不安な人のための対処法
大学生が「起業したい」と思っても、一人で考えていると不安が大きくなり、なかなか行動に移せないことがあります。そんなときに役立つのが、仲間や支援を得ながら小さく一歩を踏み出す方法です。
仲間を見つける
サークル・イベントに参加する
大学にはビジネス系や起業系のサークル、地域には学生向けの交流イベントが存在します。同じ関心を持つ学生と出会えるため、一人で悩むよりも多くの刺激を受けることができます。
SNSで呼びかける
TwitterやInstagramなどで「一緒に挑戦したい」と発信すれば、意外な反応が返ってくることもあります。文章化することで自分の考えが整理できるのもメリット。オンラインで意気投合した後に実際に会い、起業につながった例も少なくありません。
インターンに参加して同士を探す
スタートアップやベンチャー企業でのインターンは、志の近い学生に出会う絶好の機会です。現場のリアルを体験できるだけでなく、将来の共同創業者や相談相手とつながれる可能性もあります。
まずは小さく声をかけてみる(行動ハードルを下げる)
「一緒に起業しよう」といきなり誘う必要はありません。「少し意見を聞かせて」「小さな企画を試してみよう」といった軽い声かけから始めることで、自然に信頼関係や仲間意識が育ちます。
大学・自治体・企業の支援制度を活用する
大学にはビジネスプランコンテストや起業支援部門があり、自治体や商工会議所も学生向けの補助金や相談窓口を設けています。企業もCSRの一環で学生起業を支援することがあります。こうした制度を利用すれば、仲間づくりや資金面の不安を和らげながら、専門家のアドバイスを受けられます。
プログラムに参加して実践的に学ぶ
インキュベーションプログラムやアクセラレーターは、アイデア段階の学生も参加可能です。ビジネスモデルの作り方やプレゼン練習、メンタリングを受けられるので、短期間で大きく成長できます。同じ熱量を持つ仲間が集まるため、「一人で悩む」状態を抜け出しやすく、自分の行動も自然に加速していきます。
「何すれば大学生起業できる?」と悩む方へ|ユースキャリア教育機構のご紹介

学生のうちに起業してみたい──そう思っても、「自分にできるのか」「何から始めればいいのか」と不安を感じる人は多いでしょう。情報はたくさんあるのに、具体的にどう動けばいいのか分からず立ち止まってしまう。その悩みを解消できるのが、ユースキャリア教育機構です。
ユースキャリア教育機構では、大学生が実践的に起業を学び、仲間や先輩と切磋琢磨できる環境を提供しています。机上の勉強にとどまらず、小さなプロジェクトを実際に立ち上げたり、現役の起業家からリアルなアドバイスを受けたりできるのが大きな特長です。
「一人で始めるのは不安」という学生も、同期や後輩とのつながりの中で挑戦しやすい雰囲気を感じられます。卒業生の中には、スタートアップを創業して事業を拡大した人、上場企業でキャリアを積んでいる人、専門領域で起業に挑戦している人など、多彩な進路を切り拓いた例が多数あります。
また、ユースキャリア教育機構では無料説明会も実施しています。事業アイデアがまだ曖昧な段階でも参加できるので、「とりあえず一歩踏み出したい」という人にぴったりです。まずは気軽に説明会に参加し、自分の挑戦を支えてくれる仲間やメンターと出会ってみませんか?