この記事をご覧になっているあなたは、
「大学生のうちに起業コンテストに挑戦してみたいけれど、どんな準備をすればいいのか分からない」
「起業コンテストという言葉は聞いたことがあるけれど、実際の仕組みやメリットがよく分からない」
と感じているのではないでしょうか。そこで本記事では、学生向けの起業コンテストの基本的な仕組みや流れを分かりやすく解説します。さらに、実際の代表的なコンテスト事例、参加するメリット、成功事例から学べるポイント、そして失敗を防ぐための準備方法についても紹介します。

学生が知っておくべき起業コンテストの仕組みとは

起業コンテスト(ビジネスプランコンテスト、ビジコンとも呼ばれます)は、学生や若手が自分のビジネスアイデアをプレゼンし、審査員の前で競い合うイベントです。テーマは自由な場合もあれば、「社会課題解決」「環境」「テクノロジー」など特定の分野に限定される場合もあります。
応募時には、アイデア概要・収益モデル・市場分析などの書類を提出し、当日はプレゼンテーションやピッチ、さらに審査員との質疑応答を行うのが一般的です。
学生向け起業コンテストでよく重視されるポイントとは
こうしたコンテストで特に注目されるのは、新規性や独自性があるかどうか、技術面や資金面を踏まえて実際に実行可能かどうかといった実現性、そして社会課題や環境問題にどの程度貢献できるかといった社会的インパクトです。さらに、収益を生み出す仕組みが確立されているか、将来的に事業を拡大できる可能性があるかといった収益性も重要視されます。加えて、分かりやすく伝える力やチーム内での役割分担、挑戦に向かう熱意といったプレゼンテーション力やチーム力も評価対象となります。
起業コンテストのスタイル
起業コンテストにはさまざまなスタイルがあり、主催者が設定した課題に取り組む「テーマ型」と、自由な発想で挑戦できる「自由型」があります。開催規模も地域の大学や自治体が主催する小規模なものから、全国規模で大々的に行われるものまで幅広く存在します。また、開催形式についても、従来の対面型に加えてオンラインやハイブリッド形式が増えており、遠方の学生でも参加しやすくなっています。
学生が知っておくべき起業コンテスト4選
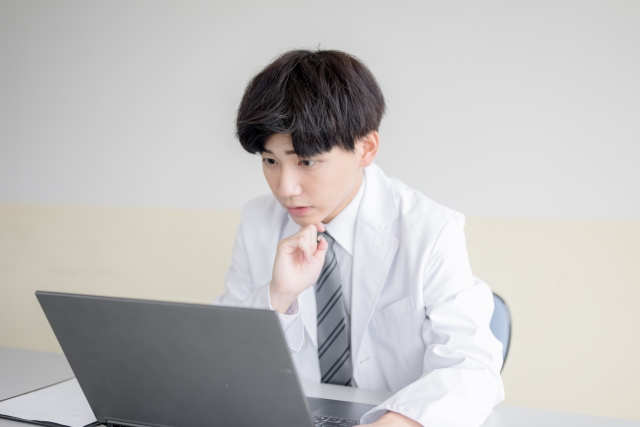
実際に大学生や若手が挑戦できる代表的な起業コンテストの事例です。いずれも全国から参加可能で、学生起業家の登竜門として注目されています。
コンテスト1.Frontier Pitch Tokyo
Frontier Pitch Tokyoはは、東京を拠点に開催されるピッチイベントで、学生や若手スタートアップが投資家や大企業の担当者に向けてアイデアを発表する場です。
- 特徴:採択されると、経験豊富なメンターによる伴走支援やネットワーク紹介が受けられます。単なるコンテストで終わらず、次の資金調達や事業提携につながるケースも少なくありません。
- 学生へのメリット:特に「本気で起業を考えている」学生にとっては、実際の投資家に自分のアイデアを売り込める貴重な場です。ビジネスプランをそのまま資金獲得のチャンスにつなげられる点で、他のコンテストよりも即効性があります。
。
コンテスト2.OIHビジネスコンテスト(大阪イノベーションハブ主催)
OIHビジネスコンテストは、大阪市のイノベーション拠点「大阪イノベーションハブ」が主催する全国規模のビジネスコンテストです。
- 特徴:書類審査からスタートし、最終選考に残れば大規模なプレゼンイベントで発表を行います。優勝者には賞金や事業支援プログラムが提供され、事業化の後押しが手厚いのが魅力です。
- 学生へのメリット:関西圏を中心に活動する学生起業家にとっては「地域発スタートアップ」としての注目を集められる機会です。特に地方から全国規模に挑戦したい学生には最適な舞台です。
コンテスト3.学生ベンチャーコンテスト(立命館大学 RIMIX 主催)
学生ベンチャーコンテストは、2004年から続く歴史ある学生向けビジネスコンテストです。対象は高校生・大学生・大学院生と幅広く、全国から多様なバックグラウンドを持つ学生が参加します。
- 特徴:大きな強みは「ブラッシュアップ型プログラム」。単に応募して審査されるのではなく、メンターによるアドバイスを受けながらプランを改善し、最終的に発表する流れです。コンテスト後もフォローアップがあり、受賞後の継続的な事業支援が受けられます。
- 学生へのメリット:初めて起業に挑戦する学生でも安心して参加でき、段階的に成長できるのが特徴です。いきなり完成度の高いプランを求められるのではなく、「挑戦して修正して学ぶ」というプロセスを重視してくれるため、起業初心者にとって最適な環境と言えます
コンテスト4.学生政策起業コンテスト – PEP for Youth
PEP for Youthは、一般的なビジネスプランコンテストとは少し毛色が異なり、「政策起業」の視点から社会課題の解決策を考えるユニークなコンテストです。
- 特徴:アイデア提出段階から政策提言を含むことが求められ、ビジネスの収益性だけでなく「社会課題にどのようにアプローチするか」が審査の中心となります。最終選考ではピッチ形式で発表し、課題認識や実行性、社会的意義が総合的に評価されます。
- 学生へのメリット:SDGsや社会起業に関心がある学生にとっては、社会貢献とビジネスを両立させるスキルを磨ける場です。将来的にNPO設立や社会事業に関わりたい学生に特におすすめです。
学生が起業コンテストに参加する4つのメリット
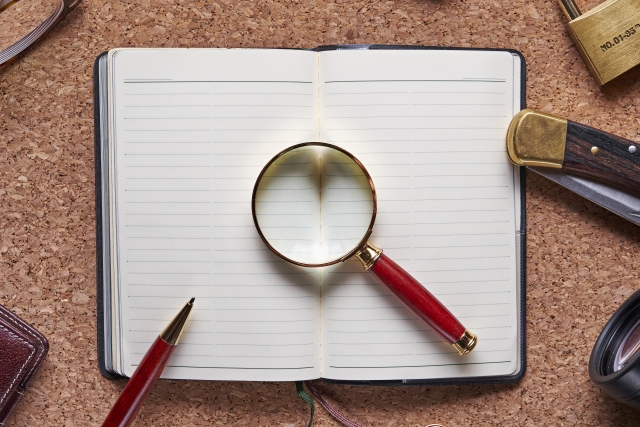
大学生が起業コンテストに参加するメリットは、ただアイデアを発表するだけにとどまりません。ここでは、学生が起業コンテストに参加するメリットを4つ紹介します。
メリット1.審査員からフィードバックをもらえる
起業コンテストに出場すると、実際に起業している経営者や投資家、企業の担当者といった審査員から直接アドバイスをもらえます。普段の授業やゼミでは得られないようなリアルな視点で、「この部分は市場規模をもっと具体的に示したほうがいいよ」とか「収益モデルの計算が甘いから修正すると投資家に響く」といった指摘を受けられるのです。これによって、自分たちでは気づけなかった課題が明確になり、次の挑戦にすぐ活かすことができます。
メリット2.賞金や事業支援を獲得できる
起業コンテストのもう一つの醍醐味は、実際に賞金や事業支援を手にできることです。優勝者や入賞者には数十万円〜数百万円の賞金が出ることもあり、それをそのまま開発費や広告費に使うことができます。さらに最近では、単なる賞金だけでなく、スポンサー企業や自治体からの事業サポートやオフィス利用、マーケティング支援といった実務的なサポートが付くケースも増えています。たとえば「JUMP」という全国規模のコンテストでは、ファイナリスト全員に事業拡大のサポートが提供されるので、優勝できなくても大きなメリットがあります。
メリット3.仲間やメンターと出会える
コンテストに参加すると、全国から集まる同世代の挑戦者たちと交流できます。アイデアをぶつけ合いながら刺激を受けるだけでなく、「実は同じような課題意識を持っていた」という仲間と出会い、一緒に新しいプロジェクトを立ち上げることもあります。また、審査員や運営スタッフとして参加しているメンターや起業家との出会いも貴重です。一度の出会いから将来の共同事業につながったり、アドバイザーとして長く支えてくれる存在になったりするケースも少なくありません。人とのつながりは起業の成功を大きく左右するため、このネットワーク形成の価値は非常に大きいと言えます。
メリット4.就活で強いガクチカになる
「起業コンテストに出たことがある」という経験は、就職活動において強力な武器になります。単にアイデアを考えただけでなく、実際に計画を練り、プレゼン資料を作成し、大勢の前で発表したという経験は「行動力」や「主体性」を示すものです。面接で「大学時代にどんなことを頑張りましたか?」と聞かれたときに、「全国規模の起業コンテストに挑戦して、最終審査まで進みました」と答えられるのは、大きな差別化要素になります。企業の採用担当者にとっても「ただの学生」ではなく、「挑戦心を持って行動できる学生」と映るため、評価が一段階上がります。

学生が起業コンテストで成功するコツ4選

せっかく勇気を出して参加しても、後から「もっと準備しておけばよかった」と後悔するのはもったいないですよね。ここでは、起業コンテストで失敗しない方法を4つ解説します。
方法1.アイデアのブラッシュアップをする
まず大切なのは、アイデアを「自分の頭の中の思いつき」で終わらせないことです。新規性はもちろん重要ですが、それ以上にユーザー視点を意識する必要があります。「本当に困っている人が使いたいか」「実際にお金を払う価値があるか」を考え、可能であれば簡単なプロトタイプを作ってユーザーに試してもらう、あるいはヒアリングを実施すると良いでしょう。
また、競合リサーチも欠かせません。似たようなサービスやアイデアがすでに存在している場合、その違いや差別化ポイントを明確にしなければ評価されにくいからです。「どの点が自分たちならではの強みなのか」を言語化しておくことで、審査員の印象に残る発表につながります。
方法2.ビジネスモデル・収益計画の準備
どんなに素晴らしいアイデアでも、収益が見込めなければビジネスとしては成立しません。開発にかかるコスト、販売価格、見込み客数、利益率といった数字を具体的に計算し、利益が出るまでのシミュレーションを用意しておきましょう。
さらに、リスクの洗い出しも大切です。資金繰りが厳しくなる可能性はないか、顧客をどう獲得するか、運営コストが膨らむ要因はないかなど、予想されるリスクを書き出しておくことで、質疑応答の場でも自信を持って答えられるようになります。
方法3.プレゼン資料とピッチ練習
審査員に伝える力を磨くことも成功のカギです。スライドや資料は見やすく、シンプルかつ要点を押さえたものに仕上げましょう。定番の構成は「問題提起 → 解決策 → 市場規模 → 収益モデル → 実行計画 → チーム紹介」。この流れに沿うと、誰にでも理解しやすいプレゼンになります。
また、発表時間を意識して何度も練習することが不可欠です。声のトーンや話すスピードを調整し、質問されそうな点を想定して回答を準備しておくと安心です。発表内容が同じでも、伝え方次第で審査員の印象は大きく変わります。
方法4.メンターの確保をする
個人で挑戦するのも良いですが、チームで取り組む場合は役割分担をはっきりさせることが重要です。代表者、技術担当、マーケティング担当、財務担当といった形で、各自の強みを活かせるように配置すると効率的に動けます。
さらに、経験豊富なメンターや起業経験者、ゼミの教員などに相談するのもおすすめです。第三者からのフィードバックは、自分たちでは気づけない改善点を浮き彫りにしてくれます。可能であれば、過去のコンテスト受賞者に話を聞くと、実際の準備や審査員の視点について具体的なアドバイスが得られるでしょう。
学生が起業コンテストで成功した実例3選

ここでは、実際に学生時代に起業コンテストへ挑戦し、その後のキャリアや事業につなげた成功事例を紹介します。
実例1.チケミー 宮下大佑氏
早稲田大学在学中にアパレルECサイトを立ち上げ、そこで得た経験をビジネスプランとして磨き、起業コンテストに挑戦したのが宮下大佑氏です。その活動がきっかけとなり、最終的にはNFTを活用したチケットプラットフォーム「Ticket Me」を創業しました。
彼の成功の大きな要因は、まず小さく始めて実際に手を動かしたこと、そしてコンテストを通じて得たフィードバックを柔軟に取り入れたことです。市場の反応を真摯に受け止め、改善を繰り返す姿勢が、学生から本格的な起業家へと成長する基盤となりました。
実例2.ヒュープロ山本玲奈氏
慶應義塾大学在学中に参加したビジネスコンテストで優勝し、その経験を原動力に起業へと進んだのが山本玲奈氏です。彼女は士業特化型の転職プラットフォーム「ヒュープロ」を創業し、短期間で成長企業へと育て上げました。
山本氏の強みは、資金調達やビジネスモデルを堅実に設計した点にあります。「一気に大きく」ではなく「小さく確実に積み上げる」という戦略を選んだことで、持続可能な成長を実現できました。学生時代のコンテスト挑戦が、自信と実行力を養う土台になったと言えるでしょう。
実例3. Progate 加藤將倫氏
東京大学在学中にオンラインプログラミング学習サービス「Progate」を立ち上げたのが加藤將倫氏です。もともとは「初心者が気軽に学べる教材が少ない」という課題感からスタートし、在学中に仲間とともにプロダクトを開発。そのビジネスプランをコンテストやピッチイベントで発表し、外部からのフィードバックを受けながらサービスを改善していきました。
成功の要因は、徹底的にユーザー視点に立ったプロダクト開発と、改善のスピード感です。教材の内容やUI/UXを何度も改良し、ユーザーの声を積極的に取り入れることで「学びやすさ」にこだわったサービスを完成させました。さらに、コンテストでの発表経験があったからこそ、自分たちのビジョンを分かりやすく伝えるスキルが磨かれ、資金調達やメディア露出にもつながったのです。
学生が起業コンテストで失敗しないためにユースキャリア教育機構へ

起業コンテストは、学生にとって学びや挑戦の場として大きな価値がありますが、同時に「準備不足で力を出し切れなかった」「アイデアを形にできなかった」と後悔してしまうケースも少なくありません。せっかく挑戦するなら、結果を出して次につながる経験にしたいものです。
そのためにおすすめなのが ユースキャリア教育機構 です。ここでは、29歳以下の若者が安心して挑戦できる仕組みが整えられており、学生が抱えやすい「ノウハウ不足」「仲間やメンターがいない」「継続できない」といった課題を解消できます。
そんな課題を持つ学生こそ、ユースキャリア教育機構を活用することで、起業コンテストでの失敗を防ぎ、次のステップにつなげられるでしょう。
まずは気軽に、ユースキャリア教育機構に相談してみてください



