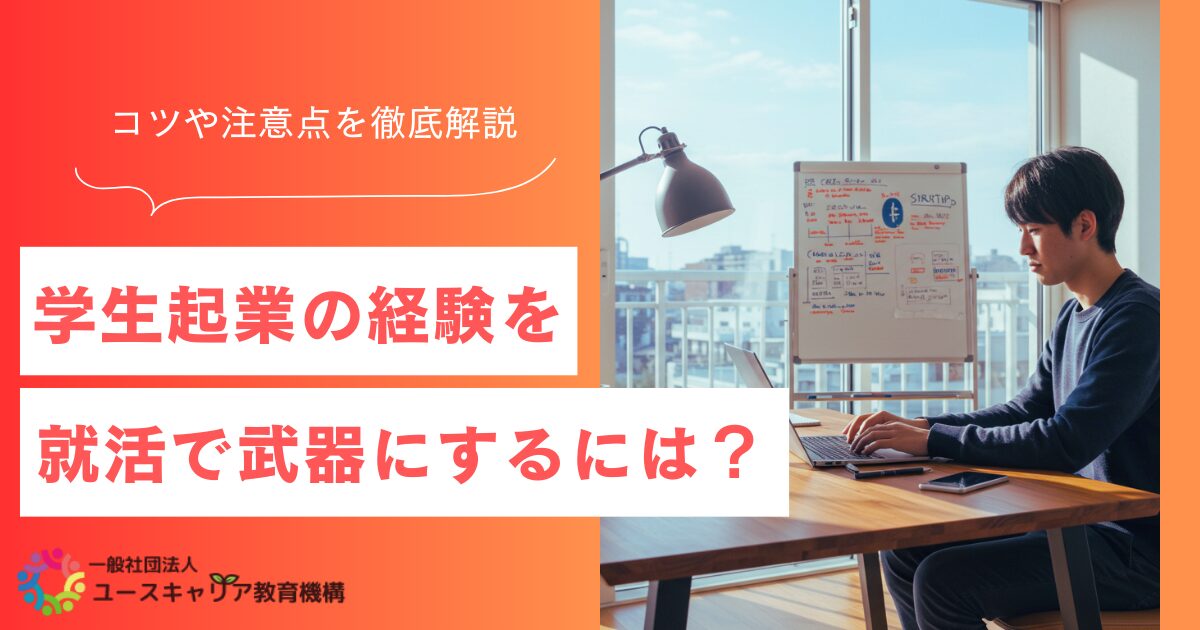学生時代に起業を経験した、あるいは起業に向けて動き始めているあなたにとって、就職活動は「起業経験がどう評価されるのか」「起業と就職、どちらを選ぶべきか」と悩みや迷いが尽きないタイミングかもしれません。
本記事では、企業が学生起業をどう見ているのかをはじめ、就活でプラスになるポイントや伝え方、就職から再起業につなげた先輩たちの事例まで、実践的に解説します。“起業か就職か”という二択ではなく、自分らしい挑戦の道を描くヒントを見つけてください。

就活生の学生起業経験に対する企業側の評価と本音

企業が学生起業経験に期待すること
自走力・行動力・課題発見力のビジネス基礎力
企業が学生の起業経験に対して最も期待しているのは、「即戦力」ではなく「将来的な成長力」です。
中でも高く評価されるのは、自ら課題を発見し、周囲を巻き込みながら行動に移した経験です。いわゆる「ポータブルスキル」と呼ばれるこの力は、業種や職種を問わず応用が利くため、多くの企業が注目しています。
例えば、課題を設定し、仮説を立て、実行し、改善するというPDCAサイクルを自走的に回した経験があれば、それは十分な強みになります。
企業の採用担当者は、事業の規模や成果よりも「なぜその起業に取り組んだのか」「困難をどう乗り越えたのか」といった背景とプロセスに強く関心を持っています。
「起業したけれど、大きな成果は出なかった」という学生でも、そこで得た思考や行動の経験を具体的に語ることで、プラス評価を得ることは十分に可能です。
ビジネス感覚や意思決定の早さへの期待
起業を経験した学生は、大学生活の中で数字感覚や意思決定の感度を実践的に養っているケースが多く、企業側はその「現場感覚」や「判断スピード」に高い期待を寄せています。
特にスタートアップや中小企業では、入社直後から裁量の大きな仕事を任せる傾向があるため、実践経験のある学生は歓迎されやすいです。
例えば、「売上を伸ばすために何を優先したのか」「失敗時にどうリカバリーしたか」といった意思決定の背景は、選考での好材料になります。
「学生の判断なんて浅く見られるのでは?」と不安に思うかもしれませんが、企業は完璧な判断を求めているわけではありません。
むしろ、自分の頭で考え抜き、行動に移した経験そのものを評価しているのです。
業界・職種によって異なる評価の傾向
スタートアップやベンチャーでは評価されやすい
スタートアップやベンチャー企業では、挑戦心・スピード感・変化への柔軟性が重視される傾向があります。そのため、学生起業経験とは非常に親和性が高く、実際に高く評価される場面が多くあります。
「失敗から学んだ経験」をポジティブに捉える企業文化が根付いているため、成功体験がなくてもチャレンジした姿勢自体が価値を持ちます。
また、こうした企業では、学生起業を経験した人に早くから責任あるポジションを任せることも珍しくありません。中には「学生起業経験者を優先的に採用する」と明言している企業も存在します。
「大企業にこだわらなくていいのだろうか」と迷う人もいるかもしれませんが、まずは評価されやすい業界や企業を理解し、自分の志向と合う環境を選ぶことが重要です。
大企業・官公庁系では慎重に見られることも
一方で、大企業や官公庁系の企業は、安定志向や組織文化を重視する傾向が強いため、起業経験が「異質なもの」として慎重に見られることがあります。
特に、「すぐ辞めるのでは?」「自分のやり方に固執して指示に従わなさそう」といった懸念が生まれやすい点には注意が必要です。
しかし、こうした懸念も伝え方次第で払拭できます。
起業経験を通じて自己理解が深まったことや、その結果として「なぜこの企業に入りたいのか」が明確であることを丁寧に伝えれば、むしろ志望動機の一貫性として評価されることもあります。
「安定志向の企業に興味があるけど、起業歴がネックにならないか」と不安な人も、自己分析と志望理由の言語化によって十分カバー可能です。
学生起業が就活にプラスに働く4つの理由

理由1. 起業のプロセスが評価されるから
就職活動において、企業が学生の起業経験を見るとき、重視するのは「結果」ではなく「プロセス」や「思考力」、そして「人間性」です。
どんな背景で起業を決意し、どのような意思決定を経て行動したのか。困難に直面したときにどう考え、何を選んだのか。そうした姿勢こそが、選考で評価されるポイントです。たとえば、「資金が足りない中で何を優先したか」「顧客からのフィードバックにどう対応したか」といった場面の判断や工夫は、企業にとって重要な評価材料になります。
成果が出なかったり、途中で事業をたたんだ経験があっても問題ありません。むしろ、リアルな困難にどう向き合い、そこから何を学んだのかを言語化できることの方が評価されます。

<メンバーコメント>
僕自身、立ち上げた事業は大きく成功したわけではありません。でも、「なぜ始めたのか」「どう判断したか」を言語化できるように準備したら、面接官にすごく興味を持ってもらえました。
評価されるのは結果じゃなくて、そこに至るまでのプロセスなんだと実感しました。
理由2. 即戦力としてのポテンシャルが伝わるから
起業を通じて、実際に「数字管理」や「顧客対応」、「マーケティング」「営業」などの実務を経験している学生は多く、その経験は入社後に即活かせる力として評価されます。
特に、限られたリソースの中で意思決定をし、責任ある立場で動いていた経験は、社会人1年目から活躍できるポテンシャルの証明です。これはベンチャー企業や中小企業のように、実行力や裁量を重視する職場で特に歓迎されます。
「自分の事業は小さかったし…」と不安に思う必要はありません。企業が見ているのは規模ではなく、自分がどこまで当事者意識を持ち、本気で取り組んでいたかという“熱量”なのです。
理由3. 自己理解が深まり、志望動機に説得力が出るから
起業という挑戦を通じて、「自分は何に価値を感じるのか」「どんな働き方が合っているのか」といった自己理解が深まった学生は、志望動機にも一貫性と説得力が出てきます。
企業は「成長できそうだから」「やりがいがありそうだから」といった抽象的な志望動機ではなく、その人の価値観や人生観に根ざした理由を求めています。起業経験を振り返ることで、「なぜこの業界なのか」「なぜこの企業なのか」といった問いに、よりリアルに答えられるようになります。
仮に起業と就職の方向性が違っていても、「今の自分にとって、なぜ就職が必要なのか」を明確に説明できれば問題ありません。むしろその思考の深さが強みになります。
理由4. 面接で印象に残りやすく、差別化できるから
学生起業はまだ少数派であり、その経験を持っているだけで、面接の場では確実に印象に残ります。
特に、何に悩み、どう乗り越えたかというストーリーは、他の就活生と大きく差をつけられる要素です。自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)の場面でも、リアルな実践経験を語れることは大きなアドバンテージとなります。
面接官に「この学生はユニークで、記憶に残る」と思わせるきっかけになるのが、起業のエピソードです。特別な成果や表彰がなくても構いません。大切なのは、「なぜ挑戦したのか」「その中で何を学んだのか」という、“あなただけの物語”を誠実に伝えることです。
学生起業経験が就活においてマイナスになる3つのケース

起業経験は就職活動において大きなアピールポイントになる一方で、伝え方を間違えると逆効果になることもあります。
ここでは、学生起業経験がマイナス評価に繋がりやすい3つの典型的なケースを紹介します。
ケース1. 成果や実態が曖昧なままアピールする
起業したことを語っても、その活動の中身が曖昧なままだと、企業はかえって不信感を抱きます。
「何の事業をしていたのか?」「収益は発生していたのか?」「どれくらいの期間続けていたのか?」といった質問に明確に答えられない場合、表面的なアピールと受け取られる恐れがあります。
特に、「名刺を作っただけ」「アイデアを温めていただけ」といった実態の薄い起業経験は、“起業”という言葉を使わずに、プロジェクト経験として話す方が良い場合もあります。
企業が本当に見ているのは「どれだけ本気で取り組んでいたか」です。失敗していても問題はありませんが、その中でどれだけ深く行動し、考え抜いたかを伝えられなければ、評価につながることは難しいでしょう。
ケース2. 企業理解や志望理由が浅く見える
「起業が本命で、就職はそのつなぎ」と思われてしまうと、企業側は「すぐ辞めるのでは?」とネガティブな印象を抱きます。
特に、「成長できそう」「視野を広げたい」といった抽象的な志望理由では、熱意や覚悟が伝わりません。
起業経験があるからこそ、「なぜこの企業を選んだのか」「どんな能力を活かして、何を実現したいのか」をしっかりと言語化する必要があります。迷いや葛藤があったとしても、それを丁寧に振り返り、今の意思として語ることで説得力が生まれます。

<メンバーコメント>
最初の頃は「起業も視野に入れてるけど、まずは就職で…」と曖昧な伝え方をしていました。
すると企業の方から「どうせすぐ辞めるんでしょ?」と正直に言われて、かなりショックを受けました。そこから、自分がなぜその企業で働きたいのかを本気で考え直すようになりました。
ケース3. 起業経験に固執して柔軟性が乏しく見える
起業経験を「自分のやり方が正しい」という主張の根拠として語ると、企業からは「扱いづらい人材」と見なされるリスクがあります。
特に、面接の場で「御社のやり方は非効率だと思う」「もっとこうした方がいい」といった発言をしてしまうと、協調性や素直さに欠ける印象を与えてしまいます。
就職後は組織の一員として、他者のやり方を理解し、必要に応じて柔軟に吸収する姿勢が求められます。自分の意見や考えを持つことは大切ですが、それを一方的に押し付けるのではなく、対話や相互理解を前提とした伝え方を意識することが重要です。
自分のビジョンを持ちながらも、「相手から学ぶ意欲がある」「一緒によりよい形を模索したい」という姿勢を見せることで、信頼につながります。
学生起業経験を就活で活かすための3つのコツ

学生起業は、取り組み方次第で就職活動において大きなアドバンテージになります。ただし、伝え方を誤ると「自己主張が強い」「企業理解が浅い」と見られることもあるため、工夫が必要です。ここでは、起業経験を就活でプラスに活かすための3つの実践的なコツを紹介します。
コツ1. ビジネス成果ではなく思考・行動プロセスを語る
採用担当者が学生起業経験を見る際、もっとも重視しているのは「思考のプロセス」や「行動に至るまでの判断力」「人間性」です。
年商や利益といった結果も参考にはされますが、それ以上に重要なのは、「なぜその事業を始めたのか」「どんな課題にどう向き合ったのか」という背景です。
たとえば、集客に苦戦したときに、何を分析し、どんな施策を試し、どう改善につなげたのか。そうしたプロセスを丁寧に語れることが、説得力を生みます。
「売上が出なかったのに話していいのだろうか?」という不安を持つ方も多いですが、数字の大きさは問題ではありません。
本気で取り組んだ経験があるなら、その中で何を考え、どう動いたかをしっかり伝えることが、何よりも評価されます。
コツ2. 企業に貢献できる要素を具体的に結びつける
起業経験を自分語りだけで終わらせてしまうと、「この会社で何ができるのか」が伝わりません。
大切なのは、経験を「企業での活躍」にどうつなげるかを明確にすることです。
たとえば、「PDCAを自走していた経験が、御社のマーケティング業務での改善提案に活きると思います」といった形で、具体的な業務との接点を提示すると説得力が高まります。
行動力や主体性などの抽象的なスキルだけでなく、営業・販促・数値管理といった実務に近い経験をリンクさせる視点が重要です。
「業界が違っていても関係あるのか」と不安に思う方もいるかもしれませんが、共通するスキルや姿勢は必ずあります。
抽象化と具体化を往復しながら自分の経験を結びつけていくことで、納得感のある自己PRが可能になります。
コツ3. 自分なりの失敗と学びを誠実に伝える
起業は誰にとっても挑戦です。失敗やつまずきがあるのは当然であり、それ自体は評価を下げる理由にはなりません。
むしろ、「どんな失敗をし、そこから何を学び、どう行動を変えたか」が明確に語れる人は、成長ポテンシャルの高い人物として評価されます。
表面的な成功エピソードよりも、葛藤や困難にどう向き合ったかの方が、面接官の記憶に残りやすい傾向があります。
「失敗を話すと印象が悪くならないか?」という不安があるかもしれませんが、誠実に事実を伝えたうえで、「その経験を経てどう変わったか」「今ならどうするか」を話すことで、かえって信頼を得ることができます。
失敗談はマイナスではなく、「乗り越える力を示すチャンス」だと捉えることが大切です。

学生起業→就職→再起業という選択肢

起業を経験した学生の中には、「このまま続けるか」「一度就職すべきか」で悩む人も多いはずです。
でも実は、起業→就職→再起業というキャリアルートは、近年の起業家にとって非常に現実的で、多くのメリットがある選択肢です。
就職で得られるスキルや人脈を活かす発想
一度就職することは、起業の道から外れることではありません。むしろ、実務経験・業界知識・人脈・チーム運営など、起業では得にくい力を伸ばす貴重な期間になります。
特に「資金調達」や「事業拡大」「組織マネジメント」などは、実際の組織での経験があってこそ身につくものです。就職は、起業への遠回りではなく、自分の挑戦に“深みと広がり”を加えるプロセスになり得ます。
「起業を諦めるようで怖い」と感じる人もいるかもしれませんが、視点を変えればそれは“より強く再挑戦するための一手”とも言えます。
あえて就職を選ぶことで、次の起業に必要な土台を築くのです。
再起業を見据えた企業の選び方
もし再起業を前提に就職を考えるなら、企業選びの基準も変わってきます。
大手企業=正解ではなく、「どんな力を得たいか」「経営視点をどう磨きたいか」に注目すべきです。
たとえば、ベンチャー企業やスタートアップ、事業責任者候補のポジションでは、経営者の意思決定を間近で見たり、自分で数字を管理する機会も多くなります。新規事業やマーケティングなど、起業に通じる職種も狙い目です。
企業選びの軸は、「この会社で何を吸収し、どんな起業につなげたいか」という逆算思考。これがブレないキャリア形成を支えてくれます。

<メンバーコメント>
僕は最初から「再起業前提」で就職しました。ベンチャーで営業職を選んだのは、自分で売上をつくる力を身につけたかったからです。1年間で、売上目標を任されたり、社長と直接やり取りする中で、経営の視点が身についたと思います。今の事業にもすごく活きています。
就職後に起業した先輩たちの事例紹介
実際に、「まずは就職して経験を積み、その後に独立する」というキャリアを選び、確かな実績を築いているユースキャリアの卒業生が多数います。
彼らの選択は、就職と起業を対立構造で捉えず、「自分に必要な学びを得る手段」として両方を活かしている点が特徴です。
樋口彩乃さん|「世の中の当たり前を更新する」社会起業家(株式会社barbarian 代表取締役/ユースキャリア教育機構 理事)
「水商売でもしてお金を稼ぎなさい」と母に言われるほど、家庭の経済状況が厳しかった中学時代から、猛勉強の末に県内トップの進学校へ進学された樋口さん。大学進学に向けては、奨学金や給付金を徹底的に調べ、生活費も含めてすべて自力で工面し、東京都立大学へ進学されました。
「貧困を抜け出したい」という一心で飛び込んだ東京で、東大の起業サークルに参加し、初めて「起業」という選択肢に出会われたそうです。
その後、シリコンバレーでのピッチ登壇や仲間との厳しい対話を経て、ユースキャリア教育機構に入会。仲間や先輩と向き合い続ける中で、自分の可能性を信じ、上場企業への就職を経て、社会人2年目で起業を決意されました。
現在は、株式会社barbarianを設立し、中高生や大学生に向けた探究学習・起業家教育のプログラムを展開。東京都や教育委員会と連携しながら、「生まれや育ちに関係なく、夢を持てる社会」を目指して活動されています。
【関連記事】
▶元超貧乏女子大生 → 親の所得で決まらない教育環境を作る会社起業!!
後上航さん|Webマーケティングで“想いを広める”仕組みをつくる起業家(株式会社Rover 代表取締役)
学生時代からWebメディアの運営や広告運用に携わり、大学卒業後は9か月間フリーランスとして活動された後上さん。さらに実務の幅を広げるため、東証プライム上場企業に入社し、デジタルマーケティング分野の業務に従事されました。
その後、より本質的な価値提供を追求するため、2022年に株式会社Roverを創業。Webコンサルティングや広告運用、メディア制作などを手がけています。
現在は、「想いのある商品やサービスが、適切なマーケティングの欠如によって世に届かない」という課題に向き合い、クライアント・その顧客・自社の三方に価値を還元するマーケティングを実践されています。
「100%の力を出せない依頼は受けない」という姿勢を貫き、事業利益よりも信頼関係と持続可能な価値創出を重視するスタンスに、全国から共感する事業者が集まっています。
石原郁也さん|地域と若者をつなぐ、キャリア教育の新しい形(ユースキャリア教育機構 理事)
石原さんは学生時代から地方創生や若者支援に強い関心を持ち、インターンやプロジェクト型学習に積極的に取り組まれていました。
卒業後はデジタルサービス系の大手企業に入社し、事業企画とマーケティングの両面で経験を積まれた後、構想していた「若者と地域をつなぐキャリア教育事業」を立ち上げ、起業されました。
現在は、自治体・高校・企業を巻き込んだ探究プログラムや、地域フィールドワークを全国で展開されています。
若者が自己理解を深め、同時に地域の未来にも関与していけるような、持続的な教育の仕組みづくりに取り組んでいます。
彼らに共通しているのは、一度就職することで足りなかった力や視点を補い、より実践的な起業につなげているという点です。
就職というステップは、起業の“終わり”ではなく“準備期間”。そう捉えることで、より現実的で持続可能な挑戦が可能になります。
学生起業と就活、どちらを選ぶか迷ったときの判断軸

「起業か就職か」。多くの学生がぶつかるこの問いに、明確な正解はありません。
どちらも選択肢であり、どちらにも価値があります。
大切なのは、“自分にとって”最適な道をどう見つけるかという視点です。ここでは、判断に迷ったときに考えたい3つの軸を紹介します。
リスク許容度とライフステージのバランスを考える
まず重要なのは、「今の自分にとって、どちらが現実的か」という視点です。
どんなに起業への意欲があっても、生活費や学費の負担、家族の理解、精神的な支えの有無など、自分のリソースが足りなければ長く挑戦を続けるのは難しくなります。
起業には、不安定な収入や時間管理の難しさといったリスクが伴います。
金銭面・精神面で余裕がない状態で飛び込んでしまうと、結果的に行動を制限してしまうケースも少なくありません。
「挑戦したいけど、金銭的に厳しい」と感じているなら、まずは一度就職して安定を得ることも、“起業に向けた準備期間”として意味のある選択です。
自分の目標にとってどちらが「最適な手段」かを考える
就職と起業、どちらが“正しい”かではなく、「どちらが自分の目的に近づける手段か」という逆算の視点を持つことが大切です。
たとえば、「将来、教育系の事業を立ち上げたい」と考えているなら、教育業界で制度や現場を学ぶために一度就職することも、理にかなった選択です。
営業力をつけたいなら営業職、プロダクトの検証を早く進めたいなら起業といったように、「やりたいこと」から逆算して今すべきことを整理することで、進むべき道は見えてきます。
「目標なんてはっきりしていない…」と感じている人も、心配はいりません。完璧な目標でなくても、“仮の目標”を立てて考えてみることで、道筋は見えやすくなります。

<メンターコメント>
大事なのは「どっちが正しいか」じゃなくて、「どっちが自分の目的に近づくか」です。
例えば「教育系の起業をしたい」という学生が、教育業界の現場や制度を知るためにまず就職するのは、目的から逆算した合理的な選択。視座が上がると、選び方も変わってきますよ。
周囲の声ではなく、自分の納得感を軸にする
就活や進路選択では、家族・友人・先輩など、さまざまな人からアドバイスを受けることがあるかもしれません。
でも最終的には、「自分が納得できるか」が最も重要です。
他人の価値観で進路を選んでしまうと、うまくいかなかったときに後悔や人のせいにしやすくなります。
一方で、自分で考え抜いて決めた道なら、たとえ失敗しても「自分で選んだことだった」と納得感が残ります。
「就職してもモヤモヤが消えなさそう」「今起業しなかったら後悔しそう」そんな直感も大事な判断材料です。
“後悔しないかどうか”という基準で考えることで、納得できる選択に近づきやすくなります。
「起業か就職か」で迷うことは、決して悪いことではありません。
それは、自分の将来に真剣に向き合っている証です。
必要なのは、「正しい答え」を探すことではなく、「自分にとって意味のある選択」を見つけることなのです。
本気で起業に挑みたい人へ|ユースキャリア教育機構のご紹介

起業か就職か。
どちらも簡単な道ではなく、悩むことに意味があります。
でも、ひとつ言えるのは、「本気で挑戦したい」という気持ちがあるなら、それを育ててくれる環境と出会うことが、何よりも大切だということです。
ユースキャリア教育機構は、学生起業からの就職・再起業までを視野に入れた、自己実現型のキャリア教育コミュニティです。
ただ学ぶだけでなく、実際にプロジェクトを動かし、社会に価値を生み出す経験を積みながら、仲間やメンターと共に“なりたい自分”に近づいていくことができます。
無料説明会のご案内
ユースキャリア教育機構では、ご興味をお持ちいただいた方のためにオンラインの「無料説明会」を実施しています。
無料説明会では、こんなことができます:
- あなたのキャリアや起業経験についての個別相談
- 実際に再起業を果たした卒業生のリアルな話を聞く
- 将来の不安やモヤモヤを整理するキャリア壁打ち
「自分に何が向いているかまだ分からない」
「でも、今のままじゃ何か違う」
そんな気持ちを抱えている人にこそ、一度話をしに来てほしいと思っています。
まずは、小さな一歩から。
あなたの挑戦を、私たちは本気で応援しています。