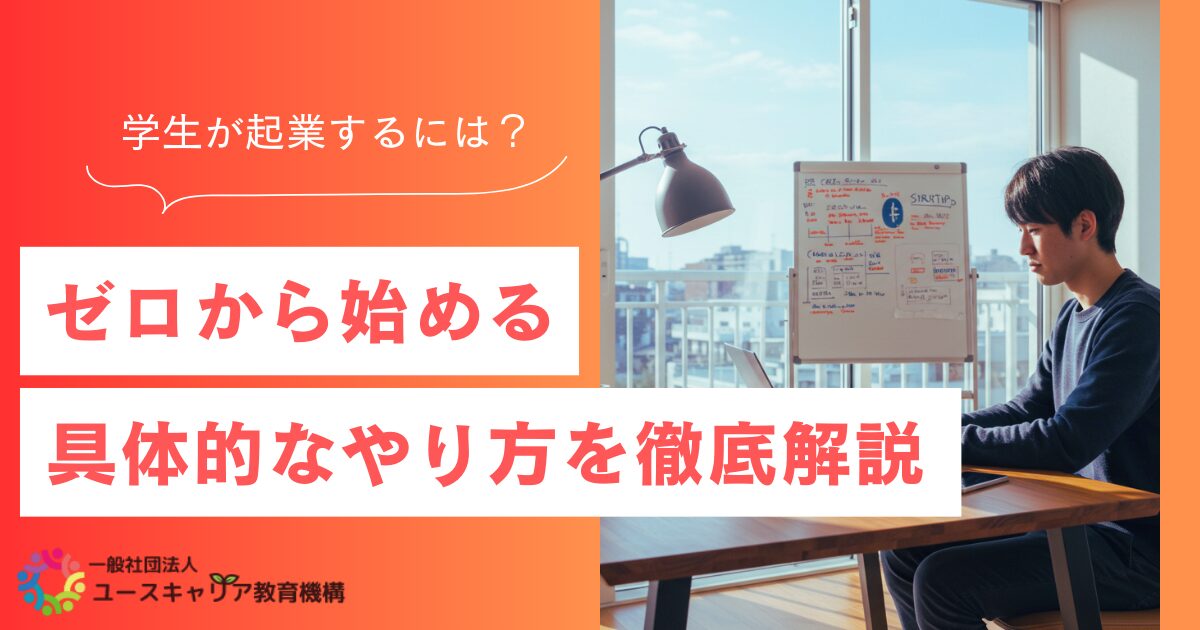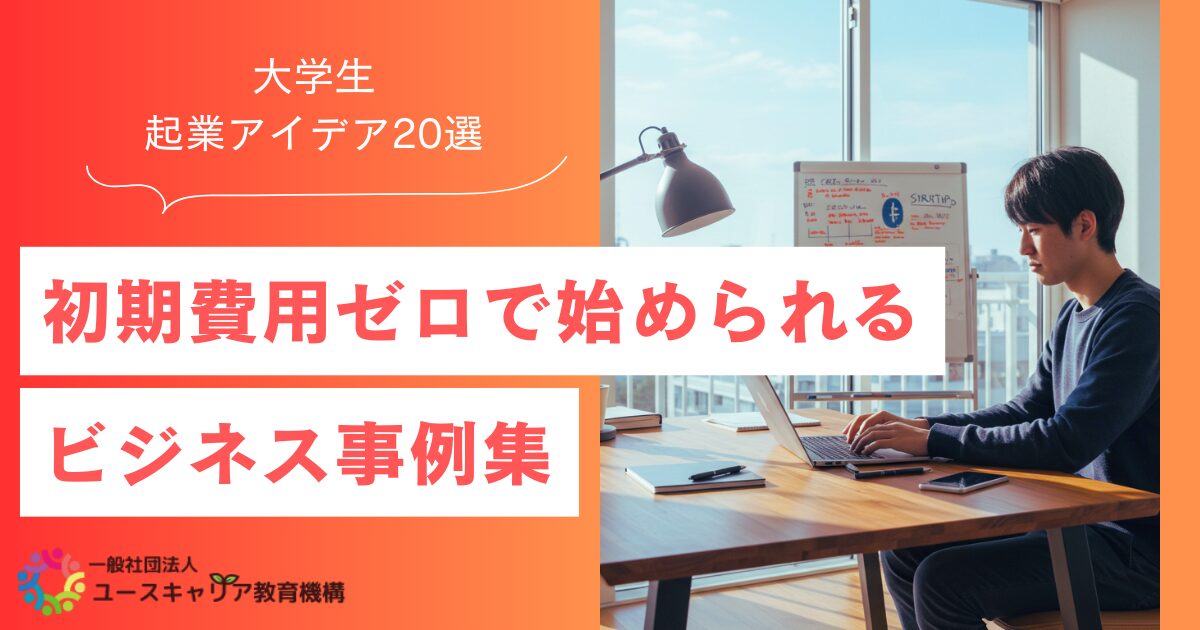「起業に興味はあるけれど、何から始めればいいのかわからない…」
そう考えている学生は多いのではないでしょうか?
実際、学生のうちに起業することで、自由な働き方を実現したり、将来のキャリアの選択肢を広げたりすることが可能です。最近では、クラシル(堀江裕介)やタイミー(小川嶺)など、多くの学生起業家が成功を収めています。
本記事では、「学生が起業するにはどうすればいいのか?」を 具体的なステップに落とし込み、未経験からでも始められる方法を解説します。
「起業を考えているけれど、一歩を踏み出せない」という方は、ぜひこの記事を読んで、行動のきっかけにしてください!

学生に合った起業のやり方をステップで紹介

学生が起業を成功させるためには、いきなり大きな勝負に出るのではなく、「今できることから少しずつ形にしていくこと」が大切です。
ここでは、未経験の学生でも実行できる起業のステップを以下の6段階に分けて解説していきます。
- ステップ⓪最低限のビジネス知識をインプットする
- ステップ①学生起業に合ったビジネスアイデアを考える
- ステップ②学内リソースを活用してビジネスアイデアを固める
- ステップ③アイデアを小さく形にして、テストマーケティングをする
- ステップ④収支計画を立て、必要な資金を調達する
- ステップ⑤身近な仲間を巻き込みビジネスをスタートする
それぞれの段階で何をすべきかを明確にすることで、着実に前進できるようになります。
ぜひ、自分がどの段階にいるのかを意識しながら読み進めてみてください。
学生起業のやり方|ステップ⓪最低限のビジネス知識をインプットする

起業の第一歩は、アイデアを考える前に「ビジネスの仕組み」を理解すること。
どれだけ面白い発想でも、収益構造が見えていなければ事業として成り立たせることはできません。
以下に、ビジネスを始める前に大学生が最低限抑えておくべき知識を整理していきます。
ビジネスモデルの基本構造
「ビジネスモデル」とは、一言でいえば
“どのように価値を届けて、お金を受け取るか”という仕組みのことです。学生であっても、事業を成立させるには次の4つの要素を明確にする必要があります。
① 何を売るか(価値提供):自分が提供する「商品やサービス」は何か?
たとえば、
- 自分のスキル(動画編集、デザイン、プログラミングなど)
- 手作りの商品(ハンドメイド作品、オリジナルグッズなど)
- コンテンツ(ブログ記事、動画、音声など)
- 体験や時間(学習支援、就活サポート、ガイドツアーなど)
などがこれにあたります。「価値提供」とは、“誰かの困りごとを解決するもの”や“日常を少し良くするもの”と捉えると分かりやすいです。
② 誰に売るか(ターゲット=顧客):自分の商品・サービスは、どんな人のニーズに応えるものか?
顧客の年齢や職業だけでなく、「どんな悩みを持っている人か?」までイメージできると、より具体的なビジネス設計が可能になります。
③ どうやって届けるか(流通・提供手段)
価値を“届ける手段”がなければ、どんなに良いサービスも使ってもらえません。
主な手段には以下のようなものがあります:
- SNS(Instagram、X、TikTokなど)で発信して集客
- ECサイト(BASE、STORESなど)や自作Webサイトで販売
- 対面での提供(イベント、学内販売、個別セッションなど)
- LINE、Zoom、アプリなどのデジタルツールを活用した提供
「どこで・どうやって届けるのか」を戦略的に設計することで、少ないリソースでも多くの人に価値を届けることができます。
④ いくらで売るか・どうやって売上・利益を得るか(収益の仕組み)
収益モデルにはさまざまなパターンがあります:
- 単品販売(1つの商品ごとに価格を設定)
- 月額課金(継続的なサービス提供)
- 広告収入(メディア運営やYouTubeなど)
- 投げ銭・サブスク支援(音声配信やクリエイター活動など)
価格のつけ方は、「原価」や「競合価格」だけでなく、「自分の時間・労力の価値」も含めて検討することが大切です。
この4つの要素を一つずつ丁寧に言語化することで、「思いつきのアイデア」から「収益を生むビジネス」へと一歩進めることができます。ビジネスを始める前の“地図づくり”として、まずはこのステップをしっかり押さえておきましょう。
売上と利益の仕組み
起業では「どれだけ売れたか」よりも、「どれだけ手元にお金が残るか(=利益)」が大切です。
利益を出すには、まずお金の流れを正しく理解することが必要です。
ビジネスの基本構造
売上 − 原価 = 粗利
粗利 − 経費 = 利益
※注釈
売上:販売して得た収入
原価:材料費や仕入れにかかる費用
経費:広告・送料・ツール使用料など
利益:最終的に残るお金
例えば、Tシャツを1枚1,000円で販売し、仕入れに500円、広告に300円かかったとします。
1,000円(売上)
− 500円(原価)= 500円(粗利)
− 300円(経費)= 200円(利益)
つまり、1枚売っても実際の利益は200円です。
この考え方を使えば、いくら売ればいいかを逆算することも可能です。たとえば月2万円稼ぎたいなら、
利益200円 × 100枚 = 2万円 利益500円の商品なら 40枚で達成
と考えることができます。
このように、「利益ベース」で目標を立てることが、現実的な計画につながります。ざっくりでもいいので、「どこでお金がかかって、いくら残るのか」を意識することが、継続できる起業の第一歩になります。
法律・税務・契約の基本
ビジネスを始めると、売上だけでなく「お金の管理」や「契約のルール」といった実務的な知識も必要になります。最初のうちは難しく感じるかもしれませんが、起業を継続していくうえで避けては通れない部分です。最低限のことだけでも、あらかじめ知っておきましょう。
多くの大学生は、法人を立ち上げる前に「個人事業主」として活動を始めています。これは、税務署に開業届を提出するだけで始められ、費用もかかりません。会社設立のように複雑な手続きが必要ないため、スモールスタートには適した形です。
起業によって得た収入が一定額を超えると、税務署への確定申告が必要になります。給与所得がある人は副業収入が20万円を超えると、事業収入のみの場合は年間48万円を超えると申告が必要になるケースがあるため、注意が必要です。
さらに、仕事のやりとりに関しても注意が必要です。友人や知人との間でも、料金や納品の条件を「なんとなく」で済ませてしまうと、後でトラブルに発展することがあります。できるだけチャットやメールなど記録が残る形で確認をとり、支払いやキャンセルなどの条件も最初に明確にしておくようにしましょう。
また、20歳未満の未成年が契約をする場合には、保護者の同意が必要となるケースもあります。とくに高額な取引やサービス提供では、「未成年だから契約が無効」と判断されるリスクもあるため、慎重に進める必要があります。
起業は自由で柔軟な活動である一方で、社会的な責任も伴います。だからこそ、契約や税金に関する基本的な知識を持っておくことが、信頼される起業家への第一歩になります。う。
学生起業のやり方|ステップ①学生起業に合ったビジネスアイデアを考える

学生起業に合ったビジネスモデルの特徴
ビジネスアイデアを考えるうえで重要なのは、「何をやるか」だけでなく、「自分にとって無理なく続けられる形かどうか」です。特に学生起業の場合は、限られた時間や資金の中で実行していく必要があるため、自分の状況に合ったビジネスモデルを選ぶことが成功への第一歩となります。
たとえば、初期費用が少なくて済むモデルは、学生起業にとって非常に相性が良いといえます。アルバイトで貯めたお金など限られた資金で始められることは、行動のハードルをぐっと下げてくれます。
また、時間や場所に縛られない働き方ができることも大切なポイントです。授業やレポート、試験期間など、学業とのバランスを取りながら取り組める柔軟なスタイルであれば、継続しやすくなります。
さらに、学生という立場そのものが強みになる分野を選ぶことも有効です。たとえば、同世代の悩みに共感できたり、学内のネットワークを活かして顧客や仲間を集めやすかったりと、「学生だからこそ提供できる価値」が事業の成長に直結するケースは多くあります。
起業アイデアを考える際は、自分の状況やリソースを踏まえながら、「自分だからこそ誰にどんな価値を届けられるのか」という視点を持ってビジネスモデルを組み立てていくことが大切です。

<ユースキャリアメンターコメント>
学生だからこそ、身近な課題がアイデアの出発点になることが多いです。
自分の“違和感”や“やりにくさ”にこそ、価値提供のヒントがあります。
メンターとして相談に乗っていても、「これって他の人も困ってたのか」と気づいた瞬間から、行動が早くなる学生は多いですね。
学生起業におすすめのビジネスアイデア例
ここでは、学生でも始めやすく、実際に多くの大学生起業家が取り組んでいる代表的なビジネスアイデアを、3つのカテゴリに分けて紹介します。いずれも、初期費用を抑えてスタートできるものや、自分のスキル・経験を活かせるものばかりです。
Web・IT関連
ITスキルやSNS活用力がある人におすすめのジャンルです。パソコン1台で始められ、在宅でも完結するモデルが多く、学業と両立しやすいのが特徴です。
- Webサイト制作:個人店や団体向けのホームページを作成
- アプリ開発:学生向け便利アプリやアイデアベースの開発
- SNS運用代行:企業や店舗のInstagram・TikTok運用をサポート
- デジタルマーケティング:広告運用やSEO対策のサポート業務
コンテンツビジネス
「自分の得意」を形にして届けるビジネスです。文章・動画・音声など、コンテンツ形式はさまざまで、発信や編集スキルがある人にぴったりです。
- 動画編集:YouTubeやPR動画の編集代行
- YouTube運営:自分のチャンネル運営や企業チャンネルの管理
- オンラインコンサルティング:受験・学習・就活などの知見を活かしたアドバイス
- スキル販売:noteやストアでのノウハウ提供、講座販売など
モノづくり・サービス業
「手を動かして形にしたい」「人と関わることが好き」という人におすすめの領域です。アイデアや創意工夫次第で、他と差別化しやすいのも特徴です。
- ハンドメイドEC:アクセサリーや雑貨などをネットショップで販売
- イベント企画:学生向けの交流イベント、学園祭企画など
- 学生向けサービス運営:履修支援、就活サポート、マッチングサービスなど
【関連記事】
▶学生起業におすすめの起業アイデアについてもっと知りたい方はこちら
学生起業のやり方|ステップ②学内リソースを活用してビジネスアイデアを固める

大学の「起業支援窓口」や「インキュベーション施設」を使う
最近では、多くの大学で学生向けの起業支援体制が整備されつつあります。これまでは「起業=一部の特別な人がやるもの」と思われがちでしたが、今では、大学のサポートを活用して、在学中から起業に取り組む学生も珍しくありません。
たとえば、インキュベーションセンターや起業支援室といった相談窓口では、アイデア段階から気軽に相談することができます。経験豊富な職員や外部の専門家が、事業の方向性や顧客の設定、収益化の仕組みについてアドバイスをくれることも少なくありません。
加えて、起業家教育に特化したゼミ・プロジェクト型授業、外部講師によるセミナーなどが用意されている大学も増えています。そうしたプログラムでは、実際にビジネスを動かしている現役起業家や専門家と出会うチャンスがあり、自分の視野や可能性を大きく広げるきっかけになります。
「このアイデアって誰に響くのか?」「このサービスはどうやって利益を出すのか?」など、起業についての悩みがあるときほど、専門家との壁打ちは有効です。自分ひとりで考えていても気づけなかった視点や、新たな可能性が見えてくることもあります。
起業に行き詰まったときは、一人で抱え込まず、こうした支援の場を活用して“壁打ち”をしてみましょう。短時間のアドバイスでも、ビジネスの精度が大きく変わってくるはずです。
起業経験のある「教授・先輩・OB」に相談する
学生起業を支えてくれるのは、制度だけではありません。実は身近なところに、頼れる“経験者”がいることもあります。
たとえば、起業経験のあるゼミの先生や、学生起業に挑戦した先輩などに今考えているアイデアを話してみることで、実践的なフィードバックをもらうことができます。
「それはすでに似たようなサービスがあるよ」「こういうターゲットの方がニーズがあるかもしれない」などと意見をもらえることで、自分ひとりでは気づけなかった視点が見えてきます。
もしアイデアに否定的な反応が返ってきたとしても、落ち込まずに「なぜそう感じたのか」を聞き、その理由をもとにアイデアをより良く磨いていくことが大切です。

<ユースキャリアメンバーコメント>
最初に先輩にアイデアを話したとき、“その視点は他の人にはない強みだよ”って言われて、自分の感覚に自信が持てるようになりました。
人に話してみることで初めて、自分の中のアイデアが形になる感じがしました。
ピッチイベントやビジネスコンテストに出てみる
アイデアがある程度形になったら、次はそれを外に向けて発信してみましょう。
実際に伝えてみることで「伝わるかどうか」「共感されるかどうか」といった視点からのフィードバックが得られます。
ピッチコンテストは各々の大学で開催されており、5分程度の短いプレゼン形式でアイデアを発表することができます。もう少し本格的に取り組みたい場合は、企画書や資料をまとめて発表するビジネスコンテストもおすすめです。ほかにも、学生同士でアイデアを共有するイベントなど気軽に参加できる場は多数あります。
こうした場で発表して得られるフィードバックは、アイデアの見直しや次のステップを考えるうえで大きなヒントになります。どこが響いたのか、どこが伝わりにくかったのかといった“生の反応”を受け取ることで、より実践的なブラッシュアップが可能になります。
さらに、イベントを通じて「一緒にやりたい」と声をかけてくれる仲間や、「応援したい」と言ってくれる人に出会えることもあります。アイデアを発信することは、自分のビジネスに共感する人とつながるきっかけにもなるのです。
まず人に伝えてみることで、次のネクストアクションのヒントを得ることができます。小さな場からでも構わないので、思いきって発表の場に出向いてみましょう。

学生起業のやり方|ステップ③アイデアを小さく形にして、テストマーケティングをする

どれだけ優れたビジネスアイデアも、「実際に誰かに使ってもらう」までその価値は見えません。
いきなり完璧なサービスを作ろうとするのではなく、完成前の段階で人に見せて改善の余地がないか探り、サービスをリリースする前にブラッシュアップを繰り返すのがおすすめです。
まずは簡単な“プロトタイプ”をつくって人に見せる
プロトタイプとは、「使い方や体験の流れを相手に伝えるための仮のサンプル」のことです。実際に開発や制作を完了していなくても、体験のイメージさえ伝われば十分に意味があります。
たとえば次のような形でもOKです:
- アプリの場合:figmaなどで作成した画面のデザインモック
- 商品・プロダクトの場合:身近な素材で組んだ試作品
- サービスの場合:Googleフォームで受付し、LINEで案内する簡易的な流れ
重要なのは、プロダクトやサービスの完成度ではなく、それを使うことでどんな体験ができるのかを伝えることです。本番環境と完全に同じでなくても、「こんな風に使えるんだ」「これなら便利かも」と想像できるような状態になっていれば、テストマーケティングとしては十分です。
この段階で得たいのは、「そもそも使ってみたいと思えるか?」、「誰にとって本当に価値があるのか?」といったリアルな感想や反応です。実際にユーザーに試してもらうことで、仮説とのズレや、思いがけない強みに気づくことがあります。
おすすめのプロトタイプの検証方法
検証方法①:SNSや学内イベントを活用して、簡単なテスト販売をしてみる
身近な場所を活用したテスト販売は、学生にとって始めやすく効果的な検証方法のひとつです。
たとえば、InstagramやXなどのSNSでサービスや商品の情報を発信し、「興味ある人いませんか?」「使ってみた感想が欲しいです」と呼びかけるのは非常に効果的です。
また、文化祭や学園祭のブースに出展したり、クラス・ゼミ・サークルの中で試してもらったりすることも有効な手段です。
LINEのオープンチャットを使ってアンケートを取ったり、販売告知をしたりする方法も取り入れやすいでしょう。
この段階で大事なのは、「売れたかどうか」という数字以上に、誰が、何に価値を感じてくれたのかを把握することです。その反応の中に、自分のアイデアの強みや、想定していなかったターゲット層の存在が見えてくることもあります。
検証方法②:身近な人に対してモニター販売をしリアクションを見てみる
もうひとつの方法は、友人や同級生など身近な人に対して、無料または低価格でサービスや商品を試してもらい、その場で感想を聞くスタイルです。
近しい関係だからこそ、率直な意見をもらえるのが大きなメリットです。たとえば、以下のようなポイントを聞いてみると、改善のヒントが見えてきます。
- なぜ使ってみようと思ったのか?
- 使ってみて良かった点や、不便だった点はどこか?
- どんな部分を改善すればもっとよくなると思うか?
こうした声には、自分では気づかなかったニーズのズレや改善点、思わぬ魅力が含まれていることがあります。それらを丁寧に受け止めて反映していくことで、サービスの完成度やターゲットとの相性を高めることができます。
学生起業のやり方|ステップ④収支計画を立て、必要な資金を調達する

まずは必要な“初期費用”と“運転資金”を明確にする
ビジネスを始めるときにありがちなのが、「まずやってみよう」と勢いだけでスタートしてしまうことです。
しかし、何にいくらかかるのかを把握せずに動き出すと、思わぬところで資金が足りなくなり、計画が頓挫してしまうリスクもあります。
まずは、起業にかかる費用を「初期費用」と「運転資金」に分けて整理してみましょう。
たとえば、商品やサービスの提供を始めるために、次のような費用が必要になるケースがあります:
- 材料費や印刷費、制作にかかる外注費(商品制作費)
- Webサイトの立ち上げに必要なサーバー代やドメイン代
- ロゴやチラシ、動画などの制作費(デザイン・動画外注費)
- 広告を出す場合のSNS広告費やフライヤー印刷費
- 商品を届けるための配送料や、イベント出展時の参加費
こうした費用を一度すべて書き出しておくことで、「最低限、どれだけの資金が必要なのか」が見えてきます。
そのうえで、「毎月どれくらいの支出が発生するのか」「それに対して、いくら売上を出せば赤字にならないのか」を逆算してみましょう。このように、収支を見通したうえで事業計画を立てることが、継続できるビジネスを実現するための第一歩です。
「学割」と「学内支援制度」をフル活用してコストを抑える工夫をしよう
学生起業においては、「できるだけお金をかけずに始める」ことが成功のカギになることもあります。そのためには、学生だからこそ使える“学割”や“学内の支援制度”をうまく活用することが非常に重要です。
たとえば、AdobeやCanvaなどのクリエイティブツールには、学生向けの割引プランが用意されています。デザイン費を抑えながらも、見栄えのよいチラシや資料を作ることが可能です。
また、大学によっては起業支援センターやインキュベーション施設があり、会議室やプリンター、法人登記に使える住所などを無料または格安で提供してくれているケースもあります。
さらに、創業を志す学生向けに、助成金や補助金制度など、資金面での支援を受けられるチャンスも用意されています。
こうした制度は、案外知られていなかったり、活用されずに終わってしまったりすることも多いため、まずは一度、自分の大学のウェブサイトやキャリアセンターで確認してみることをおすすめします。
「学生だからこそ使える支援」は、立派な起業資源です。無理に自己資金だけで背負いこまず、身の回りにある制度を味方につけていきましょう。できるのか、一度調べてみましょう。

<ユースキャリアメンターコメント>
学生には、“最初から完璧な起業”を目指すのではなく、“失敗しても立ち直れる範囲で試す”という発想が重要です。
環境資源を使い倒すことは、むしろ立派な経営判断。うまく使える人ほど、アイデアの実現スピードが速い印象があります。
小規模のクラウドファンディングも有力な選択肢
資金調達の手段として、クラウドファンディングは学生起業にとっても現実的で有効な方法のひとつです。
とくに、「なぜこの事業を始めたいのか」「どんな課題を解決したいのか」といったストーリー性があるプロジェクトであれば、多くの人からの共感を得やすくなります。
代表的なサービスには、CAMPFIREやREADYFORなどがあります。これらのプラットフォームでは、学生によるプロジェクトページの開設も可能で、特別な資格や実績がなくても挑戦できます。
リターン(支援へのお礼)は、必ずしもモノを用意する必要はありません。たとえば、「サービスの先行体験」や「プロジェクトの進行状況を共有する限定グループへの招待」など、低コストで体験価値を提供する形でも十分に支援を集めることができます。
また、支援者を集めるうえでは、SNSの活用が欠かせません。InstagramやXなどで自分の想いを発信し、知り合いや共感してくれる人にリーチしていくことが、成功の鍵となります。
特に、「社会課題を解決したい」「地域や文化を盛り上げたい」といった共感を呼びやすいテーマは、クラウドファンディングとの相性が抜群です。大きな資金を必要としない小規模プロジェクトでも、思いを丁寧に伝えれば、応援の輪が広がっていきます。
ビジネスコンテストや自治体の支援プログラムに“出せるだけ出してみる”も一つの戦略
学生起業にとって、資金調達の方法はクラウドファンディングだけではありません。ビジネスコンテスト(ビジコン)や自治体の起業支援制度など、公的・民間の支援プログラムに積極的に応募することも、有力な選択肢です。
前述したとおり、ビジコンでは優秀な企画に対して賞金や支援金が授与されるだけでなく、事業への注目度が高まり、外部の支援者とつながるきっかけにもなります。また、地方自治体によっては、学生起業家を対象とした助成金制度や創業支援プログラムを実施しており、10〜30万円程度の資金援助が得られることもあります。
NPOや企業、財団が主催する若者向けのチャレンジ支援プログラムも増えており、条件に合うものがあれば、積極的に“出せるだけ出してみる”というスタンスが成果につながりやすいといえるでしょう。
仮に受賞に至らなかったとしても、エントリーやプレゼンの準備を通じて、自分のアイデアを整理し、言語化する力が磨かれます。これは、起業を進めるうえで必ず役立つスキルです。
小さな挑戦の積み重ねが、大きな資金や仲間との出会いにつながることもあります。
チャンスを見逃さず、応募できるものには臆せず手を伸ばしてみましょう。
学生起業のやり方|ステップ⑤身近な仲間を巻き込みビジネスをスタートする

起業を一人で進めることもできますが、事業の幅を広げたり、継続しやすくしたりするうえで「仲間の存在」はとても大きな支えになります。
特に学生起業では、同じ目線で動ける仲間と一緒にスタートすることで、アイデアの質や実行スピードも大きく変わってきます。
自分のビジョンに共感してくれる仲間を見つける
起業においては、スキルのある人を集めることよりも、共通の想いや目的を持てるかどうかが何より大切です。
たとえば、自分のアイデアに興味を持ってくれている友人や、「何か挑戦してみたいけどきっかけがなかった」という同級生は、強力な仲間候補です。
起業系の授業やゼミ、学生団体、SNSでの発信を通じて、同じような志を持った人とつながる機会をつくるのも有効です。
仲間集めの段階から「エンジニアが必要」「マーケターが必要」と役割を強く意識する必要はありません。むしろ、「一緒に学びながら挑戦したい」と思える仲間と始めた方が、柔軟に成長していけるケースが多いです。
役割と責任範囲を“あいまいにしない”ことが継続のポイント
仲の良いメンバーと起業を始めると、最初は気軽に動ける一方で、役割や責任の分担があいまいなままだと、後々のトラブルの原因になります。
長く事業を続けるためには、立ち上げの段階で以下のような点をしっかり話し合っておくことが大切です。
- 誰が何を担当するのか(営業、SNS運用、会計など)
- 週にどれくらいの時間をコミットできるのか
- 意思決定はどうするか(代表が判断? 全員合意?)
- 売上や報酬をどう分配するか(完全ボランティアか、成果報酬か)
これは、友人関係にヒビを入れないためにも重要です。「仲良しグループ」ではなく、「プロジェクトチーム」としての意識を持つことが、継続と成果につながります。
チームで機能する仕組みをつくる
チームで動くうえでは、進捗や方向性をこまめに共有する仕組みを整えることが欠かせません。
たとえば、SlackやLINE WORKSでのタスク管理や、週1回の定例ミーティング、月1回の方向性確認の時間を設けるなど、無理なく情報をシェアできる仕組みをつくりましょう。
学生生活は授業やバイト、サークルなどやることが多いため、「ゆるくても続けられる設計」を意識することが、結果として事業の持続力にもつながります。
学生起業のリスクと対策

起業で掴みとれるチャンスもありますが、当然ながらリスクも多く存在します。
特に学生起業では、環境や経験の面からくる課題に直面することが多く、「なかなか継続できない」「踏み出せない」という声も少なくありません。
ここでは、学生起業でよくある3つのリスクと、それに対する具体的な対策を紹介します。
あらかじめリスクを把握しておけば、安心して一歩を踏み出す準備ができます。
よくあるリスク
① 経験や知識が足りず失敗する
学生起業で最も多い不安のひとつが、「自分が何を分かっていないのかすら分からない」という状態です。
ビジネスモデルの設計や集客方法、契約・税金といった実務的な知識は、学校の授業だけではなかなか身につきません。
その結果、「このやり方で本当に合っているのか?」「リスクを見落としていないか?」と不安になり、行動にブレーキがかかってしまいます。
② 協力者や相談相手がいない
周りに起業経験者や事業について相談できる相手がいない場合、自分だけで判断を重ねなければならず、孤独を感じやすくなります。
この状態が長く続くと「これで合っているのか」という不安が膨らんでいき、手が止まってしまうことも少なくありません。
③ 学業やバイトとの両立が難しい
学生は授業、課題、バイト、サークルなど、多くの時間を他に割かなければならないことが多いです。
その中で起業にも取り組むとなると、時間管理が一気に複雑になります。
計画が曖昧なままだと、すべてが中途半端になってしまい、「結局、起業は無理だった」と諦める原因にもなります。
対策
対策①:経験・知識不足への対策→ 実践の中で学べる「コミュニティ」に飛び込もう
ビジネスモデルや集客、法務・会計など、はじめのうちは分からないことだらけなのが当たり前です。重要なのは、「分からないからやらない」のではなく、「学びながら進める姿勢」を持つことです。
そのためには、起業家が集まるコミュニティや支援プログラムに参加し、実践的な環境に身を置くのがおすすめです。起業経験者の話を直接聞ける場では、教科書には載っていないリアルな視点や判断基準を学ぶことができます。
失敗や不安は、環境次第で成長のきっかけに変わります。わからないことを前提に、情報と人をうまく活用しましょう。
対策②:協力者・相談相手の不足への対策→ ネットワークづくりを積極的にする
起業初期は一人で判断を抱えがちですが、信頼できる相談相手がいるだけで、進めやすさと安心感は大きく変わります。
そのためにも、SNSやイベントを通じて、自分と同じようにチャレンジしている仲間や、少し先を歩く先輩とつながるのがおすすめです。
また、学内の起業部やインキュベーション施設、学生向けビジコンなどに参加して出会いのきっかけを作るのも良いでしょう。
「何をするか」よりも、「誰といるか」がモチベーションに直結する場面も多いため、自分が安心して相談できる関係性を築いておくことが、継続と挑戦の支えになります。
対策③:時間管理の難しさへの対策→ 具体的な行動スケジュールをつくる
学業、バイト、プライベートに加えて起業となると、どうしてもやるべきことが多くなります。
このとき必要なのは、時間の使い方を“感覚”ではなく“計画”で管理することです。
まずは、1週間・1ヶ月単位でどのくらいの時間が確保できるかを把握し、そこから逆算してやるべきタスクを整理します。大きな作業も、細かいステップに分けてスケジュールに落とし込めば、実行しやすくなります。
また、タスク管理アプリやカレンダーの活用、チームでの情報共有などを取り入れながら、無理なく継続できるペースを見つけていくことが重要です。る仲間を見つけ、自分に合ったペースで行動すれば、どんなリスクも乗り越えることができます。
まとめ|学生が起業するにはまず“小さな一歩”を踏み出すことが大事

「いつか起業したいけど、何から始めればいいかわからない」と感じている学生は多くいます。
しかし、成功している起業家の多くも最初は小さな挑戦からスタートしています。SNSでの発信、小さなサービスの提供、知人向けの販売など、すべて立派な第一歩です。
考えすぎて立ち止まるより、「やってみてから考える」方が、道は広がっていきます。 試行錯誤の中で、あなたなりのやり方がきっと見えてくるはずです。

<ユースキャリアメンバーコメント>
最初は『起業ってすごく特別な人がやること』と思っていたけれど、やってみたら“気になることを試す”の延長線にあると感じました。
自分の“やってみたい”を応援してくれる人たちと出会えたことで、踏み出すのがこわくなくなりました。
具体的な行動が思いつかない人へ、ユースキャリア教育機構へのご案内

「起業に興味はあるけど、1人で動くのは不安」
そんな人こそ、一歩目を“環境”に頼ってみてください。
ユースキャリア教育機構では、すでに800人以上の若者が、起業というテーマに向き合い、試行錯誤を重ねています。
同じ志を持つ仲間と出会い、先輩から実践的な学びを得て、想像もしなかった未来を描き始めたメンバーがたくさんいます。
興味を持った方はぜひこちらから無料説明会に申し込んでみてください!