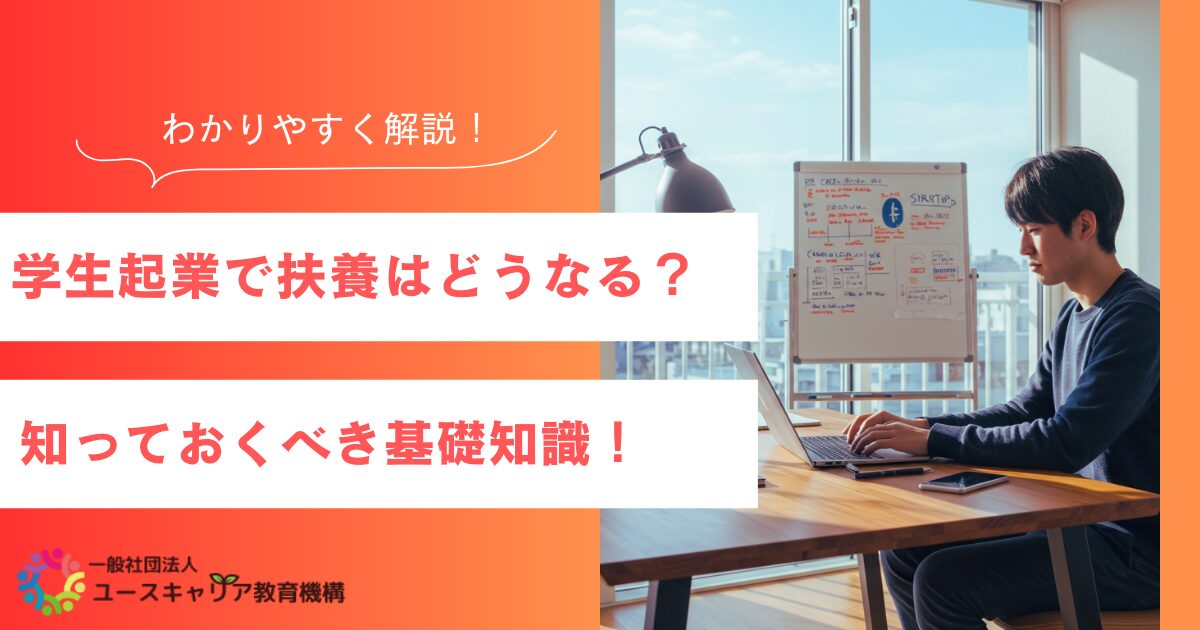この記事にたどり着いた方には、将来何かをなしとげたいと感じて、起業に挑戦しようと思ってみたけど扶養が怖い。実際に起業したら扶養がどうなるのか聞きたい。
そこで本記事は起業を目指す学生のために、扶養の一般常識を解説しながら、扶養を超えないための工夫、心構えまでご紹介します。

学生起業するなら知っておきたい、扶養制度の2つのポイント
「扶養」とは、親が子どもを経済的に支えている場合に、税金や社会保険の優遇が受けられる制度です。学生でも、一定の条件を満たせば「扶養内」として扱われますが、起業で収入が増えると条件を超えるケースが出てきます。
扶養には大きく分けて2つの種類があります。
- 税法上の扶養(所得税の控除):親の税負担を軽減できる仕組み。
- 健康保険上の扶養:親の健康保険に加入でき、保険料が不要になる仕組み。
これらの扶養についてさらに解説していきます!
ポイント1.税法上の扶養とは?
税金面での扶養条件は、以下の通りです。
- 所得が年間48万円以下
- 給与のみであれば年収103万円以下
この条件を超えると、親が受けている「扶養控除(最大63万円)」がなくなり、親の所得税・住民税の負担が増えてしまいます。
たとえば、起業で年間50万円の利益(経費を引いた後)が出た場合、それだけで扶養から外れる可能性があります。
ポイント2.健康保険上の扶養とは?
健康保険では、以下のような条件が必要です。
- 年収が130万円未満(見込み)
- 親の収入の半分未満
- 同一生計(仕送りなどで親とつながっている)
この130万円を超えてしまうと、自分で国民健康保険に加入して保険料を払わなければなりません。月1万円前後の保険料がかかることもあります。
学生起業で扶養対象外となることによる3つの影響

学生起業で得た収入が一定額を超えてしまうと、「扶養の範囲外」とみなされ、税金や保険に関してさまざまな影響が出てきます。ここでは、扶養を外れた際に具体的にどんなことが起こるのか、3つのポイントに分けて詳しく解説します。
影響1.親の税金が上がる
税法上の扶養から外れると、親が受けていた扶養控除がなくなります。これは、親の年間所得から一定額を差し引ける仕組みで、たとえば大学生を扶養している場合、年間最大63万円の所得控除が認められていました。
この控除がなくなると、親の課税所得が増え、結果的に所得税や住民税の支払額が数万円単位で増えることがあります。
たとえば、税率が10%であれば、63万円の控除がなくなることで約6.3万円の税金増となる可能性もあるのです。
つまり、扶養を外れることで「親の家計にも影響が出る」ことをあらかじめ理解しておく必要があります。
影響2.自分で保険料を払う必要がある
扶養の範囲内にいる間は、親の勤務先などの健康保険に「被扶養者」として加入できるため、自分で保険料を支払う必要はありません。しかし、扶養を外れると、自分で国民健康保険に加入し、保険料を支払わなければならなくなります。
また、20歳以上であれば、国民年金への加入も義務化されており、こちらも自分で保険料(月額約17,000円前後)を払う必要があります。
仮に健康保険料が月額10,000円、年金保険料が月額17,000円だとすれば、毎月27,000円、年間で約32万円近い負担が発生します。
これは起業によって得た収入のなかから支払うことになるため、実質的な「手取り」が大きく減ることになります。
影響3.確定申告が必要になる
扶養を外れた=自分で生計を立てる収入がある、ということは、税務署に対して自分で収入を申告する責任が発生します。アルバイトだけの場合は年末調整で済むことが多いですが、起業して個人で収益を上げるようになると、確定申告が必須です。
確定申告では、売上・経費・利益などを帳簿にまとめて税務署に提出し、所得税や住民税を計算して納付します。手続きが煩雑に思えるかもしれませんが、次のようなメリットもあります。
- 青色申告をすれば65万円の特別控除が使える
- 経費をしっかり計上すれば課税額を抑えられる
- 節税や資金管理の意識が高まる
とはいえ、正確な帳簿管理や知識が必要となるため、税理士や支援団体のサポートを活用するのがおすすめです。また、確定申告をスムーズに行うには、開業届とセットで準備するのがベストです。
学生起業しても扶養内に収める5つの工夫

「起業で収入が出てきたけれど、できるだけ親の扶養内でいたい」
そんな大学生も少なくありません。実は、ちょっとした工夫や知識を持っておくだけで、扶養の範囲内にとどまりつつ起業を続けることは十分可能です。
ここでは、税金・保険の観点から、扶養を維持するための現実的な対策を紹介します。
工夫1.経費を正しく活用する
まず押さえておきたいのが、「扶養判定は収入ではなく所得(収入-経費)で行われる」という点です。
たとえば、年間収入が100万円あっても、必要経費が60万円かかっていれば、所得は40万円となり、税法上の扶養(所得48万円以下)にとどまれる可能性があるのです。
経費として認められるものには以下のような例があります:
- 機材費(カメラ・PCなど)
- 通信費・SNS広告費
- 取材や打ち合わせの交通費
- 専門書・セミナー参加費
大切なのは「プライベートとの線引き」です。家計と事業用の財布を分け、帳簿をきちんとつけることで、経費の漏れや申告ミスを防ぐことができます。
工夫2.収入の分散・タイミングの調整
1年間の売上が扶養ラインギリギリ…そんなときは、「収入のタイミングを調整する」という選択肢もあります。
例えば、年末に大きな報酬が入る予定がある場合、その納品や請求を翌年にずらせないかをクライアントと相談してみることも有効です。
また、契約書上で「納品日=来年1月」などと記載すれば、その売上は来年分として処理することができます。ただし、収益認識には会計上のルールがあるため、不安な場合詳しい起業家さんに聞くのがおすすめです。
工夫3.勤労学生控除を活用する
大学生であれば、「勤労学生控除」という制度を利用することができます。これを使うことで、年間所得が75万円以下なら最大27万円の所得控除が受けられ、所得税や住民税の軽減につながります。
ただし注意点もあります。
- 親の扶養に入れる「所得48万円以下」という条件とは別枠であるため、扶養判定を考えるなら「控除後の所得」ではなく「控除前の所得」で見ておく必要があります。
そのため、勤労学生控除は「税金を抑える手段」としては有効ですが、「扶養維持」の判断には含まれない点に注意しましょう。
工夫4.青色申告と帳簿づけで控除最大化
起業するなら、税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出しておくのがおすすめです。青色申告を行うことで、次のような恩恵が受けられます。
- 65万円の特別控除が使える(複式簿記が必要)
- 家族への給与を経費として計上できる(条件あり)
- 赤字の繰越が最大3年間可能になる
これらを正しく活用すれば、課税所得を大幅に抑えることができ、扶養から外れずに済むケースも増えてきます。
工夫5. 親や保険組合との事前相談も忘れずに行う
健康保険の扶養基準は一律ではなく、保険組合ごとに細かい運用ルールが異なることがあります。たとえ年収が130万円未満でも、条件によっては扶養認定されない場合もあるため、早めに確認しておきましょう。
また、親が会社員の場合は、勤務先の人事・総務にも相談して、必要な手続きや注意点を聞いておくと安心です。

学生起業で「扶養」を外れる前に知るべき4つの準備

学生起業をして収入が増えると、避けて通れないのが「扶養の壁」です。
扶養を外れると、税金や保険、親の税負担など、これまでとは違った責任が発生します。ここでは、学生起業をする上で「扶養」について必ず知っておきたい4つの準備をわかりやすく解説します。
準備1.扶養基準の改正にも注目する
2025年には、これまで「年収103万円以下」とされていた扶養の基準が、年収150万円に緩和される動きが報じられています(※一部制度に限る見通し)。この変更により、これまでよりも多くの学生が扶養内で活動しやすくなる可能性があります。
ただし、税制や保険制度は複雑かつ流動的なので、定期的に最新情報を確認し、わからないことは税理士や支援団体に相談するのがベストです。
準備2. 社会保険と年金の支払いを見越して準備する
扶養を外れると、国民健康保険料や国民年金の支払い義務が発生します。大学生にとっては「突然の出費」に感じるかもしれませんが、これは将来につながる重要な支払いでもあります。
例えば:
- 国民健康保険:医療費の自己負担を軽減する仕組み
- 国民年金:将来の老後資金(65歳以降)の土台になる
収入があるなら、ここにきちんとお金を回すことも、一人の事業主としての責任感を養う第一歩です。
準備3.収入が伸びたら「法人化」も視野に入れる
もしあなたのビジネスが順調に伸びて、年間売上が1000万円を超えるくらいになってきたら、次の選択肢として「法人化(法人成り)」を考えるタイミングです。
法人にすることで以下のようなメリットがあります:
- 所得を法人と自分で分けて税率を抑えることができる
- 経費として認められる幅が広がる(家賃や車など)
- 銀行融資や大手企業との取引にも有利になる
もちろん法人化には設立費用や会計処理の手間が発生しますが、長期的に安定した事業運営を目指すなら避けて通れないステップです。
準備4.親と「扶養の変更」について相談する
収入が増え始めたら、できるだけ早めに親御さんと相談しておくことも大切です。というのも、扶養から外れると以下のような変化が起きます:
- 親の所得税・住民税の負担が増える(扶養控除が外れるため)
- 親の会社の健康保険から自分が外れ、自分で国民健康保険に加入する必要がある
事後報告で慌てるよりも、事前に話しておくことで、トラブルや混乱を防ぐことができます。
扶養を超えず学生起業起したい方はユースキャリア教育機構に相談へ

「起業に挑戦してみたいけど、扶養を外れるのが不安…」「税金や保険のことが難しくて、一歩が踏み出せない…」
そんな悩みを持つ大学生には、ユースキャリア教育機構がおすすめです。
ユースキャリア教育機構は、29歳以下の若者を対象とした実践型の起業育成コミュニティです。学生の起業に関する不安や疑問を、経験豊富なメンターや現役起業家に相談できる仕組みが整っています。
ユースキャリア教育機構では、起業スキルの習得だけでなく、お金や税金の基礎知識、扶養制度との向き合い方までしっかり学べる環境が用意されています。勉強会・ワークショップ・個別面談などのサポートも充実しているため、経営や制度の知識に自信がない方でも安心して参加できます。
また、イベントやメンタープログラムを通じて、「起業した先にある将来」まで見据えた行動力が身につきます。単なる起業支援にとどまらず、「なぜ自分はビジネスをやるのか」という根本的な目的設計も一緒に考えていけるのが、このコミュニティの強みです。
まずは気軽にユースキャリア教育機構相談してみましょう。
興味のある方は、実際に起業経験を持つアドバイザーとの無料面談にぜひお申込みください。