「医学生のままで起業なんて、無謀なのでは?」そんな声や不安に、心当たりがあるかもしれません。
確かに、医療という専門職を目指す中で、起業という選択肢は少数派かもしれません。ですが、現代は“医師になること”だけがゴールではない時代です。社会の変化とともに、医学生だからこそ挑戦できる起業ジャンルや支援環境も広がっています。
この記事では、実際に起業に挑んだ医学生のリアルな事例、ぶつかる壁、リスクの捉え方、そして一歩踏み出すための選択肢までを網羅的に紹介。進路やキャリアに悩むあなたが「医学生のままで挑戦していい」と思える後押しになる内容をお届けします。

起業に関心を持つ医学生が増えている背景

臨床医だけに進むキャリアに違和感を持つ学生の増加
近年、「臨床医としての道」に違和感を持つ医学生が増えています。背景には、医療現場の過重労働や地域格差、訴訟リスクなど、将来の医療をめぐる構造的な課題が存在します。診療報酬の抑制や制度改革によって、医師が疲弊しやすい環境が続く中、「このまま医師一本で生きていくべきなのか」と早い段階から悩む学生も珍しくありません。
こうした現実に触れる中で、「医師の専門知識を活かしながら、異なる形で社会に貢献する方法はないか」と模索する声が生まれ、キャリアの選択肢として“起業”を視野に入れる学生が増えつつあります。
「医師免許=安定」への疑問と価値観の多様化
「医師免許さえあれば一生安泰」という考え方に、疑問を持つ医学生も増えています。特にZ世代では、「やりがい」や「自己実現」、「社会的インパクト」といった価値を、安定や地位よりも重視する傾向が強く、自分の想いに素直なキャリア選択を目指す人が増えています。
医師免許という専門性をベースにしながら、「社会にどう価値を提供できるか」を考える志向が強まり、それが起業や複線的なキャリアへの関心につながっています。これは時代の価値観の変化に合わせた、医学生たちの新しい選択とも言えるでしょう。
医療×社会課題に関心を持つ学生の広がり
離島医療・認知症・難病などで現場課題に触れる機会が増加
i医学生が地域医療や高齢化、難病支援といった現場の課題に触れる機会が、実習や課外活動を通して増えています。
特に、離島医療や介護施設では、制度では解決できない複雑な問題に直面する場面が多く、そうした現実が医学生の問題意識を強く刺激しています。
また、自分の家族や友人が病気や障害と向き合っている姿を見たことをきっかけに、当事者の視点で課題を捉えるようになった学生も少なくありません。
その経験を通して「単に治療を行うだけでなく、そもそも制度や仕組みを変える側に回りたい」と感じるようになるケースも増えています。
こうした気づきが、「自分の手で何かを始めたい」という強い動機につながり、起業という道に目を向けるきっかけとなっています。
医療の枠を超えて「社会を変えたい」と考える動機の台頭
近年の医学生の中には、医療という領域にとどまらず、教育、福祉、地域づくりなど、幅広い社会課題に関心を持つ人が増えています。
「なぜ病気になるのか」「なぜ医療費はこれほど高いのか」といった医療の背景や構造そのものに疑問を抱き、社会の根本に目を向ける姿勢が強まっています。
そうした中で、現場の限界を痛感する学生たちは、「医師として治療するだけでなく、仕組みを変える側に立つには経営や事業化の力が必要だ」と気づき始めています。
その結果、「医師免許を持った社会起業家」というキャリア像にも共感が集まり、医療×ソーシャルビジネスの分野で挑戦する学生も少しずつ増えてきました。
医療の枠に縛られず、「社会を変える」ための手段として起業を捉える動きが、これからの医学生にとって自然な選択肢になりつつあります。
SNS・メディアで医学生起業家が話題になる時代背景
起業ストーリーが可視化され、共感と刺激が生まれている
近年、SNSやYouTube、noteなどのメディアを通じて、医学生が起業に挑戦する姿が日常的に発信されています。
「完全栄養チョコレート」「VR×医療支援」「在宅医療マッチング」など、これまで想像しにくかったビジネスが、身近な事例として次々に紹介されるようになっています。
こうしたストーリーに触れることで、「同じ医学生でもここまでやっているんだ」「もしかしたら自分にもできるかも」と感じる学生が増加しているのです。
起業は特別な人だけの話ではなく、少し先を行く先輩たちの選択肢として現実味を帯びてきています。
特にX(旧Twitter)やInstagramでの発信は、医学生同士の会話の中でも話題になりやすく、自然と起業に対する関心が高まる環境が形成されています。
医師国家試験合格を前提としないキャリアも選択肢に入り始めている
以前は「まず医師国家試験に合格し、臨床経験を積んだ上で起業する」というルートが一般的とされてきました。
しかし今では、在学中に事業を立ち上げ、そのまま経営に専念する医学生も少しずつ登場しています。
国家試験合格後にあえて臨床へ進まず、研究・スタートアップ・事業開発の道を選ぶケースも出てきており、キャリアの選択肢は着実に多様化しています。
起業を通じて「医師免許がなくても社会に価値を届けられる」という実感を得たことで、国家試験をゴールではなく、選択肢の一つとして捉える医学生が増えているのです。
医師であることがキャリアの「前提条件」ではなくなり、「どんな社会課題を解決したいか」という視点から逆算して進路を考える時代が始まっています。
実際に起業した医学生たちの3つの事例
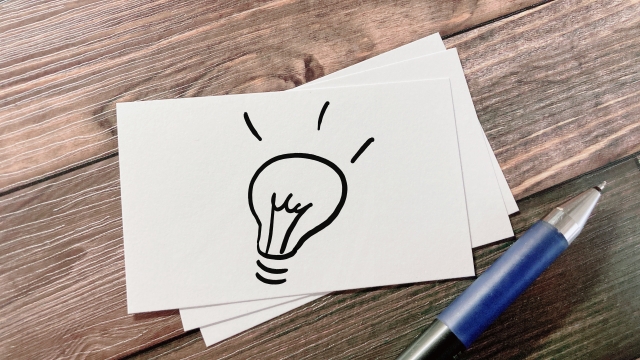
事例1.IoTを使用した介護事業者向けのアプリ開発(株式会社直井ホールディングス 直井 香澄)
新潟大学医学部に在学中の直井香澄氏は、医療現場での課題に直面した経験をきっかけに、「地域医療を支える持続可能な仕組みづくり」を掲げて起業に踏み出しました。医学生という立場にありながら、介護現場のEラーニングアプリ開発を中心に、ITの力で人材育成と現場改善を支援する事業を展開しています。
直井氏は大学の地域枠制度で学びつつ、新潟県が実施するヘルスケアアカデミーやイノベーター育成コースを通じて、課題解決型の思考を深めてきました。これらの経験が、単なる「医療従事者」ではなく「仕組みを作る側」へと視野を広げる転機となったと語っています。
提供しているEラーニングアプリは、施設ごとの課題に応じてオーダーメイドで教材を作成できる柔軟性と、学びを継続しやすいUI設計が特長。さらに、オンライン自習室などを通じて、介護人材の育成環境を整備する取り組みも進めています。
「一人の医師ができることには限界がある。だからこそ、システムやテクノロジーの力を使えば、より多くの人を支えられる」
この言葉に象徴されるように、直井氏の挑戦は「現場に向き合う医師」と「社会構造を変える起業家」の両立を目指したものです。医師として地域に貢献する9年間の義務年限を果たしつつ、並行して起業家としてのキャリアも積み上げていくとのこと。その姿は、医学生が自分自身の可能性を広げる上でのリアルなロールモデルとなるはずです。

<メンターコメント>
医学生は専門知識が蓄積されている分、現場の問題を見過ごせないという責任感が強くなる傾向があります。直井さんのように“目の前の人を救うだけでなく、仕組みで現場を変える”という発想は、医学生が起業する際の優れた起点だと感じます。医師になる道と起業の道を二択にしない姿勢にも、大きな価値があります。
【参照:株式会社アイドマ・ホールディングス「株式会社直井ホールディングス」(https://biz-maps.com/item/b7lQGeRgYr】
【参照:医師ナビにいがた「地域枠での経験と学びを活かし、医学生で起業」(https://www.ishinavi-niigata.jp/person/21090/】
事例2.難病患者向けのD2Cチョコレート開発(株式会社SpinLife代表 中村恒星)
北海道大学医学部に在学中の中村恒星氏は、自身の難病体験と患者会での出会いから、「食べる楽しみを奪われがちな人にも、美味しさと栄養を届けたい」という想いで起業を決意。完全栄養チョコレート「andew(アンジュ)」を開発し、医療と食の課題を同時に解決するD2Cモデルの事業を立ち上げました。
andewの開発背景には、表皮水疱症などの口腔障害を持つ患者の「食の制限」があります。一般的な栄養食品や医療用補助食品は、機能性はあっても「楽しさ」や「美味しさ」が欠けている。中村氏はチョコレートという媒体に、形状・保存性・嗜好性・メッセージ性といった多くの可能性を見出し、「患者も健常者も同じものを楽しめる」商品として設計しました。
世界初の完全食チョコレートandewは、9種の栄養素をバランスよく配合し、見た目やパッケージ、ギフトとしての設計にもこだわった製品。商品開発だけでなく、患者や支援者との共創を重視し、SNSやポップアップストアなどでブランドの共感性を高めています。
中村氏は、医師・研究者・経営者の3つの視点を行き来しながら、社会的意義とビジネス性の両立を追求しています。製造原価や収益性といったスタートアップとしての課題にも正面から向き合い、難病患者のQOL向上というテーマに真摯に取り組む姿勢は、医学生が起業する上での強いヒントになるはずです。

<メンターコメント>
中村さんの取り組みは、単に商品を作ったというよりも、ニーズの「取りこぼし」を拾いにいった事例です。
多くの起業初心者は「課題が見つからない」と悩みますが、実際には“あえて見ていない課題”にこそ、価値の高い市場があります。医療に関わるからこその感性が活きた好例ですね。
【参照:プロトスター株式会社「現役医学部生がなぜ起業!?〜完全食チョコレートで起業した背景に迫る〜」(https://kigyolog.com/interview.php?id=101)】
事例3.ボードゲーム200種類以上を楽しめる店(7th DICE 稲垣海里・上西凜太郎)
島根大学医学部に在籍する稲垣海里さん(30)と上西凜太郎さん(25)は、学生と地域住民が気軽に交流できる場として、ボードゲームカフェ「7th DICE」を出雲市にオープンしました。稲垣さんが個人事業主として運営を担い、複数の学生メンバーとともに学業と並行して店舗を切り盛りしています。
社会人経験を経て医学部に再入学した稲垣さんは、「学生時代にもっと多様な経験をしておけばよかった」という反省から起業を決意。きっかけとなったのは、参加した起業セミナーで書いた1枚の事業計画書でした。
実際の店舗は、医学部の教授が管理する地域拠点施設「出雲ベース」を活用し、開店準備はわずか2か月で完了。店内には200種類以上のボードゲームと1,200冊以上の漫画が揃っており、年齢や職業を問わず誰でもくつろげる空間が提供されています。
特徴的なのは、「経営を学びたい学生にチャンスを開く設計」です。店長希望の学生に運営を任せ、会計・集客・サービス設計を実地で体験させる仕組みを整備。売上の一部を成果報酬として還元することで、経済性の理解も深めています。
上西さんは、この経験を通じて、地域との接点づくりやサービス設計、接客といった多様なスキルを獲得。「医療現場以外のリアルなビジネス体験」が、今後のキャリア形成に大きく寄与していると語っています。
医学生でありながら、地域と接続したビジネスを実践する本取り組みは、医療の枠にとどまらないキャリアの可能性を体現するモデルケースといえるでしょう。

<メンバーコメント>
自分は最初「お金のことを考えるのって、なんか嫌だな」と思っていたんですが、実際に集客や原価の計算をしてみると、逆に「お金は選択肢を広げてくれる道具だ」と感じました。
稲垣さんたちのように、学生のうちにリアルな経済体験ができるのは貴重だと思います。
【参照:まいどなニュース「多忙なはずなのに…医学生が『ボードゲーム店』を“起業”した深いワケ 学生にも地域住民にも『新たな発見がある場』に」(https://maidonanews.jp/article/14776383)】

医学生が挑戦しやすい起業ジャンル

ヘルスケアテック系
医療DXやヘルスケアテックは、医学生にとって最も親和性の高い起業ジャンルのひとつです。
例えば、介護現場向けのEラーニングアプリを開発した直井香澄氏(株式会社直井ホールディングス代表)のように、現場の非効率や限界に直面した経験を起点として、テクノロジーの力で医療・福祉の仕組みを補完しようとする動きが各地で広がっています。
医学生がこの領域で挑戦しやすい背景には、以下の3つの理由があります。
理由1. 現場理解と専門性を活かせるから
医学生は、実習やボランティアなどの現場体験を通じて、制度や仕組みではカバーしきれないリアルな課題を肌で感じています。
「夜間対応の非効率さ」「患者との情報共有の難しさ」「学びの仕組みの乏しさ」など、現場に根ざした課題意識は、アイデアの出発点として非常に有効です。
さらに、彼らは制度や診療報酬の仕組み、疾患モデルなどの専門知識も並行して学んでおり、これが課題の因果構造を論理的に把握する力につながっています。
その結果、現場の“モヤモヤ”を、仮説や検証に転換しやすいのです。事業アイデアの構築からプロトタイピングまでのプロセスにおいて、現場と専門性の両輪を持つ医学生は独自の強みを発揮します。
理由2. 医師・研究者との人脈を活用できるから
医学生は、日常的に医師や教授と接する環境にあり、すでに有望なネットワークを形成しています。
この関係性は、起業時の「仮説検証」「専門的フィードバック」「実証フィールドの確保」に大きく貢献します。
たとえば、新規サービスの効果測定を病院やクリニックと連携して行う際も、学生時代から築いてきた信頼関係があれば、比較的スムーズに協力を得ることが可能です。
また、研究室の繋がりを通じて医療機器や薬学・工学分野の学生と協業することもでき、専門横断的なプロジェクトに発展するケースも少なくありません。
こうした「学内資源を実証インフラとして活用できる」点は、医学生ならではの大きな武器です。
理由3. 大学の制度や資産を活用できるから
医療・ライフサイエンス系の大学では、大学発ベンチャー制度や技術移転機関(TLO)などを通じた起業支援制度が整ってきています。
医学生でも、研究成果の特許取得、補助金申請、企業との共同開発などに関わるチャンスが生まれており、知財を活用したスケーラブルな事業を立ち上げる例も増えています。
また、近年はビジネスプランコンテストや起業部、大学横断型のインキュベーションプログラムも充実しており、「経営の経験がなくても支援を受けながら挑戦できる」環境が整いつつあります。
医学生自身が学内でピッチを行い、研究成果を外部資本と結びつける機会が増えている点も見逃せません。
このように、医学生は知識・人脈・制度の三位一体のアセットを持っており、それらを活かせる分野としてヘルスケアテックは非常に相性が良いのです。
情報発信系
医学生がInstagramやX(旧Twitter)、YouTubeなどを活用して、発信を通じた副業や起業につなげるケースが増えてきました。
情報発信に挑戦する学生は全国に数多くいますが、その中でも医学生は特に有利なポジションにあると言えます。
ここでは、医学生が情報発信に取り組みやすく、成果を出しやすい理由を3つの観点から解説します。
理由1. 医学生の知識は「信頼される情報源」になりやすいから
医学生は医学的知識を日々学んでおり、健康・栄養・睡眠といったテーマに対する発信は、「専門家に近い立場のリアルな声」として高い信頼を得やすい傾向があります。
特に、「現役医学生のリアルな情報」として、講義内容や実習での経験、最新の医療研究への触れ方などを一次情報として発信できる点が大きな差別化要素です。
受験勉強法や大学生活の工夫など、医療とは直接関係のないテーマでも「説得力のある発信者」として見られやすく、フォロワーの獲得や認知の広がりにもつながります。
理由2. 初期コストが低く、学業との両立がしやすいから
SNSやブログ、YouTubeなどを使った発信は、基本的に初期費用がほとんどかからず、スマホ1台でもスタートできます。
また、編集や投稿のスケジュールも自分で調整しやすいため、学業や実習と両立しやすい点が魅力です。
まずは“副業的”に始めて徐々に収益化し、一定の成果が出た段階で法人化やサービス展開に進むという形も可能です。
実際に、医学生が健康情報をYouTubeで発信し、広告収益や企業案件を得ているケースもあります。
発信活動がそのまま自身の学びの整理やアウトプットにもなり、“やればやるほど得をする”高コスパな挑戦と言えるでしょう。
理由3. 活動が医療キャリアの土台づくりにもつながるから
情報発信を通じて、自分の専門性や関心領域を社会に伝えることで、医師になった後のキャリアにもつながる基盤を築くことができます。
啓発活動やSNS診療、予防医学の普及など、医療界においても「情報発信力」はますます重視されており、学生時代からの取り組みが将来的に大きな価値を生み出します。
また、発信の内容次第では、企業とのコラボレーション、メディア出演、書籍出版など、キャリアの広がりを生む可能性もあります。
「自分が何に興味を持っているか」「どんな価値を届けたいか」を発信を通して掘り下げていくプロセスそのものが、キャリア形成における重要なステップになります。
医学生という“信頼されやすい若者”としてのポジションを活かしながら、社会との接点を持ち始める第一歩として、情報発信は非常に効果的な選択肢です。
起業を志す医学生が直面する壁
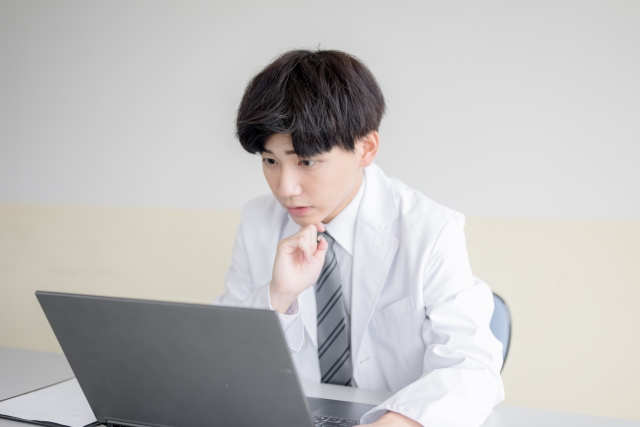
医学生としての道を歩みながら「自分で何かを立ち上げたい」と考える人が増えていますが、実際に行動に移す中で多くの壁に直面します。
医学部という特殊な環境だからこその制約や、周囲とのギャップによって、思うように進まないことも少なくありません。
ここでは、起業を目指す医学生がぶつかりやすい3つの代表的な課題について整理します。
時間や学業との両立が難しい
医学生は、日々の講義に加えて病院実習や国家試験対策に追われるため、自由に使える時間が非常に限られています。起業に必要なリサーチや仮説検証、チームとの打ち合わせなどに時間を割く余裕がなく、フルタイムでの事業推進は現実的ではないケースも少なくありません。
また、他の学生起業家と比較して「自分は出遅れているのでは」と感じて焦り、挑戦自体を諦めてしまう人もいます。特に初期段階で長期的なロードマップを描かないまま始めてしまうと、継続の見通しが立てられず、モチベーションを維持するのが難しくなることもあります。
ビジネス経験・知識が不足している
医学部ではビジネスに関する教育がほとんど行われないため、財務・マーケティング・組織運営といった起業に必要な基礎知識が不足しているケースが多く見られます。
そのため、アイデアはあっても「どうやって収益化するのか」「なぜ伸びないのか」が分からず、壁にぶつかりやすい状況に陥ります。周囲に経営の知識を持った人材が少ないため、独学に頼らざるを得ず、事業の推進に不安を感じやすい点も医学生特有の課題です。
周囲の目や期待とのギャップ
医学生が起業を志すと、家族や教員から「まずは医師としての道を固めるべきだ」と忠告されることが多く、挑戦そのものを否定される場面があります。
医師=安定というイメージが根強いため、「なぜわざわざ起業を?」と違和感を持たれたり、心配されたりすることが多く、孤独や温度差を感じやすい環境です。
また、まだ成功事例が少ない中では、自分の取り組みを説明すること自体にエネルギーを要し、精神的な消耗にもつながりかねません。周囲とのギャップは、医学生が起業に踏み出す上で見過ごせないハードルのひとつです。
起業を志す医学生が、最初に持つべき考え方

医学部に通いながら起業を目指す―その決意は簡単なものではありません。時間や学業、周囲からの期待など、多くの制約と向き合う必要があります。
それでも一歩を踏み出すためには、最初に「どんな姿勢で臨むか」が何よりも重要です。ここでは、起業を志す医学生がまず持っておくべき3つの考え方をご紹介します。
すべてを完璧にやろうとしない
医学生がフルタイムで事業に取り組むのは現実的ではありません。だからこそ、「週末起業」や「短期集中プロジェクト」など、限られた時間の中で取り組めるスタイルを選ぶことが大切です。
特に医学生の特性を活かすなら、「リサーチ型のサービス検証」「情報発信を軸にした集客テスト」「共同創業者とのパートナー分担」など、スモールスタートの設計が現実的。
すべてを自分ひとりで背負わず、優先順位を明確にしながら、一つずつ丁寧に進めていく姿勢が、挑戦を長く続けるカギになります。
ゼロから学ぶ姿勢を受け入れる
医学生は専門的な医学知識を持つ一方で、ビジネスに関しては未経験であることがほとんどです。だからこそ、「知らないことを学びにいく」姿勢が必要です。
書籍やオンライン講座での基礎学習、起業支援団体やスタートアップでのインターンなど、知識と実践を往復することで、地に足のついた事業構築に近づいていきます。
自分を「専門家」ではなく「学ぶ立場」として位置づけることで、外部からの支援も受けやすくなります。
不安や孤独は「分かち合える場所」に持ち込む
挑戦する中で、不安や孤独を感じる瞬間は誰にでもあります。一人で抱え込むと視野が狭まり、「本当にこの道でよかったのか」と自信を失ってしまうことも。
だからこそ、同じように挑戦している学生や、医療とビジネスの両方を理解する先輩・メンターとの対話が不可欠です。
実際に医師の道と起業を両立させた人の話を聞くことで、より現実的なヒントや、自分らしい道の見つけ方が見えてきます。

<メンターコメント>
医師になることが“当たり前”だと思われる中で、起業に目を向けるだけでも葛藤が生まれます。でも、外からの正解ではなく、自分の意思で決める力を育てていくことが大切です。
対話の中で、学生が自分の思考のクセや興味の軸に気づき、「この道を選んでいいんだ」と腹落ちしていく姿を何度も見てきました。
医学生が起業するときのリスクマネジメント

医学生が起業に挑戦する際には、時間や資金の制約だけでなく、「そもそも本当にニーズがあるのか?」「医療者の立場として責任をどう取るのか?」といった独自のリスクとも向き合う必要があります。
そのリスクを最小限に抑えつつ、事業の成功可能性を高めるためには、初期段階での情報収集と検証プロセスが欠かせません。
1. アイデア着想〜プロトタイプ開発の流れを押さえる
課題発見・仮説検証・ユーザーインタビューの進め方
医学生が起業アイデアを考える際、最初の起点は「現場での違和感」や「当事者の声」にあります。たとえば、患者会やボランティア活動、臨床実習などを通じて見えてくる「困りごと」に着目し、「どんなアプローチなら解決できるか?」という仮説を立てることが第一歩です。
この仮説が独りよがりにならないようにするには、ユーザーインタビューが非常に重要です。
患者本人だけでなく、医師、看護師、家族、支援者など、多面的な視点から話を聞くことで、「本当にその課題は深刻か?」「今の手段では何が足りないのか?」というリアルなニーズを掘り下げることができます。
その上で、得られたインサイトをもとに、最小限の機能(MVP)を持つプロトタイプを作成し、実際にユーザーに試してもらう。ここまでのプロセスを踏むことで、思いつきや理想論だけで進めてしまうリスクを回避し、事業の方向性を早期に確かめることができます。
医学生のネットワークや立場を活かした情報収集
医学生という立場には、想像以上に大きな“情報資源”があります。
たとえば、教授や医局の医師、実習先の現場スタッフ、患者会や学内の研究室など、他学部の学生にはアクセスしづらい信頼性の高いネットワークに自然と囲まれています。
この環境を活かせば、インタビューやヒアリングだけでなく、制度上の壁や既存サービスとの違い、倫理的な懸念といった論点も早い段階で把握できます。
「この領域はすでに研究・実装されているのでは?」「法的にリスクはないか?」「現場に導入された場合のインパクトは?」といった問いを先回りして確認できるのは、医学生ならではの強みです。
自分一人でリサーチを行うより、一次情報にアクセスしやすい環境をフルに使うことで、無駄な遠回りや失敗を防ぐリスクマネジメントが可能になります。
2. 国家試験・研究進学など将来選択肢を残す設計にする
医学生が起業に挑戦する際、あらかじめ将来の選択肢を閉ざさない設計をしておくことは非常に重要です。
医師国家試験の受験、研究分野への進学、臨床研修など、医学の本道に戻れるルートを確保しながら挑戦することで、精神的なハードルも大きく下がります。
実際、休学や留年などの制度を活用して「一定期間だけ事業にフルコミットする」ケースも増えており、事業フェーズが落ち着いた後に医師としての道へ戻る学生もいます。
「起業するなら医師にはなれない」「臨床を諦めなければならない」といった極端な二項対立にとらわれず、柔軟なキャリア設計が可能な時代です。
事前に「このタイミングで成果が出なければ学業に戻る」「このフェーズまでやり切ってから進学判断をする」といった“ステージ制”の計画を立てることで、安心感を保ちながら挑戦を継続しやすくなります。
3. やり直しが効く「仮説検証型」の進め方を意識する
医学生に限らず、起業の初期段階では「いきなり完璧なプロダクトを作る」よりも、「仮説を立てて試し、修正する」サイクルを回す方が、失敗のリスクを大きく抑えることができます。
医療分野は特に失敗が許されにくい印象があるため、医学生は慎重になりがちですが、ビジネスにおいては“間違ってもやり直せる設計”が重要です。
たとえば、「とりあえずLPを1万円で作ってみて、SNSで10人に反応を聞く」「知人にヒアリングをして仮説の精度を上げる」といった、小さなステップから始めることで、検証と学びを積み上げることができます。
こうした“仮説検証型”の進め方であれば、大きな資金や時間を投じる前に「この方向性で進めていいか」の判断ができ、結果的に自信にもつながります。
完璧さを求めず、「小さく動いて学びながら前進する」というマインドセットが、医学生起業の第一歩には欠かせません。
医学生の起業支援|無料説明会のご案内

医学生として進路に迷うのは、決して特別なことではありません。むしろ、悩むこと自体に大きな意味があります。
現代の医師キャリアは、臨床・研究・行政・教育・起業など多岐にわたり、もはや「正解」はひとつではありません。
「医師になることが当たり前」とされがちな環境のなかでも、ふと芽生える「何かをやってみたい」という気持ち。それを見過ごさず、まず一歩を踏み出してみることが重要です。
起業と聞くと身構えるかもしれませんが、実は挑戦のハードルは思っているほど高くありません。
ユースキャリア教育機構が主催する無料説明会では、将来に迷いながらも挑戦を始めた医学生たちのリアルな声に触れることができます。
同じような不安や葛藤を持つ仲間と出会い、対話を通じて自分の視野を広げることができる貴重な機会です。
「何か動いてみたい」「外の世界を知りたい」と感じているのなら、その気持ちを大切にして、ぜひ一度説明会に参加してみてください。



