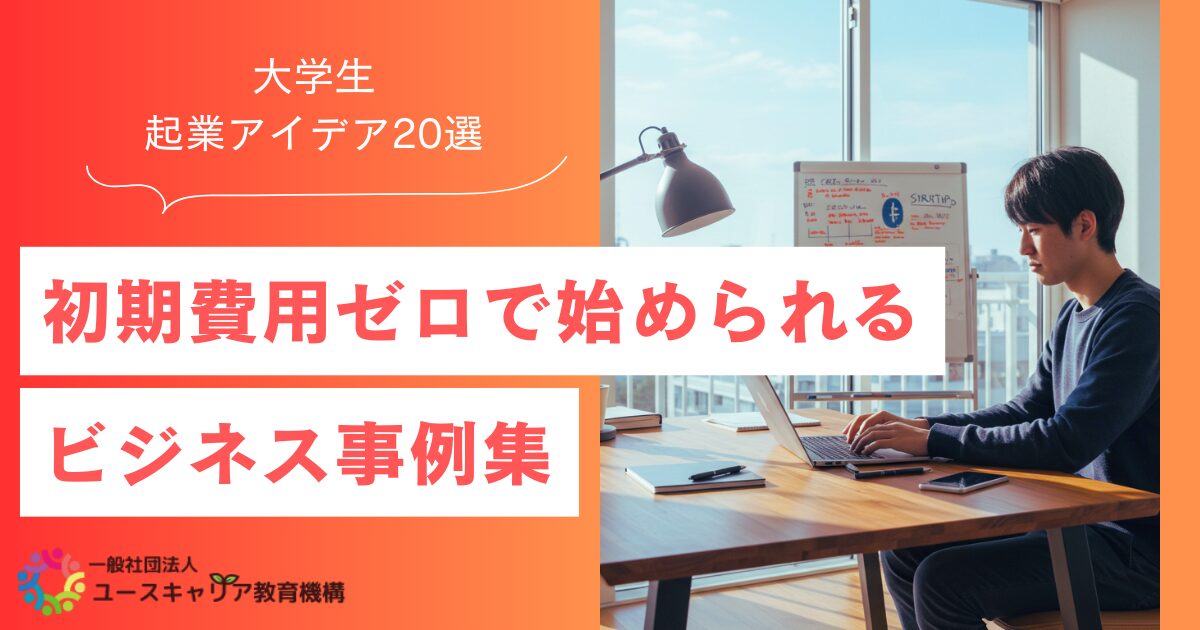大学生のうちに起業し、成果を上げている若者たちが増えています。
SNSやメディアでも話題になる彼らの姿に触れ、「自分にもできるかもしれない」「自分もやってみたい」と考える方も多いのではないでしょうか。
この記事では、実際に起業に成功した大学生の事例を紹介しながら、どのような事業で成果を出したのか、どんな背景や行動が成功に繋がったのかを解説します。
✅ 実在する大学生起業家の成功例と、その背景や行動の共通点を知ることができる
✅大学生に向いているビジネス分野と、失敗しやすいケースの傾向を知ることができる
✅ 起業前に整理しておくべき準備や、最初のステップについてヒントを得られる
✅ 現実的な起業のイメージが湧きやすくなる

大学生起業の成功例に共通する5つの特徴とは

学生起業で成果を出す人たちには、いくつかの共通点があります。ここでは成功する大学生起業家によく見られる特徴を5つ紹介します。
①資金調達先をきちんと選定している
起業初期の資金調達で「誰から・どう借りるか」を見極められる人は、失敗リスクを抑えつつ事業を安定的に育てています。
成功している大学生起業家の多くは、助成金やビジネスコンテスト、クラウドファンディングなど、返済不要または返済負担の少ない資金調達手段を上手に活用しています。親族や知人からの支援に頼る場合も、必要額と返済計画を丁寧に伝えるなど、関係性に配慮した対応をしている人が多いです。
事業の見通しが不明確な段階で高額な投資や融資を受けると、万が一の失敗時に精神的・金銭的なダメージが大きくなります。自己資金とリスクのバランスを見極め、スモールスタートを徹底できる人ほど、柔軟に改善を重ねて成長の軌道に乗りやすいのです。
②「社会経験の乏しさ」につけ入る誘いに乗らない
成功する大学生起業家は、「うまい話」には必ず裏があると理解し、慎重に判断を下しています。
「初期費用ゼロで稼げる」「誰でも簡単に月収100万円」など、一見魅力的に見える誘いは、実際には高額な商材購入や、ねずみ講的な仕組みを含んでいるケースも少なくありません。起業意欲が高く、社会経験が乏しい学生ほど、こうした話に巻き込まれやすい傾向にあります。
しかし、成功している学生は、表面的な儲け話に飛びつかず、情報を鵜呑みにせず、信頼できるメンターや専門家の助言を仰ぎながら、自分の頭で判断する力を養っています。
一時的な利益よりも、長期的に価値あるビジネスをつくる視点を持ち、リスクを避ける冷静さと倫理観を併せ持つことが、起業を成功させる鍵となります。
③失敗を恐れない
成功する大学生起業家は、「うまくいかないことは当たり前」と捉え、失敗を前提に動きながら学んでいます。
最初から完璧な事業設計を目指すのではなく、小さく始めて仮説検証を重ね、改善を繰り返す姿勢が共通しています。商品が売れない、価格が合っていない、ターゲットがずれているなどの“ズレ”に直面したとき、そこで止まるのではなく、現場の声を拾って改善策を次々と試している人が着実に事業を育てている傾向があります。
「失敗=損失」ではなく、「失敗=学びと修正の材料」と捉えるマインドがあるかどうかが分かれ目です。
逆に、ミスを避けて慎重になりすぎる人は、そもそも行動に移せず、現実の反応を得られないまま停滞しがちです。最初から完璧にやろうとせず、動きながら現実を見て調整できる柔軟さが、ビジネスの継続・拡大に繋がります。
④長期的な視点を持って事業を経営している
成功する大学生起業家は、「いま何を売るか」だけでなく、「この事業を通じて誰にどんな価値を提供し続けたいのか」を見据えています。
目先の利益やバズりだけを追い求めると、売上が一時的に伸びても、やがて方向性を見失って失速してしまうケースが少なくありません。実際、短期的な成果だけを重視して始めた事業が、数ヶ月後にはモチベーションが続かずに立ち消えてしまうという例は非常に多く見られます。
一方で、長期的に届けたい価値やビジョンがある人は、目の前の小さな判断にも一貫性が生まれ、事業の軸がぶれません。プロダクトの改善やパートナーシップの構築、ブランディングの方向性なども、「将来の目標に近づく選択かどうか」を基準に判断できるため、着実に積み上げる力がつきます。
行動量も大切ですが、「この一歩が未来のどこに繋がっているのか?」を意識することで、事業の持続性と成長力が大きく変わってきます。
⑤支援者を見つけている
成功している大学生起業家の多くは、「信頼できる支援者」とのつながりを早い段階から築いています。
起業の初期段階では、知識・経験・人脈・資金のすべてが不足している状態で動き出すため、一人であらゆる課題に対応しようとすると、迷いや不安に押しつぶされてしまいがちです。「ひとりで頑張る」ことを美徳とするのではなく、「必要なときに頼れる力」が、継続力と成功率を大きく左右します。
大学の先生、先輩起業家、地域の支援機関、起業家コミュニティなど、自分より経験値のある人に定期的に壁打ちしながら、判断の精度を上げたり、視野を広げたりしていくことが重要です。さらに、孤独やスランプに直面したときも、支援者の存在が精神的な支えとなり、踏みとどまるきっかけになるケースは非常に多く見られます。
「誰とつながっているか」は、「どれだけ動けるか」と同じくらい成功に直結する要素です。
実際の大学生起業の成功例

ここでは、ユースキャリア教育機構のプログラムに参加し、大学在学中に起業を実現したOBたちの実例を紹介します。
彼らがどんなきっかけで事業を立ち上げ、どのように工夫して取り組んできたのかなど、学生ならではの視点や行動のヒントも見えてくると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。
株式会社Rover代表取締役 後上航さん
| サービス内容 | Webコンサルティング、DX推進・AI活用支援 |
| ターゲット | 中小企業やスタートアップ企業の経営者・マーケティング担当者、起業を目指す個人や新規事業担当者 |
| 起業のタイミング | 2022年3月(当時大学4年生) |
| 大学生時の売上 | 1ヶ月あたり150万円~200万円 |
| 起業のきっかけ | スポーツ・教育・Webの領域で活動する中で、周囲の人々から感謝され、自分の役割について深く考えるようになったこと |
| 起業のために最初に取り組んだこと | 最初に行ったのは「身近な経営者3名への徹底ヒアリング」。WebやDXの知識はある程度あったものの、「自分ができること」と「実際に求められていること」のズレを解消するため、あえて報酬ゼロで相談に乗りながら課題抽出と改善提案に集中した。 |
| 成功の要因 | ・PDCAを回す頻度を週単位ではなく日単位にし、一つの施策につき毎回3つ以上の改善仮説を立てることで、分析・振り返りの精度も高くしていたこと ・単なるマーケティング施策を提供するサービスにするのではなく、クライアントやその顧客との信頼関係を重視した上でサービスを提供するようにしたこと |

<後上さんから学生起業を目指す人へのアドバイス>
起業は「正解のない問い」に自ら答えを出し続ける挑戦です。
大切なのは、「アイデア」よりも「やり切る力」と「人を巻き込む力」。失敗するのは前提として、むしろ小さく何度も失敗して、学び続けてください。
僕自身もゼロから始め、多くの試行錯誤を繰り返して今があります。結果以上に、挑戦した経験が将来の糧になるので、ぜひ思い切って飛び込んでください。応援しています。
株式会社Heywalk代表取締役 石原郁也さん
| サービス内容 | フリーコンサルタントのマッチング支援、地方創生支援 |
| ターゲット | 若者を対象としたキャリア教育や地方創生事業に軸を置いている企業・組織 |
| 起業のタイミング | 2023年2月(当時大学4年生) |
| 大学生時の売上 | 1ヶ月あたり150万円~200万円 |
| 起業のきっかけ | 幼少期から地元商店街の衰退を目の当たりにしており、企業と地方創生事業で関わりを持つなどの機会を経て「若者が地域で活躍できる仕組みを作りたい」と思うようになったこと |
| 起業のために最初に取り組んだこと | 大学時代、キャリア支援を目的とした学生団体を立ち上げ、企業と学生をつなぐイベントや就活相談サービスを運営。団体で築いた企業との信頼関係と、学生のリアルな声をもとに、質の高いマッチングを実現。ここでの実績が、Heywalk設立の土台となった |
| 成功の要因 | 学生団体時代から築いてきた人間関係を土台に、企業への提案や協力依頼を実現。信頼をベースに人を巻き込む力が、サービスの立ち上げと拡大を加速させた。 |

<石原さんから学生起業を目指す人へのアドバイス>
起業には不安も壁もたくさんあります。でも、僕が確信しているのは「夢を諦めずに走り続ける人には、必ず応援してくれる人が現れる」ということです。
最初はうまくいかなくても、自分の想いを言葉にして行動を続けていれば少しずつ共感や仲間が集まってきます。
大事なのは、完璧な準備よりも“踏み出す勇気”と“続ける覚悟”。恐れずに、自分の信じる道を進んでください!
株式会社AnnRock代表取締役 清水大河さん
| サービス内容 | DX推進支援、Webコンサルティング、マーケティング支援、経営コンサルティング |
| ターゲット | 実店舗を運営する中小企業、Webを活用した新規事業や業務改善を目指す企業 |
| 起業のタイミング | 2021年10月(当時大学3年生) |
| 大学生時の売上 | 1ヶ月あたり300万円程度 |
| 起業のきっかけ | 学習塾の運営やWebコンサルタントとして仕事をしている中で、経営難の企業の実態を目の当たりにし、支援事業を始めたいと考えたこと |
| 起業のために最初に取り組んだこと | 学習塾の運営を通じて、実店舗経営における集客・業務効率化・人材管理の課題を実感。起業時はまず、自らの経験を活かし、塾やサロンなど小規模事業者に向けたDX支援の仕組みづくりに着手した |
| 成功の要因 | ・経営者が抱える感情や実務のリアルを理解したうえで支援を行ったため、机上の空論ではない提案が高評価を得た |

<清水さんから学生起業を目指す人へのアドバイス>
起業は熱量だけでも、行動量だけでも成功しません。大事なのは、どれだけ「相手の視点」で物事を設計できるかです。学生だからこそ視野が内向きになりやすい。
だから僕はサービスを考える前に“誰がどんなタイミングでどんな悩みを抱えているか”を徹底的に想像するクセをつけていました。
しっかり考え抜いて準備するほどあとからの行動がスムーズになります。冷静に考えて始めたことこそ、長く続けられる土台になると僕は考えています。

大学生起業の成功例によく見られるビジネス

IT関連のビジネス
IT関連のビジネスで大学生が成功しやすい理由は「初期投資が少なくて済む」「時間と柔軟性がある」「同世代のニーズを知っている」という大学生ならではの強みを活かしやすい条件が揃っているからです。
特に、大学の授業や就職活動をうまく調整しながら、自分のペースで開発や運営に取り組めるのは大きなメリットです。また、大学内でのユーザー実験やSNSを使った口コミ拡散など、学生だからこその行動導線も使えます。
ただし、プログラミングやマーケティング、UI/UXなど幅広い知識が求められるため、完全な未経験者にとってはややハードルが高いジャンルです。動画教材やオンライン講座を活用すれば、半年〜1年で実践レベルに到達することができます。
独学でも学び続けられる探求心がある人、トレンドに敏感で課題発見力がある人、エンジニアやデザイナーとチームを組める人/組む意欲がある人は結果を出しやすい分野のビジネスです。
例:学生限定のイベントマッチングアプリ開発、オンライン学習メディアの運営など
イベント企画型のビジネス
イベント企画型のビジネスで大学生が起業しやすい理由は、学生という立場自体にあります。自分自身が「学生」という顧客と共通の立場を持っているため、顧客の悩みやニーズを解像度高く理解したうえでサービス設計をすることができます。
また、大学やサークル、地域団体とのつながりを活用して集客がしやすく協賛を得やすいというのも特徴です。
一方で、企画・準備・集客・当日運営とやることが多く、「継続性」と「マネタイズの仕組みづくり」には難しさがあります。また、天候や人の流れなど“運の要素”も大きいので他のビジネスに比べると売上の安定性は低いです。そのため、小さく始めて徐々にスケールすることや、別の事業を組み合わせることを検討しておくのがおすすめです。
人と話すのが好きで巻き込む力がある人、細かい段取りやスケジュール管理が得意な人、「自分だったらこんな場がほしい」という課題意識がある人に向いているビジネスです。
例: 学内キャリアイベント、地元商店街とのコラボ型フードフェス、学生向け就職説明会など
ファッション・美容関連のビジネス
ファッションや美容は、学生がターゲット層であることも多く、「自分が欲しいと思う商品やサービス=他の学生にも刺さる」という構図をつくりやすいのがこの分野の特徴です。
SNSでの発信がそのままブランディングや集客につながるため、広告費をかけずにスタートできるのも大学生に向いている理由です。加えて、コーディネート提案、メイク術紹介、古着販売など、日常と直結したテーマで始められるため、大学生にとって比較的ハードルが低いビジネスと言えるでしょう。
一方で、競合が多く「なんとなくオシャレ」だけでは差別化しづらいのも事実です。仕入れルートや価格設定、在庫管理など、表に出ない部分での工夫や実行力が成果を分けます。
また、トレンドに流されすぎるとブレやすく、軸をもったブランド設計も必要になります。
自分の“世界観”やスタイルに自信がある人、SNSでの発信や見せ方に長けている人、「好き」だけでなく「売れる」視点を持てる人が向いている分野です。
例: オリジナルアパレル、学生限定の美容サービスなど
マッチングビジネス
就活支援、地域活性、スキルシェアなど、あらゆる分野でニーズが広がっている「マッチングビジネス」。大学生起業でも人気が高く、初期費用を抑えながら社会課題の解決にもつながるビジネスモデルとして人気を集めています。
大学生がマッチングビジネスで成功しやすいのは、「若者」ならではの視点で、現場の課題にいち早く気づけるからです。たとえば「就活相談できる人がいない」「地方の店舗がSNSをうまく活用できていない」など、同世代や身近な人の悩みに敏感で、それを解決できる人とつなぐ立場を自然に担えるのが強みです。
また、プラットフォームや仲介モデルなら在庫を持たずに事業化できるため、コストを抑えたスタートが可能です。SNSや学内ネットワークを活かせば初期の集客もスムーズです。
人と人をつなげるのが得意または好きな人、信頼や安全性を丁寧に設計できる人、小さく始めてコツコツ改善できる人は特に結果を出しやすいビジネスと言えます。
例: 大学生家庭教師と高校生のマッチング、大学サークルと企業のコラボ支援など
【関連記事】
▶大学生向けのビジネスアイデアについてもっと詳しく知りたい方はこちら
大学生起業の失敗例

成功を夢見て起業に挑戦する大学生が多いのに対して、実際は失敗する人の方が圧倒的に多いのが現実です。
ここでは、実際に起業を試みたものの壁にぶつかった学生のリアルな事例を紹介します。
失敗例①友達と起業したが、組織マネジメントがうまくいかず売上を上げづらくなってしまった
友達と一緒に塾事業を作ろうとして失敗した馬上君の例:
大学1年生の6月、高校時代から仲の良かったメンバー数人で、馬上君は塾事業を立ち上げました。
オンライン上で大学生が講師となり、高校生の「学校で理解しきれなかった部分」をフォローするサービスです。
SNSや口コミで少しずつ広がり、既存顧客が新しい顧客を呼んでくれる流れができるほどスタートは順調でした。
しかし、時間が経つにつれメンバーそれぞれが大学生活で多忙になっていくと、次第に業務の責任の所在が曖昧になり対応が後回しになる事態が増加。 誰が何を担当しているのかが曖昧なまま、進捗が滞るようになりました。
さらに大きな問題となったのが報酬の取り分でした。 売上は伸びつつあるものの、「誰が一番貢献しているのか」「どの仕事が収益にどう影響しているのか」 といった視点での話し合いができず、 「仲が良いからこそ、フェアに取り決めるのが難しい」 という状況に陥ってしまいました。
リーダーであった馬上君も、これまでの関係性が壊れるのが怖くて、強く役割や責任を求められなかったと振り返ります。結果として、メンバー間で温度差が広がり、チームとしての方向性も曖昧になっていき、半年ほどで自然消滅という形になってしまいました。

仲が良かったからこそ、言えなかったことが本当に多かったです。普段の関係性を壊したくない気持ちが先に立ってしまい、業務の遅れや責任の偏りにもはっきり指摘できませんでした。
でも、ビジネスは「仲良しでやること」じゃなくて「役割と責任を果たすこと」が第一だと今になってよくわかります。メンバーの感情面に配慮しすぎて、中途半端なまま終わってしまいました。
最初にちゃんと業務が回る仕組みを整えるべきだったと思います。
失敗例②事業と学業との両立に苦しみ、どちらも中途半端になってしまった
物販や卸の分野で事業を始めた小泉君の例:
大学3年生の春、小泉君は物販・卸のビジネスをスタートしました。SNSで見つけた海外のユニークなガジェットを仕入れてECサイトで販売するというもので、商品の見せ方やコピーライティングのセンスが評価されて最初の数ヶ月は順調に売上を伸ばしていました。
しかし、壁となったのは学業との両立です。
事業に熱中するあまり、出荷・顧客対応・仕入れ業務などをすべて1人でこなしていた小泉君は、大学のテストやレポートの時期になると時間に追われるようになりました。
「今はテストがあるから」と対応が後手に回り、顧客への返信が遅れたり対応が雑になったりしたことで結果的に信頼を失ってリピーターが離れてしまう事態にもなりました。
一時的に事業を止める場面も出てきて、再開後も以前の勢いは戻らず、やがて事業全体に手をつけられなくなってフェードアウト。結局、売上も規模も伸ばしきれないまま終わる形となってしまいました。

最初は楽しかったし、売上が立ったときは本当に手応えを感じていました。
でも、大学のテストやレポートが近づくとどうしても時間が足りなくなって、事業の方が雑になってしまって… 返信が遅れたり対応が適当になったりする中でお客さんが離れていくのも感じていました。
逆に事業に集中していると、今度は単位が危うくなる。どちらかに集中するともう片方が崩れていく。結果的に、両方とも中途半端になってしまいどちらも続けられませんでした。
準備や仕組みを考えず勢いで始めた反省が大きいです。
「まず何から始めたらいい?」学生起業を成功に導くためにしておきたい準備

小さく始めることを意識する
大学生が起業を考えるとき、いきなり完璧な事業モデルや大規模なプランをつくろうとしがちですが、それは大きな落とし穴です。大切なのは、「まずは小さく試してみること」。最初から完璧を求めるのではなく、プロジェクト単位やテスト運用から始めて、実際の反応を見ながら調整することが成功の近道です。
たとえば、物販ならまずは数点だけ商品を仕入れて販売してみる、イベントなら身近な10人を集めて試験開催してみる、という規模感で十分です。小さく始めることで、リスクを抑えながら、必要なスキル・改善点・本当に求められている価値が見えてきます。
また、初期の失敗や反応を学びとして蓄積できるのも「小さく始める」ことの最大のメリットです。うまくいかなかった原因を振り返り、修正しながら次の一手を打てる状態を保つことで、事業は少しずつ形になっていきます。
事業計画を立てる
どんなに小さく始めるとしても、最低限のビジネスモデルは言語化しておくことが重要です。
「何を目指すのか(目標)」「誰に届けるのか(ターゲット)」「どうやって収益を上げるのか(収益構造)」「どれくらいお金がかかるのか(コスト)」といった基本的な要素を整理しておくだけで、行き当たりばったりの経営を避けることができます。
事業計画は、他人に見せるためではなく、自分の判断をブレさせないための道しるべです。特に大学生起業は、限られた時間と資金の中で進めることになるため、「どこに集中し、何を削るか」の判断が求められる場面も多くなります。
ざっくりでも良いので、長期でどのように運営していくのかの計画を持っておくことが、無理のない運営・改善・成長を支える大きな土台になります。
頼れる人を見つけておく
大学生の起業は、未経験だからこそ壁にぶつかる場面が多くあります。だからこそ、「迷ったときに話を聞いてくれる人」「ヒントをくれる人」をあらかじめ見つけておくことが、成功率を大きく左右します。
それは、大学の教授でも、先輩起業家でも、地域の支援機関でも構いません。SNSで発信している起業家にDMを送ってみるのも一つの手です。大切なのは、「この人に聞けば視野が広がる」「判断に自信が持てる」という存在をつくっておくことです。
以下の特徴が当てはまる人に頼るのが特におすすめです:
- 自分が目指す姿に近い経験をしている人
- 考え方や価値観が合いそうな人
- 忖度なくフィードバックしてくれそうな人
- 自分のビジネスに関係する分野に詳しい人
また、最初に相談するときはいきなり長文で現状をすべて伝えるよりも、「〇〇に悩んでいます。ヒントをもらえませんか?」と絞って聞くと相手も答えやすいです。
そして、「なぜその人を選んで相談したのか」という理由を添えると誠意が伝わりやすく、もらったアドバイスを即実行して感謝を伝えると長期的に頼れる関係を築きやすいです。
学生起業に向けた第一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか?

ユースキャリア教育機構では、起業を目指す若者に対し、経験者との交流機会や学びの場を提供しています。
「まず何から始めればいいか分からない」「身近に相談できる人がいない」
そんな方こそ、一度説明会に参加してみてください。経営、ビジネス、事業を、正しく楽しく学べる場所として運営しています。
あなたの挑戦を、お待ちしています!