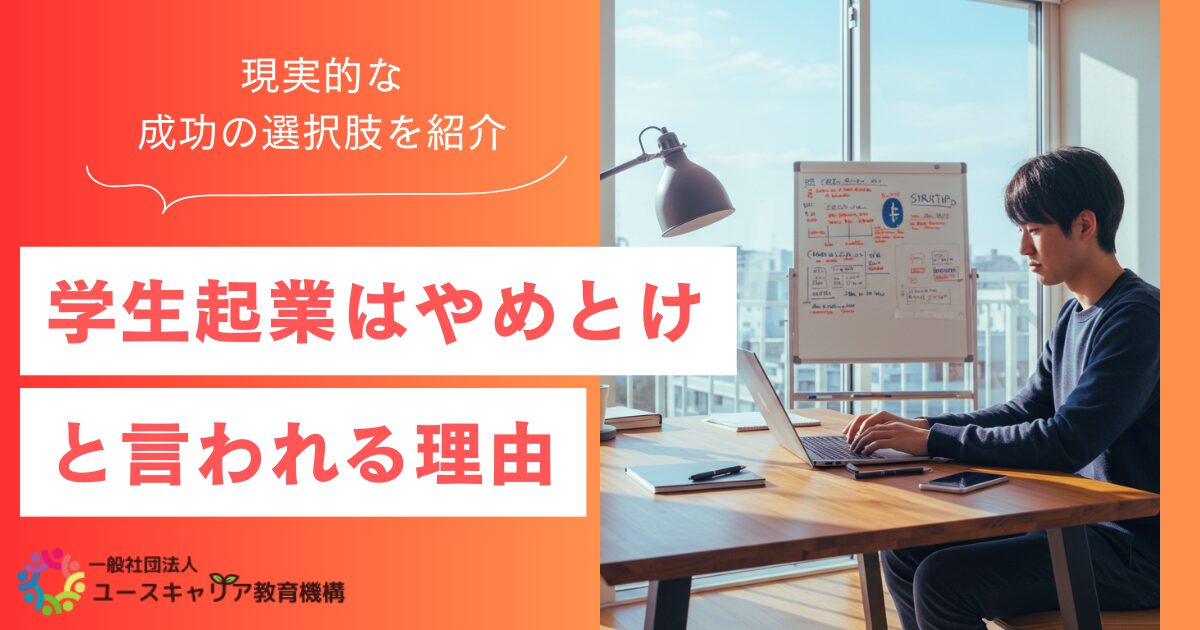「学生起業はやめとけ」—そんな言葉を耳にしたことがある人も多いと思います。
確かに、学生起業の現実は甘くないし、リスクも小さくありません。
けれど、それは「学生だから無理」なのではなく、「準備や環境の違い」が大きく影響しているのです。
この記事では、なぜ「学生起業はやめとけ」と言われるのか、どんな背景があるのかを丁寧に解説していきます。
そのうえで、リスクを抑えて起業にチャレンジする方法や、先輩たちの経験談、学生起業を現実的に考えるための視点も紹介します。
学生起業を視野に入れている方はこの記事を参考にしてぜひ今後のアクションについて考えてみてください。

「学生起業はやめとけ」と言われる4つの理由|学生が抱えるリアルな課題

①資金の不足が起きやすいため
2023年度の「新規開業実態調査」によると、開業資金の平均は約1000万円、中央値でも約550万円。これに対して学生が起業資金を用意するのはかなりハードルが高いのが現実です。
(参照:日本政策金融公庫総合研究所「2023年度新規開業実態調査」)
起業資金の調達方法は主に以下の3つに分けられます。
- 融資:金融機関からお金を借りる方法
- 出資: 事業の成長を期待する投資家などから資金を提供してもらう方法
- 自己資金:自分で稼いだお金を、必要な額まで貯金する方法
しかし、大学生がこれら3つの手段の中から資金調達の方法を選ぶには、それぞれに大きなリスクや障壁があります。
大学生が融資を受けることのリスク・障壁
融資で起業資金を調達しようとする場合、大学生だと就業経験や安定した収入がないことが多く、社会的な信用力が不足しているとみなされます。その結果「返済能力に乏しい」と判断され、そもそも融資が認められにくいのです。
加えて、多くの融資制度では返済不能時に備えて「担保(不動産など)」や「保証人(親など)」が必要です。ところが大学生の場合、自分名義の資産を持っていることは稀で、保証人の確保も難しいケースがあります。
また、金融機関は過去の売上実績や決算資料などからリスクを判断するため、実績ゼロの大学生にとっては不利になってしまいます。
大学生が出資を受けることのリスク・障壁
出資を受けるには、まず「将来性の高い事業計画」が必要です。
しかし、経験や知識が限られる大学生の起業案は、実行性や収益性への不安を持たれやすく、投資家からの信頼を得にくいのが現実です。
さらに、出資を受けたとしても、事業が期待どおりに成長しなかった場合には投資家との関係が悪化するリスクもあります。「信頼を裏切った」と受け取られることもあり、資金提供を受けた側として精神的なプレッシャーも大きくなりがちです。
また、出資は株式や経営権の一部を手放すことにもつながります。交渉や契約に関する知識が乏しい段階で、不利な条件を受け入れてしまうリスクも無視できません。
大学生が自己資金で資金調達をすることのリスク・障壁
自己資金で起業する方法は、リスクが最も低く、他者に頼らずに始められるというメリットがあります。しかし、大学生にとってはこの方法も決して簡単ではありません。
まず、アルバイトなどで得られる収入は限られており、月に数万円〜10万円前後が一般的です。そこから学費や生活費を差し引くと、貯金に回せる金額はごくわずかになります。
さらに、数百万〜数千万円という金額を自己資金だけで用意しようとすれば、数年単位の時間が必要になり、起業のタイミングを逃してしまう可能性も高まります。
よって、自己資金だけで起業資金を確保するのは時間的・金銭的な面から見て、大学生にとっては現実的に難しい手段といえます。
このように、資金面のハードルは大きく、準備不足のまま始めてしまうと資金繰りに詰まってしまいます。
②スケジュールの管理が破綻しやすいため
大学生の生活は一見自由に見えて、実は非常に多忙です。
特に学期末のテスト期間やレポート提出の時期には、学業が大きな負担となり、事業運営に支障をきたすことが珍しくありません。また、大学の授業は平日日中に組まれていることが多く、事業に割く時間をまとめて確保するのは簡単ではありません。
空き時間に事業に取り組もうとしても、移動や準備時間などの細切れ時間では、戦略的な思考や実務をこなすのは難易度が高くなります。さらに、アルバイトやサークル活動との両立を図ろうとすると、スケジュール全体が逼迫し、心身の負担も大きくなります。
どれも中途半端になってしまい、「起業も進まない」「学業成績も落ちる」「体調も崩す」といった悪循環に陥るリスクがあります。
起業には、戦略を立てて考え抜く時間、実行に集中する時間、そして成果が出るまで継続する粘り強さが求められます。そのため、時間の使い方を誤ると、事業と学業のどちらも中途半端に終わってしまう可能性が高いのです。
③経験不足により失敗しやすいため
ビジネスの現場では、想定通りに物事が進むことのほうが珍しく、常に「想定外」への対応が求められます。しかし、多くの大学生は、そうした場面での判断や立て直しの経験が乏しく、行き詰まったときにどう動くべきか分からなくなるケースが少なくありません。
実際に、学生起業でよく見られる典型的な失敗要因には以下のようなものがあります。
チーム運営が初めてで、人間関係の摩擦に悩む
学生起業では、友人や知人を巻き込んでチームを組むケースが多いですが、利害や責任が絡んだ環境での人間関係は、想像以上に繊細です。
「友達としては良好な関係」だったはずが、金銭や役割の問題が絡むと対立が生じやすくなります。それまで友人だったメンバーに対してビジネスマンとして必要な人間力や仕事の基礎力を求め始めると、元々築いていた関係性は良くも悪くも大きく変化します。それにより元々の友人関係にひびが入ってしまうことも珍しくありません。
意見の衝突や温度差に直面し、チームが空中分解してしまったという事例も非常に多いです。
役割や意思決定の曖昧さから、組織がまとまらなくなる
学生起業でよくある失敗の一つが、「意思決定の曖昧さ」によってチームがまとまらなくなることです。
たとえば、「SNSの運用方針を誰が決めるのか」「営業先のリストを誰が管理するのか」といった日常の判断や責任分担が不明確だと、次第にタスクが停滞してチームの動きがバラバラになります。
実際に「話し合いばかりで結論が出ず、結局誰も動かない」という事態や、「ある人が勝手に決めたことで他のメンバーが不満を感じ、モチベーションが下がる」などのトラブルは学生起業では頻発します。
フラットな関係性が前提の学生同士のチームだからこそ、リーダーが責任と権限を明確にし、意思決定のスピードと実行力を担保する仕組みづくりが不可欠です。
仮説検証のサイクルを知らず、改善が進まない
ビジネスでは、「やってみてダメならすぐ改善する」ことが鉄則ですが、学生の多くはこの仮説検証の重要性を理解していません。
高校までの教育で、仮説を立てたり仮説検証の振り返りの仕方を学び実践する機会があまりないため、そもそも「仮説検証をする」という発想がないことが多いのです。
1つのやり方に固執したり、うまくいかない理由を分析せずに感覚で動いたりすると、成長のチャンスを逃します。
PDCA(計画→実行→検証→改善)の基本を知り、実践していくことで同じミスを繰り返さないようにすることが大事です。
販売後のフィードバックを活かせず、チャンスを逃す
ユーザーや顧客からのフィードバックは、ビジネスを改善する貴重な材料です。
しかし経験が浅いと、ポジティブな声だけに安心してしまったり、ネガティブな意見を受け止めきれなかったりする傾向があります。
また、ネガティブな意見を受けた結果改善しようとしても、そもそも集めたフィードバックの解像度が十分でない場合やフィードバックを反映するまでの思考に間違いがあって適切なブラッシュアップに至らない場合もあります。
フィードバックを戦略に反映できないまま次のアクションを起こせずにいると、競争の中で取り残されてしまう恐れがあります。
④ビジネススキルや人脈の不足により失敗しやすいため
起業には、アイデアだけでなく実行に必要なスキルと支えてくれる人脈の両方が不可欠です。しかし、多くの大学生はこの2つを十分に持たないまま事業を始めてしまい、早期につまずいてしまうケースが少なくありません。
そもそもマーケティングや営業、契約交渉、資金繰りといった経営スキルは、大学の授業だけでは身につきにくいものです。理論や事例を学ぶことはできても、それを自分の事業に落とし込むための実践的なノウハウまでは教えてもらえないことが多く、結果として「どう売ればいいか」「どう顧客を獲得すればいいか」といった具体的なアクションに悩むことになります。
加えて、学生のうちは社会との接点が限られているため、起業時に顧客やアドバイザーといった外部の関係者とのつながりを持つことが難しく、孤立した状態でのスタートになりがちです。その結果、自分たちだけで考えた商品やサービスが、実際のニーズとずれていたり、フィードバックを得る機会を逃してしまったりすることも珍しくありません。
さらに、事業を進める中でトラブルや課題に直面しても、相談できる相手がいないというのも学生起業における大きなリスクの一つです。経験や人脈の乏しさから、問題解決に時間がかかり、精神的にも追い込まれてしまい、最終的には事業そのものを諦めてしまうケースもあります。
このように、ビジネススキルと人脈の不足は、単なる「準備不足」にとどまらず、事業の根幹を揺るがす大きな障壁となります。だからこそ、まずは小さく始めて失敗できる範囲で経験を積み、外部との接点を少しずつ増やしていくことが、学生にとっては堅実なスタートとなるのです。
学生起業が「難しい」と言われる理由
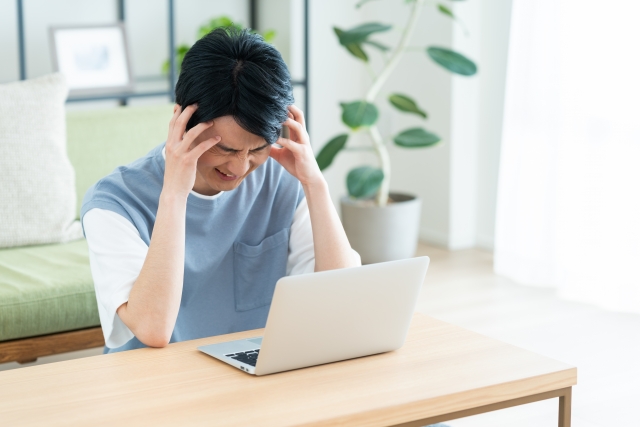
学生起業の現状
学生による起業は、近年メディアなどで注目を集めるようになってきましたが、実際に取り組んでいる学生はまだごくわずかに限られています。
2021年時点では実際に起業している学生の割合はわずか1.5%。つまり、100人のうち起業しているのは1人いるかいないかという水準にとどまっています。
(参考:GUESSS 日本事務局「GUESSS 2021 Japanese National Report」)
一方で、起業に対する関心は確実に高まりつつあります。2023年に行われた調査では、起業に「興味がある」と回答した高校生は14%、大学生では12.4%という結果が出ています。
(参考:株式会社ペンマーク「【高校生13万人調査】高校生の起業志望率は約14%、大学生(約12.4%)を上回る。」)
つまり、「起業してみたい」と思っている学生は約10人に1人いるのに対し、実際に行動に移しているのはごく一部に過ぎないという、大きなギャップがあります。このギャップの背景には、起業に対する不安や情報不足、資金やスキル面でのハードルが存在しているのです。
しかし一部の学生は、小さなステップからビジネスを始めています。実際に学生が最初に挑戦することの多い起業分野としては、以下のような“始めやすい領域”が挙げられます。
- SNS運用代行:企業や個人のSNSアカウントを運用し、投稿作成や分析を代行するビジネス。デザインやマーケティングに興味のある学生に人気。
- 物販(フリマアプリなど):メルカリやBASEなどを活用し、不要品や仕入れ商品を販売。低コストで始められ、商売の基本を学ぶ入門編として活用されている。
- アフィリエイトやブログ運営:自分のメディアを立ち上げ、広告収入を得るモデル。文章力やSEOの知識が求められるため、スキルアップを兼ねて始める人もいる。
これらのビジネスは、初期費用が少なく、自分一人で始められるという利点がある一方で、競争が非常に激しく、収益化までに多くの試行錯誤が必要です。SNS運用代行は案件獲得に営業力が求められますし、アフィリエイトやブログも継続的な発信力とマーケティング理解が不可欠です。
つまり、「始めることはできるが、稼ぐのは簡単ではない」のがこれらの分野の共通点です。
このように、学生の起業にはチャンスがある一方で、成功までの道のりには多くの現実的な課題が伴います。だからこそ、最初の一歩を踏み出す際には、自分に合った小さなスタートラインを見極めることが重要です。
学生起業が難しいと言われる理由
近年、「学生でも起業できる時代」と言われるようになってきました。しかし現実には、学生が起業で成果を出すのは容易ではありません。その背景には、情報や環境の不足、そして競争の激化という3つの大きな壁が存在しています。
同じ志を持つ仲間に出会いにくい環境
学生起業の初期段階で直面しやすいのが、「孤独」との戦いです。
学校やバイト先には起業に興味を持つ人が少なく、共通言語が通じる仲間が見つかりにくいのが現状です。
ビジネスの話をしても「変わったやつ」「意識高い系」と見なされて距離を置かれることもあり、深い議論や壁打ちができる相手を見つけるのに苦労します。
このような孤立した環境では、アイデアが育ちにくく、モチベーションも維持しづらくなります。成長を加速させるためには、同じ志を持つ学生が集まるコミュニティや勉強会に積極的に参加し、自分から環境を変える意識が必要です。

<ユースキャリアメンバーのコメント>
起業に関心はあったけど、同年代で同じ温度感の人がいなくて、誰にも話せず止まっていた時期がありました。仲のいい友達には話せても、具体的な相談や壁打ちまでは難しくて。
今振り返ると、環境を変えた瞬間に一気に動けるようになった気がします。仲間がいることで、行動って自然と続けられるんだなと実感しました。
頼れる先輩やメンターの不在
起業は「やってみて初めて分かること」の連続です。
しかし学生の多くは実務経験も少なく、壁にぶつかったときに頼れる人がいないとその都度行き詰まりやすくなります。
資金調達、契約書の扱い、顧客トラブル、マーケティングなど、多岐にわたる課題に直面するたびに自己流で対応し続けるのは、大きな時間と労力の消耗を招きます。
特に重要なのは、行き詰まったときに「正しい問い」を立て、適切な打ち手を教えてくれる存在です。経験豊富な先輩起業家や社会人メンターとつながることで、失敗のリスクを下げながら、実践を通じて成長することができます。

<ユースキャリアメンバーのコメント>
自分ひとりで調べていた頃は、わからないことが出るたびに手が止まって、モヤモヤして終わることが多かったです。
でも一度だけ、知り合いの社会人に「そのやり方は非効率だよ」と指摘されたとき、視界がパッと開けたような感覚がありました。
経験者の一言って、想像以上に重みがあるんだと気づいた出来事です。
“始めやすい”とされる業種の競争激化
「学生でも始めやすい」と言われるビジネス領域には、多くの落とし穴があります。
例えば、SNS運用代行やフリマアプリによる物販、ブログやアフィリエイトなどは、初期コストが低く参入障壁が小さいため、毎年多くの人がチャレンジしています。
しかしその分競争は非常に激しく、差別化なしに始めた場合は、価格競争や情報の埋もれによってすぐに成果が頭打ちになります。
成果を出すには、商品設計、集客戦略、ブランディングなど、一定以上のビジネススキルが必要になります。
「始めやすさ=簡単に稼げる」ではないことを理解し、ニッチ戦略や顧客理解の深さを武器に地道に実績を積み上げていく姿勢が求められます。
このように、学生起業が難しいと言われるのは、「挑戦できる仕組みは増えているが、乗り越えるべき壁も多い」という構造があるからです。情報不足、支援不足、競争激化といった外的なハードルに対して、正しい知識と、行動を支えてくれる環境を持っているかどうかが、成功の鍵になります。
だからこそ、起業を目指す学生には「一人だけで頑張らないこと」「信頼できる人とつながること」「小さく検証して改善していくこと」が重要です。勢いや思いつきだけで突き進まず、学びと支援のある環境で堅実に挑戦する姿勢が求められています。

リアルな失敗から学ぶ|学生起業家の失敗事例と末路

失敗例①友達と起業したが、組織マネジメントがうまくいかず売上を上げづらくなってしまった
友達と一緒に塾事業を作ろうとして失敗した馬上君の例:
大学1年生の6月、高校時代から仲の良かったメンバー数人で、馬上君は塾事業を立ち上げました。
オンライン上で大学生が講師となり、高校生の「学校で理解しきれなかった部分」をフォローするサービスです。
SNSや口コミで少しずつ広がり、既存顧客が新しい顧客を呼んでくれる流れができるほどスタートは順調でした。
しかし、時間が経つにつれメンバーそれぞれが大学生活で多忙になっていくと、次第に業務の責任の所在が曖昧になり対応が後回しになる事態が増加。 誰が何を担当しているのかが曖昧なまま、進捗が滞るようになりました。
さらに大きな問題となったのが報酬の取り分でした。 売上は伸びつつあるものの、「誰が一番貢献しているのか」「どの仕事が収益にどう影響しているのか」 といった視点での話し合いができず、 「仲が良いからこそ、フェアに取り決めるのが難しい」 という状況に陥ってしまいました。
リーダーであった馬上君も、これまでの関係性が壊れるのが怖くて、強く役割や責任を求められなかったと振り返ります。結果として、メンバー間で温度差が広がり、チームとしての方向性も曖昧になっていき、半年ほどで自然消滅という形になってしまいました。

仲が良かったからこそ、言えなかったことが本当に多かったです。普段の関係性を壊したくない気持ちが先に立ってしまい、業務の遅れや責任の偏りにもはっきり指摘できませんでした。
でも、ビジネスは「仲良しでやること」ではなくて「役割と責任を果たすこと」が第一だと今になってよくわかります。メンバーの感情面に配慮しすぎて、中途半端なまま終わってしまいました。
最初にちゃんと業務が回る仕組みを整えるべきでした。
失敗例②事業と学業との両立に苦しみ、どちらも中途半端になってしまった
物販や卸の分野で事業を始めた小泉君の例:
大学3年生の春、小泉君は物販・卸のビジネスをスタートしました。SNSで見つけた海外のユニークなガジェットを仕入れてECサイトで販売するというもので、商品の見せ方やコピーライティングのセンスが評価されて最初の数ヶ月は順調に売上を伸ばしていました。
しかし、壁となったのは学業との両立です。
事業に熱中するあまり、出荷・顧客対応・仕入れ業務などをすべて1人でこなしていた小泉君は、大学のテストやレポートの時期になると時間に追われるようになりました。「今はテストがあるから」と対応が後手に回り、顧客への返信が遅れたり対応が雑になったりしたことで結果的に信頼を失ってリピーターが離れてしまう事態にもなりました。
一時的に事業を止める場面も出てきて、再開後も以前の勢いは戻らず、やがて事業全体に手をつけられなくなってフェードアウト。結局、売上も規模も伸ばしきれないまま終わる形となってしまいました。

最初は楽しかったし、売上が立ったときは本当に手応えを感じていました。
でも、大学のテストやレポートが近づくとどうしても時間が足りなくなって、事業の方が雑になってしまって… 返信が遅れたり対応が適当になったりする中でお客さんが離れていくのも感じていました。
逆に事業に集中していると、今度は単位が危うくなる。どちらかに集中するともう片方が崩れていく。結果的に、両方とも中途半端になってしまいどちらも続けられませんでした。
準備や仕組みを考えず勢いで始めた反省が大きいです。
失敗のリスク以上の価値がある!学生起業がもたらす3つのメリット

学生起業にはリスクもありますが、それを上回る大きな価値を得られる可能性があります。ここでは、実際に挑戦することで得られる主なメリット3つをご紹介します。
①普通の学生生活では得られない経験を得ることができる
学生起業の最大の魅力のひとつは、一般的な学生生活では経験できない「実践の場」を自ら作り出せることにあります。
講義やインターン、アルバイトでは得られないリアルな経営経験を通じて、圧倒的に視野が広がり、思考力や行動力が磨かれます。
たとえば、実際に自分のアイデアから商品やサービスをつくって売るとなると、単にマーケティングの理論を学ぶのとはまったく異なり「誰に、どう伝えたら、買ってもらえるのか?」という問いに自分で向き合う必要があります。普段は「買う側」として当たり前に利用していたモノやサービスを、「売る側」の視点で見ることで消費者心理や市場の構造が一気に立体的に理解できるようになります。
また、起業では営業、集客、顧客対応、在庫管理、売上の記録・分析まで、すべてを自分で担うことになります。責任の重さはアルバイトやインターンとは比べものにならず、「お金をもらう=相手に価値を提供する」という前提のもと、強い当事者意識が芽生えます。実際、1,000円を「自分の力で稼ぐ」経験をした学生は、同じ1,000円の価値の重みをまったく違った感覚で受け取るようになります。
さらに、自分の事業を立ち上げる中で、「どうすればお金が回るのか」「どこにコストがかかり、どう利益が生まれるのか」といった資本主義の基本構造が、体感的に理解できるようになります。これは、教科書ではなかなか掴めない、経済の原理に対する“肌感覚”を養う貴重なプロセスです。
このように、学生のうちに起業に挑戦することは、単なるスキル習得にとどまらず、思考のレベルや社会の見え方そのものを変える体験につながります。
②組織運営のスキルを身に着けることができる
学生起業に取り組む過程では、ひとりで完結できる範囲を超えて、チームを組んで仲間と共に目標を追う機会が自然と生まれてきます。
この「誰かと一緒に成果を出す」という経験は、学業や部活動、アルバイトとはまったく異なる質の学びをもたらします。たとえば、自分のビジョンに共感してくれた仲間を集めて、役割分担をしながら一つのプロジェクトを進めることは簡単なようでいて、意見の食い違い・温度差・スケジュールのズレなど、多くの壁に直面します。
それでも対話を重ね、信頼関係を築き、共に壁を乗り越えた経験はまさに「リーダーシップの原点」となります。実際にチームで何かを成し遂げたとき、メンバーからの感謝の言葉や周囲からの評価を通じて、自分の存在が誰かにとって価値あるものだったと実感することができます。
また、事業を拡大していく過程では、「この人と一緒に働きたい」と思われ続ける存在であることが不可欠です。指示を出すだけでなく、信頼を得て、巻き込んでいく力や人を育て、任せ、チームとして成果を最大化する力はいわゆる“人間力”とも呼ばれる部分です。学生のうちに起業というリアルな場で鍛えることで、将来的にどんな職業に就くにせよ大きなアドバンテージとなります。
③自分自身を成長させることができる
学生起業は、単なるビジネスの経験にとどまらず、自分自身を大きく成長させるプロセスでもあります。
起業をするということは、すべての意思決定に自分自身で責任を持つということです。「やる」「やらない」「どう進めるか」「誰と組むか」といった判断を、自分の頭で考えて下していく中で、主体性や判断力が磨かれていきます。
また、商品やサービスを提供するうえでは、顧客や協力パートナーなど、さまざまな人と直接やりとりする機会が生まれます。その過程で、相手の立場に立って考える力や、丁寧に信頼を築く力、誠実に謝る力など、人としての総合的な魅力が磨かれていくのも大きな特徴です。
「うまくいくかどうか」以上に、「誰にどう向き合うか」が試される場面が多く、どんなキャリアでも通用する“社会人力”を養うことができます。
さらに、どんなに小さなことでも「自分の力で生み出した成果」が積み上がっていくとそれが大きな自信につながります。初めて売れた商品、初めて喜ばれた瞬間、初めての利益が生まれた瞬間など、小さな成功体験は、次の挑戦へのエネルギーとなり、「自分ならできる」という感覚を着実に育ててくれます。
起業を通じて得られる成長は、教室では教わることができない、人生を前に進める力そのものです。自分自身と真剣に向き合う中で、可能性を広げていくきっかけになる、それが学生起業の大きな価値だといえるでしょう。
学生起業を成功させるためにやるべきこと

学生起業を軌道に乗せるには、最初の一歩をどう踏み出すかがとても重要です。ここでは、成功に近づくために意識したい2つのポイントを紹介します。
① 資金ではなく「資産」を集める
学生起業を目指すとき、多くの人が真っ先に考えるのが「お金の問題」です。「いくら必要か」「どうやって調達するか」といった資金面の不安から、なかなか踏み出せないという声もよく聞きます。
しかし、起業を軌道に乗せるうえで本当に重要なのは、最初に資金を集めることではなく、「資産を蓄積していくこと」です。
ここで言う資産とは、「金銭的な財産」だけでなく、将来的に価値を生み出す可能性のあるリソース全般を指します。具体的には、以下の6つに分類することができます。
- 有形資産:人・モノ・金
- 無形資産:時間・スキル・情報
この中でも、最も重要なのは「人」という資産です。どれだけ優れたビジネスアイデアやスキルがあっても、それを実行し、継続し、成長させていくには、協力してくれる仲間・支えてくれる先輩・メンターの存在が不可欠です。
実際、必要な資金やスキル、顧客とのつながりなど、ほとんどのリソースは「人を通じて得られる」ものです。例えば、信頼できる友人とチームを組めば、自分一人では気づけなかった課題に気づけたり、行動が加速したりします。起業家の先輩に相談できる環境があれば、リスクの高い意思決定を避けることができるかもしれません。応援してくれるフォロワーやコミュニティがあれば、最初の顧客や出資者が生まれることだってあります。
さらに、「人」という資産があると、行動の継続力やモチベーションの維持にも大きな効果を発揮します。孤独な状態では迷いや不安が増幅されてしまいますが、仲間と一緒に動くことで失敗を乗り越える力や成功体験の喜びが何倍にも広がります。スキルや経験の吸収スピードも、周囲の存在によって格段に上がります。
つまり、学生起業の最初の一歩で意識すべきことは、「お金がないからできない」と考えることではなく、「自分にはどんな資産がすでにあるのか」「どんな資産をこれから集めるべきか」を見極めることなのです。その中でも、特に「人」という資産を大切にし、信頼関係を築いていくことが、成功への土台を作ることにつながります。
② まず行動しよう!
必要な資産が何か見えてきたら、次にやるべきは「行動」です。
動かない限り、自分に足りないものも、必要な支援も見えてきません。たとえ小さな一歩でも、行動することで経験が生まれ、人とのつながりが生まれます。
SNSで発信してみる、身近な人に相談してみる、仮のプロジェクトを立ち上げてみる。そういった些細な行動が、次の展開を呼び込みます。成功している起業家に共通するのは、慎重に考え込むよりも“動きながら考える”スタイルを取っているということです。
完璧な準備をするのに時間をかけるよりも実践をしながら考える方が、得られる学びがはるかに多く現実的な成果につながります。をかけるよりも実践をしながら考える方が、得られる学びがはるかに多く現実的な成果につながります。

<ユースキャリアメンバーのコメント>
自分も最初は一歩目を踏み出すまでは「もっと準備してから…」と先延ばしにしていました。
でも小さくてもやってみたら意外と反応が返ってきて、自分の中の仮説が間違っていたことにもすぐに気づけました。
頭で考えているだけではわからないことが多すぎる。
やっぱり、動きながら考える方が学びは早いと感じます。
具体的な行動が思いつかない人へ、ユースキャリア教育機構へのご案内

「やってみたいけど、何から始めればいいか分からない」
「起業に興味はあるけど、1人で動くのは不安」
そんな人こそ、一歩目を“環境”に頼ってみてください。
ユースキャリア教育機構では、すでに800人以上の若者が、起業というテーマに向き合い、試行錯誤を重ねています。
同じ志を持つ仲間と出会い、先輩から実践的な学びを得て、想像もしなかった未来を描き始めたメンバーがたくさんいます。
興味を持った方はぜひこちらから無料説明会に申し込んでみてください!