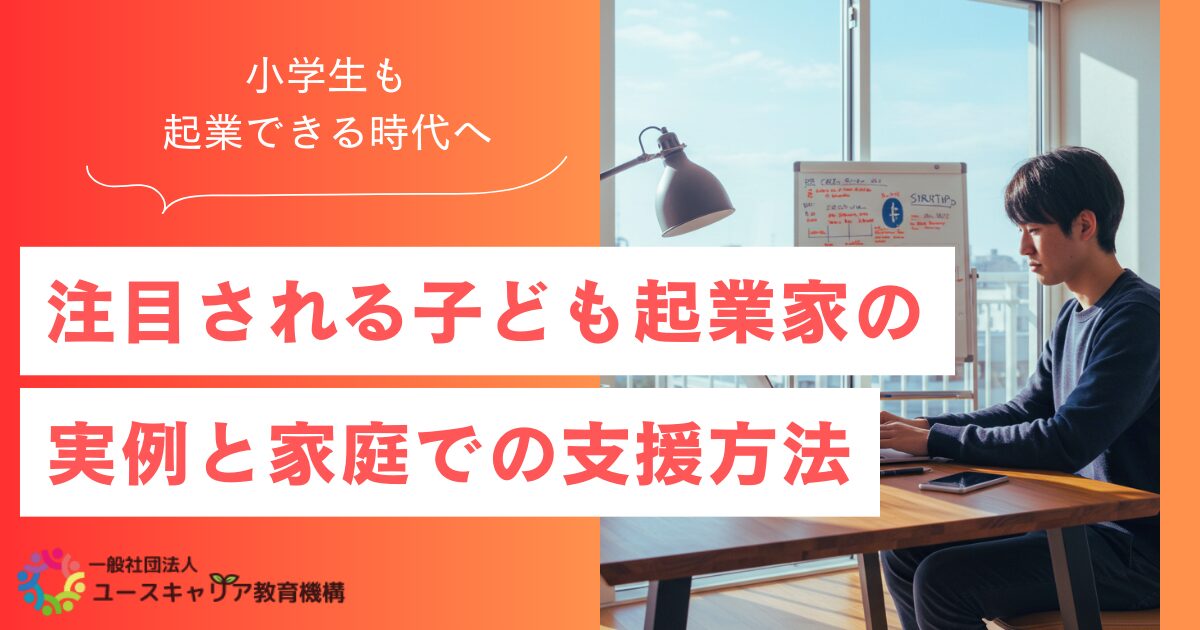小学生のうちから「起業」に挑戦する子どもたちが、いま注目を集めています。全国各地で起業体験プログラムやワークショップが広がる中、実際に商品を開発・販売し、事業化している小学生も増えてきています。
この記事では、実際の小学生起業家の事例や、起業によって身につく力、家庭での具体的なサポート方法を幅広くご紹介します。
子どもの将来を見据え、「起業」がどのように役立つかをわかりやすくお伝えします。
✅ 小学生が実際に起業している事例と、その背景・取り組み内容がわかる
✅起業に必要なステップや家庭でできるサポート方法について知ることができる
✅ 子ども向けのビジネスアイデアを具体例付きで知ることができる
✅起業を学ぶ手段と、それぞれのメリット・デメリットが分かる

いま注目される“小学生起業家”の実態

小学生の起業が注目されている背景
ここ数年、「子ども起業塾」や「ジュニアビジネススクール」など、子ども向けの起業教育プログラムが各地で開催されています。
対象となるのは主に小学4〜6年生。子どもたちは、事業計画の立て方から資金調達、商品開発、販売までを実践形式で学びます。多くのプログラムでは、大人はアドバイザーとして関わるだけで、最終的な意思決定は子ども自身が担います。
こうしたスタイルが広まっている背景には、「正解のない時代」を生き抜くための力を育てたいという、社会全体の教育的ニーズがあります。
起業体験は、創造力・問題解決力・コミュニケーション力といった“非認知能力”を育てる有効な手段としても注目されています。まさにこれからの時代に求められる「生きる力」を育む、新しい学びの形といえるでしょう。
保護者の間でも関心が高まっている理由
近年、「アントレプレナーシップ教育」や「起業家精神」という言葉を耳にする機会が増え、保護者の間でも子どもの起業体験への関心が高まりつつあります。その背景には、これからの時代を生きる子どもたちに対して、知識やスキルだけでなく「より本質的な力」、すなわち「自ら考え、自ら動く力」を育んでほしいという願いがあります。
保護者の多くは、ただ指示を待つのではなく、主体性をもって行動できる子に育ってほしいと願っています。さらに、自分の「好きなこと」や「得意なこと」を活かし、それを将来の仕事や生き方につなげてほしいと思っている保護者も多いです。加えて、将来に対する不確実性が高まる現代においては、「どんな環境にあっても自分で選び、自分で決めていく力」―いわば意思決定力の重要性も高まってきています。
こうした想いから、起業体験は単なるビジネス教育の枠を超えて、子ども自身の可能性を広げるための学びの場として注目されています。実際に自分のアイデアを形にして、誰かに届けてみるという経験を通して、子どもは「自分にもできるんだ」という実感を得ることができ、それが自信や前向きな行動へとつながっていきます。
さらに、「やりたいことが分からない」「自分には特別なものがない」と感じている子にとっても、起業という手段はひとつの突破口となり得ます。自分の手で何かを生み出し、実際に人に喜ばれる体験を通じて、自己肯定感が育ち、見えていなかった自分の可能性に気づくことも少なくありません。
起業体験は、特別な資質を持った一部の子どもだけのものではありません。どんな子どもにとっても、自分のアイデアを試し、社会とつながり、自分自身を見つめ直す貴重な機会となり得るのです。

<ユースキャリアメンターコメント>
子どもの“やってみたい”という感情は、とても繊細で不確かです。
でも、その曖昧さに付き合い、問いかけを重ねていくことで、自分なりの興味や願いが少しずつ形になっていきます。
大人が急いで正解を与えるのではなく、じっくりと耳を傾けることが、子どもの自己肯定感と挑戦のエネルギーを育てる第一歩になります。
小学生起業家たちの実例と彼らの共通点

ここでは、実際に小学生のうちから起業というチャレンジを始めた子どもたちの事例を紹介します。
どの小学生起業家も、「自分の得意」や「好きなこと」を軸に行動を起こし、社会とつながる経験を積んでいます。
それぞれの取り組みや背景を知ることで、子どもたちがどんなきっかけで起業に踏み出したのかを具体的にイメージできるはずです。
浜口祐衣さん(こどもLabo)
| 地域 | 大阪府 |
| 起業したタイミング(当時の学年) | 小学4年生 |
| ビジネスの内容 | 小学生が自分で考えた商品やサービスを販売・発表できるイベントやワークショップを企画・運営。 子どもたちが自分のアイデアを形にし、社会とつながる機会を提供することを目的としている。 |
| どのように行動を始めたか | もともと「自分でお金を稼いでみたい」「自分のアイデアを形にしたい」という思いがあり、地域のイベントやワークショップに参加したことがきっかけ。 その経験を活かし、自分でもイベントを主催することを決意。 SNSや学校、地域のネットワークを活用して参加者を集め、企画・運営をスタート。 |
| 結果・成果 | ・「こどもLabo」のイベントには多くの小学生が参加し、新聞やテレビなどのメディアにも取り上げられた ・子どもたちが自分のアイデアを発表し、販売することで「自信がついた」「新しい友達ができた」などの声が多数寄せられている ・浜口さん自身も起業家イベントや講演会に招かれるなど、活動の幅を広げている |
| 成長したポイント | ・リーダーシップ:イベント運営を通じて、仲間をまとめたり、責任を持って行動する力が身についた ・コミュニケーション力:参加者や大人、メディアとのやりとりを通じて、伝える力や聞く力が向上した ・課題解決力:イベント運営で発生するトラブルや課題に対し、自分で考えて解決策を見つける力が養われた |
| 保護者の関わり方 | 「見守る」スタンスを大切にしつつ、必要な場面ではサポートやアドバイス(イベントの会場手配や安全面のサポート、金銭管理のアドバイス)を行っている |
参考:テレビ朝日「『小学生起業家』に密着 12歳で『塾』を経営」
レウォンさん(株式会社polarewon)
| 地域 | 主に東京都を拠点に活動しているが、全国的に事業を展開 |
| 起業したタイミング(当時の学年) | 小学6年生 |
| ビジネスの内容 | ・元素の仕組みを学ぶ「元素カルタ」や、楽しく漢字を学ぶ「漢字ミッション」など、学びを面白くする教材・サービスの開発 ・「UWABAKIプロジェクト」(白くて汚れが落ちにくいうわばきを心地良い履き物に革新するプロジェクト)など、社会課題を解決する新しいプロダクトの開発 ・教育イベントや企業研修、理想の学び場「之楽館(しらくかん)」の運営 |
| どのように行動を始めたか | ・自分自身の「モヤモヤ」や「違和感」からアイデアを生み出し、まず「元素カルタ」や「漢字ミッション」を自作。クラウドファンディングで資金を集め、実際に商品化(元素カルタは629人から約380万円を調達) ・「UWABAKIプロジェクト」を実現するため、周囲の大人のアドバイスを受けて法人化を決意 |
| 結果・成果 | ・元素カルタや漢字ミッションは多くのメディアで注目され、教育現場や企業研修にも導入 ・クラウドファンディングで目標の5倍以上の資金調達に成功 ・多数の賞を受賞し、講演やイベント登壇も多数 |
| 成長したポイント | ・「言ってみる」「行ってみる」「やってみる」の“いいや”の法則で、行動力と挑戦力を身につけた ・失敗や困難をポジティブに捉え、粘り強く取り組む姿勢 ・自分の違和感や疑問を社会課題の解決につなげる発想力 |
| 保護者の関わり方 | レウォンさんの主体性を尊重し、「見守る」「サポートする」スタンスを大切にしている。 必要なときにアドバイスや情報提供をしつつ、本人の意思決定や挑戦を最大限応援する姿勢を徹底している。 |
参考:東洋経済「ホリエモンも絶賛、小学生で起業の13歳社長が語る『学校の違和感』の中身」
参考:システムブレーン「【講師特別インタビュー】レウォン (李 禮元)さん 後編投資家が惚れた若き才能 中学生起業家の出会いと挑戦の物語」
井上美奈さん(TSUNAGU OÜ)
| 地域 | 東京在住だが、エストニアに法人を設立 |
| 起業したタイミング(当時の学年) | 小学6年生 |
| ビジネスの内容 | ・「つなぐ」をテーマに、年齢や場所を問わず誰でも未来に貢献できるサービスの開発(現在も開発中) ・国内外をつなぐイベントやワークショップの開催 ・テクノロジーフェスティバルやオンラインイベントの企画・運営 ・自治体や学校でのデジタル化支援や授業の実施 |
| どのように行動を始めたか | ・10歳でStartup Weekendに参加し起業に興味を持つ ・11歳でクラウドファンディングに挑戦し、エストニアへ渡航 ・現地で起業家や投資家と交流し、帰国後エストニアで法人設立 |
| 結果・成果 | ・国内外でワークショップやイベントを多数開催 ・EdTech Asiaでピッチ登壇、自治体や学校と連携したプロジェクトも実施 ・年齢や地域を超えた多様な人々の交流と学びの場を創出 |
| 成長したポイント | ・異文化や多世代との交流を通じたコミュニケーション力 ・行動力とチャレンジ精神 ・社会課題を見つけ、実践的に解決へつなげる力 |
| 保護者の関わり方 | ・興味のあることに挑戦させる環境を整え、本人の意思を尊重 ・習い事や活動の選択も自主性を重視し、必要なサポートのみ行う |
参考:Gaiax「小学生でエストニア起業、起業家・井上美奈が13歳になった今ガイアックスとコラボする理由」
参考:常翔学園中学校・高等学校「中学生起業家 井上美奈さん講演会」
彼らに共通する2つのポイント
① 社会課題への関心と「自分にできること」を形にする行動力
まず共通して見られるのは、「社会課題への関心」と、それを自分なりの方法で形にしていく行動力です。
3人の小学生起業家はいずれも、日常生活の中で感じた違和感や身近な人の困りごとを出発点に、「自分に何かできることはないか」と考え、実際に行動を起こしています。
たとえば 浜口祐衣さんは、勉強が苦手な子の力になりたいという純粋な想いから、そのニーズに応える学習支援のしくみを立ち上げています。
レウォンさんは、学校の授業がつまらないと感じたことをきっかけに、子どもたちが楽しんで学べるような教材を自分で考案し、商品として形にしました。
また井上美奈さんは、「誰かの役に立ちたい」という思いを胸に、なんと国を越えて海外での社会貢献活動に挑戦しています。
彼らに共通するのは、単なる好奇心や興味にとどまらず、自分の“好き”や“得意”を社会とつなげる視点を持ち、それを具体的なアクションに落とし込んでいる点です。
② 家族の理解とサポート
もう一つの共通点は、家族の深い理解と実践的なサポートの存在です。どの事例においても、家族は単なる応援者ではなく時に伴走者として子どもたちの挑戦をしっかりと支えていました。
浜口さんは、ご両親ともに起業経験を持っており、ビジネスの進め方に関するアドバイスだけでなく、開業届の提出など、実際の起業手続きにも一緒に取り組みました。
レウォンさんの場合、クラウドファンディングを立ち上げる際に保護者が主体的に支援し、資金提供者とのやり取りやプロジェクト運営の場面でも実務的な支えとなっていました。
さらに井上さんのケースでは、家族全体が海外移住という大きな決断を受け入れ、現地で活動を継続するための生活基盤づくりを積極的に行っています。
このように、子どもの想いや行動を尊重しながら、現実的な面で支えてくれる家族の存在が常にあって彼らの起業が成り立っています。
これらの成功例から、起業は「才能がある子だからできたこと」ではなく、「環境と関わり方次第で、誰にでもできる可能性があること」であると言えます。

<ユースキャリアメンターコメント>
“行動できた子”に注目が集まりがちですが、実は行動の前段階にある“もやもや”や“違和感”を大切にすることこそが、子どもの挑戦を引き出す鍵になります。大人がその芽に気づき、『面白いね』『やってみたら?』と自然に背中を押せる環境があれば、どんな子にも起業という選択肢は開かれていきます。
小学生が起業を学ぶための最初のステップ

ビジネスアイデアを決める
小学生が起業を考えるとき、最初に必要なのは「どんなことに取り組みたいか」を見つけることです。
このとき大切なのは、“お金になりそうなこと”よりも、“やってみたい・興味がある”という気持ちを出発点にすることです。
「お金になりそうだから」と選んだアイデアは、思った通りの結果が出なかった時にすぐにやる気を失ってしまいがちです。逆に自身が楽しめるテーマであれば、自然と工夫したり、続けたりする力も湧いてきます。
また、最初は小さな範囲からで大丈夫です。たとえば、自分の作ったものを家族に見せてみたり、近所の人にお願いしてお手伝いを体験してみたりといった身近な実践が起業の第一歩になります。
家庭内で経営の基本について教える
小学生にとって、「お金をもらう」「サービスを提供する」といった起業に関わる感覚は、まだ身近に感じにくいものです。ですが、日常のちょっとしたやりとりの中で、経営の基本を親子で自然に学んでいくことは十分に可能です。
まずは、「ものを売る」ということの意味から伝えてみましょう。
たとえば、「売る=何かを渡してお金をもらうこと」と思っている子も多いですが、ただ物を渡すだけではなく、「誰かに喜んでもらう」「困っていることを助ける」といった“価値を届ける”ことがビジネスの本質であると伝えることが大切です。
「買ってくれる人が何に困っていて、それにどう応えているのか?」という視点を持つことで、単なる“売買”ではない、人とのつながりを学ぶことができます。
次に、「原価」と「利益」についても、むずかしい言葉を使わずに実生活に落とし込んで説明してみましょう。
たとえばお菓子作りを一緒にする中で、「材料にこれだけお金がかかったよね。じゃあ、売るとしたらいくらにしたらよさそうかな?」と話し合ってみたり「材料費より安く売ったらどうなる?」「高すぎたら誰も買ってくれないかもしれないよね」と伝えてみたりするなど、コストと価格の“ちょうどよい”バランスを考える力が養われます。
また、売る側だけでなく、「買う側の気持ちになって考えること」もとても重要な視点です。
「この商品だったらどんな人が喜んでくれるかな?」「どんな工夫をすれば手に取ってもらいやすくなるだろう?」といった会話を通して、思いやりや想像力をベースにした“お客さん目線”の考え方が自然と身についていきます。
ポイントは、「教える」というより、「一緒に考える」ことです。保護者が“先生”になる必要はありません。むしろ、お子さんのアイデアに耳を傾けながら、「なるほど、じゃあこういう考え方もあるよね」と対話を通して気づきを育てるスタイルが理想的です。
ビジネスの基礎知識は、決して特別な教育の場が必要なわけではありません。日々の生活の中で、お金や商品、気持ちのやりとりに少し目を向けるだけで、経営の考え方はぐんと身近なものになります。
親子で一緒に楽しみながら、「どうやったら人に喜ばれるかな?」を考える時間をつくってみてください。それが、未来の起業の力を育てる第一歩になります。

<ユースキャリアメンターコメント>
子どもが“どうやったらもっと喜ばれるかな?”と考え始めた瞬間、それはもう立派な起業の入り口です。
私たちはつい知識を教えたくなりますが、子どもの創造力を育むには、教えるより一緒に考えることの方がずっと大切です。“こうしたらどう思う?”“試してみる?”と対話を重ねることで、思考力と主体性が自然と育っていきます
小さな規模から試してみる
小学生が起業に挑戦するとき、最初から「立派な事業」にする必要はまったくありません。大切なのは、身近なところから小さく試してみることです。
たとえば、おうちで「お店ごっこ」をして、手づくりの商品を家族に“販売”してみるのも立派なスタートです。
近所のフリーマーケットに出て、使わなくなったおもちゃや小物を売ってみる。あるいは、絵や作品をSNSで紹介して、反応をもらう。こうした体験から、「自分の工夫が誰かに伝わった」「よろこんでもらえた」という感覚が芽生えていきます。
この「誰かに価値を届ける経験」こそが、”起業のタネ”になります。
お金が動く・動かないに関係なく、まずは「試してみる→反応を見る→次の工夫を考える」という流れを何度も経験することで、自然と“ビジネスの力”が育っていきます。
最初の挑戦を通じて、「商品を作って売る」「誰かとやりとりする」といった経験が少しずつできるようになったら、次のレベルでは以下のようなことに挑戦してみるとよいでしょう。
- 「誰のために何をするか」を意識して考えてみること(お客さん像を想像する)
- 価格を考えるときに“原価”や“利益”を話題にしてみること
- 1回きりではなく「もう一度やる」「次はもっとこうする」と改善を考えること
こうしたステップアップをすることで、「なんとなくやってみた」から「目的をもって動いてみた」へと、考え方もぐっと深まります。
一方で、「もっとすごいことがしたい」「もっと広げたい」と思ったときに気をつけておきたいこともあります。
たとえば、以下のようなケースでは、小学生にとって負担やリスクが大きくなりすぎることがあります。
- SNSでの活動が過剰になり、知らない人とのやりとりが発生する
- 大人向けのイベントや商取引に子ども一人で参加しようとする
- お金の流れが複雑になり、本人が管理できないまま進んでしまう
このようなときは、「家庭内で管理できるかどうか」「子どもが安心して続けられるか」という視点を大人がしっかり持つことが大切です。
無理に背伸びをさせるのではなく、本人の成長に合わせて「できることを少しずつ広げていく」ように見守りましょう。

<ユースキャリアメンターコメント>
最初の挑戦で大人がやるべきなのは、“すごいことをさせること”ではなく、“安心して試せる環境”を整えることです。
SNSや販売体験など、刺激の多い取り組みこそ、リスクと成長の両方があります。私たちメンターが現場で大切にしているのは、保護者が過干渉にも放任にもならず、子どもの“ちょっとした勇気”に丁寧に寄り添えるよう伴走することです。

おすすめの小学生起業家向けビジネスアイデア

小学生でも無理なく取り組める、身近で実践的なアイデアをいくつかご紹介します。
手作り品の販売
| どんなことをするビジネスか | 折り紙やビーズ、手作りアクセサリー、しおり、雑貨など、自分で作ったオリジナル作品を家族や友達、フリーマーケットなどで販売するビジネス。 「誰かに使ってもらう」ことを意識しながら工夫することでビジネス体験につながる。 |
| おすすめポイント | 身近な材料で始めやすく、創造力を活かして自分らしい作品をつくることができる。 「こんなのあったらいいな」「友達がよろこんでくれそう」と想像しながら形にする楽しさがあり、達成感も得られやすいアイデア。 |
| 初期費用の目安 | 家にある折り紙やビーズ、画用紙などを使えば0円からでもスタートできる。 材料を買い足す場合も、数百円〜1,000円程度から始められる。 |
| 保護者のサポート | お金のやりとりやネット販売をする場合は、保護者が管理・同伴する必要がある。 お金の計算、値段設定、購入者とのやりとりも一緒に行いながら学ぶスタイルがおすすめ。 特にインターネットで紹介・販売する場合(例:メルカリ・minneなど)は、必ず大人のアカウント管理下で行う。 |
| このビジネスで身につく力 | 自分の作品を「使う人」の目線で考える力材料費と販売価格のバランスを考えるお金の感覚「ありがとう」「かわいいね」と言われる経験による自己肯定感の向上改善や工夫を繰り返す継続力・創造力 |
| ステップアップ例(もっとやりたくなったら) | 学校のバザーや地域のイベントに出店してみるお友達とチームを組んで「お店ごっこプロジェクト」を立ち上げる自分の作品を紹介するチラシやカタログを作ってみる |
お手伝いビジネス
| どんなことをするビジネスか | 家の人や近所の方に向けて、草むしりや整理整とん、ペットの世話などの簡単なお手伝いを“サービス”として提供。 いつものお手伝いを「お願いされてやる」のではなく、「自分から提案して引き受ける」ことでビジネス体験につながる。 |
| おすすめポイント | 特別な材料や道具を使わずに、今できることからすぐに始められる。誰かの役に立てた実感を得やすく、感謝の言葉がそのまま「がんばってよかった!」という自信に変わる。 |
| 初期費用の目安 | 基本的に0円。エプロンや道具が必要な場合でも、家にあるものでできる。 |
| 保護者のサポート | 対象は必ず知っている大人(家族・親戚・近所の顔見知り)に限定する。金額や内容は保護者と相談して決め、最初は付き添いや声かけのサポートを行うのが理想的。 |
| このビジネスで身につく力 | 人のために働く喜びや責任感相手の気持ちを想像して行動する力時間の使い方や報酬に対する感覚自分の「できること」を活かす考え方 |
| ステップアップ例(もっとやりたくなったら) | 「メニュー表」をつくってサービス内容を分かりやすく伝えてみる友達と一緒に“お手伝いチーム”をつくって役割分担してみる何回もやってみて、反応をふりかえってサービスを改善してみる |
イベント出店やフリーマーケット体験
| どんなことをするビジネスか | 学校のバザーや地域のフリーマーケット、子ども向けのマルシェイベントなどに参加して、自分の商品を販売する体験。 手作り品や使わなくなったおもちゃ、工作作品などを並べて、「お客さんに選んでもらう」経験ができる。 |
| おすすめポイント | お店を出すという非日常の体験を通じて、遊びながらリアルな「売る・伝える・届ける」が学べる。 販売だけでなく、接客やお金のやりとりなども実際に体験でき、起業への興味が一気に高まる。 |
| 初期費用の目安 | 出店料が数百円〜1,000円程度かかることがある。 商品は家にあるものや手作りで良い。 |
| 保護者のサポート | 保護者と一緒に参加することが前提。 出店の準備や売上の管理も親子で話し合いながら行うことで、安心・安全に進められる。 |
| このビジネスで身につく力 | お客さんにどう伝えるか考える表現力売上やおつりの計算を通じた実用的な金銭感覚人とのやりとりを楽しむ力、あいさつ・接客の基本準備・実行・ふりかえりのサイクルを学ぶ力 |
| ステップアップ例(もっとやりたくなったら) | 自分だけの看板やチラシを作ってみるどんな商品が人気だったかをふりかえり、次回の出店に活かしてみる商品だけでなく「体験サービス」(似顔絵・ゲームコーナーなど)にチャレンジしてみる |
デジタル活用(動画配信・プチ講座)
| どんなことをするビジネスか | 自分の得意なことや好きなことを、動画やオンライン講座のかたちで発信するビジネス。 たとえば、工作の作り方を説明する動画を撮ったり、得意な教科を「教える動画」として紹介したりすることで、“知っていることを伝える”ことが価値になる。 |
| おすすめポイント | 話す・見せる・伝えるという「表現する力」を楽しく育てられる。 「人前で話すのはちょっと苦手…」という子でも、動画なら何度でも撮り直せるので挑戦しやすく、成功体験につながりやすいのが魅力。 |
| 初期費用の目安 | スマートフォンやタブレットがあればスタートできる。 基本的に無料アプリで編集・投稿ができる(※必ず保護者管理のもとで使用すること)。 |
| 保護者のサポート | インターネットを活用するビジネスは、安全面の管理がとても重要。 動画投稿やライブ配信は必ず保護者が内容を確認し、公開範囲の設定(限定公開・コメント制限など)を行う必要がある。 また、視聴者とのやりとりは大人が仲介し、子ども本人が直接返信しないようにするのが安心。 |
| このビジネスで身につく力 | 自分の得意を言語化・視覚化する「伝える力」構成・台本作り・編集などの創造的な企画力動画を見てくれる人の気持ちを考える視点継続して発信する中で育つ忍耐力や工夫力 |
| ステップアップ例(もっとやりたくなったら) | テーマに合わせたシリーズ企画を立ててみる(例:「週に1回アップする」など)学校外の人にも見てもらえるよう、保護者と一緒に公開範囲を広げる見てくれた人の感想やコメントをヒントに、より役立つ内容へ改善してみる |
小学生の起業を支える上で親ができること

小学生が起業に挑戦するには、本人の意欲や好奇心だけでなく、家庭での見守りやサポートがあってこそ、安全で実りある経験につながります。親の関わり方ひとつで、子どもの学びや成長がより深いものになるのです。
まず大切なのは、子どもが思いついたアイデアに耳を傾け、共に考える時間を持つことです。
「それはダメ」「難しそう」と否定するのではなく、「どうしたらうまくいくかな?」「どんな人が喜んでくれそう?」といった問いかけを通じて、子ども自身がアイデアを深めたり整理したりできるように支えてあげましょう。親が“壁打ち相手”になることで、子どもは自分の考えに自信を持ち、前向きに行動する力が育ちます。
また、外部とのやり取りや金銭の管理といった部分では、必ず大人の目や手助けが必要になります。
特にネット上での販売やSNSを使った発信を行う場合は、安全性の確保が何よりも優先されます。個人情報の取り扱いや相手との連絡方法、商品のやり取りなどについては、親がしっかり監督し、場合によっては実務を一緒に担うことも求められます。お金についても、どこまで自由に扱わせるかを話し合い、基本的なルールを決めておくと安心です。
さらに、挑戦の中で子どもが思うような結果を出せなかったときには、結果よりも「やってみたこと」に価値があると伝えてあげてください。「失敗しても大丈夫」「まずはチャレンジしてみよう」という言葉があることで、子どもは失敗を恐れず、一歩を踏み出す勇気を持てるようになります。失敗を叱るのではなく、「どう感じた?」「次はどうしてみたい?」と一緒に振り返ることで、学びや次の行動に自然とつながっていきます。
子どもの起業体験は、親が伴走者として関わるからこそ、安全で、そして子どもらしく伸びやかに成長できる学びの場になります。大人が「正解」を与えるのではなく、「一緒に考える」「環境を整える」「背中を押す」という関わり方が、何より大きなサポートになるのです。
小学生が起業を学ぶための手段

起業を「学ぶ」方法もさまざまです。
それぞれの特徴を理解した上で、家庭に合った方法を選ぶのがポイントです。
| 評価項目 | 本・オンライン教材・講座などのコンテンツ学習 | ビジネスコンテスト | 体験型ワークショップ | 起業家とのメンタリング |
| 価格の手頃さ | ◎ | 〇 | △ | × |
| 手軽さ・始めやすさ | ◎ | △ | 〇 | × |
| 継続のしやすさ | 〇 | × | △ | 〇 |
| 学びの深さ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ |
| 楽しさ・モチベーション | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
| 親の関わりやすさ | ◎ | △ | 〇 | △ |
| 実践的な経験の有無 | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 他者との関わりの有無 | × | ◎ | 〇 | ◎ |
最近では、さまざまな団体が小学生向けの起業プログラムを提供しています。選ぶ際には、以下のポイントを意識してみてください。
・子どもが主体的に判断・行動できる場か
・金銭管理・販促など「実践」の機会があるか
・大人の関与が適切なバランスになっているか
プログラムのパンフレットや体験談などもチェックしながら、親子で納得できる選択をしましょう。
まとめ|小学生の挑戦を“応援する姿勢”が何より大切

小学生にとっての「起業」は、大人が考えるようなビジネスの成功や利益を目的とするものではありません。それ以上に、「自分のアイデアで誰かを喜ばせる」「やってみたらできた」という実感を得られる、かけがえのない学びと成長の機会です。
起業というテーマは一見難しそうに見えるかもしれませんが、だからこそ、保護者のサポートが大きな意味を持ちます。お金の管理や安全面の見守りはもちろん、アイデアに耳を傾けたり、失敗しても笑顔で応援したりといった関わりが、子どもにとって何よりの安心材料になります。
「起業をさせる」のではなく、「やってみたい!」という気持ちに寄り添い、無理なく小さく始めさせてあげること。それが結果として、「やらせてみてよかった」と親子ともに思える体験につながっていきます。
今の時代は、正解がひとつではない社会。そんな中で、「自分で考え、選び、動いてみる力」を子どものうちから育てていくことは、将来どんな道を選んでも役に立つ大きな力になります。どんなに小さなチャレンジでも、親が信じて応援することで、子どもはその一歩を自信に変えていきます。「応援する姿勢」こそが、子どもにとって最高の土台です。
お子さまの”最初の一歩”をサポートしてみませんか?

お子さまが「起業」に興味を持ちはじめたとき、どんな風に関わればいいのか迷う方も多いと思います。
ユースキャリア教育機構では、実際に中高生も参加し、起業をテーマにしたプロジェクトを立ち上げています。
現役の学生起業家やメンターと出会える機会もあり、初めての挑戦をしっかりサポートできる環境が整っています。
興味のある方は、ぜひ無料のオンライン説明会にご参加ください!