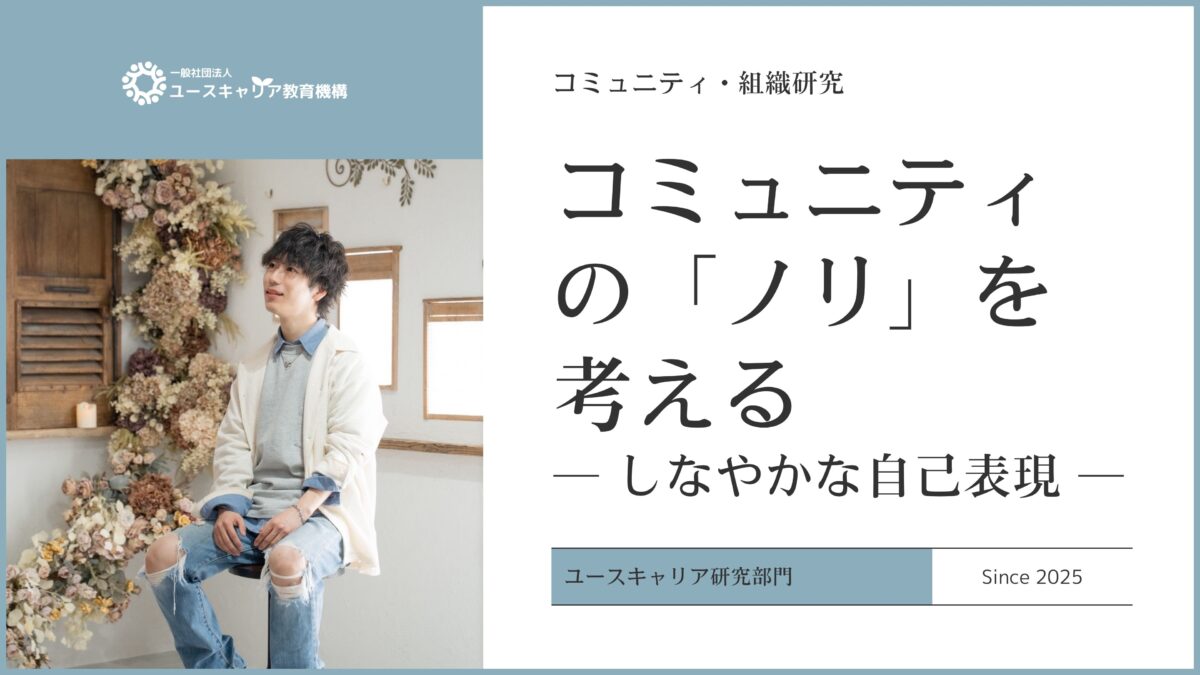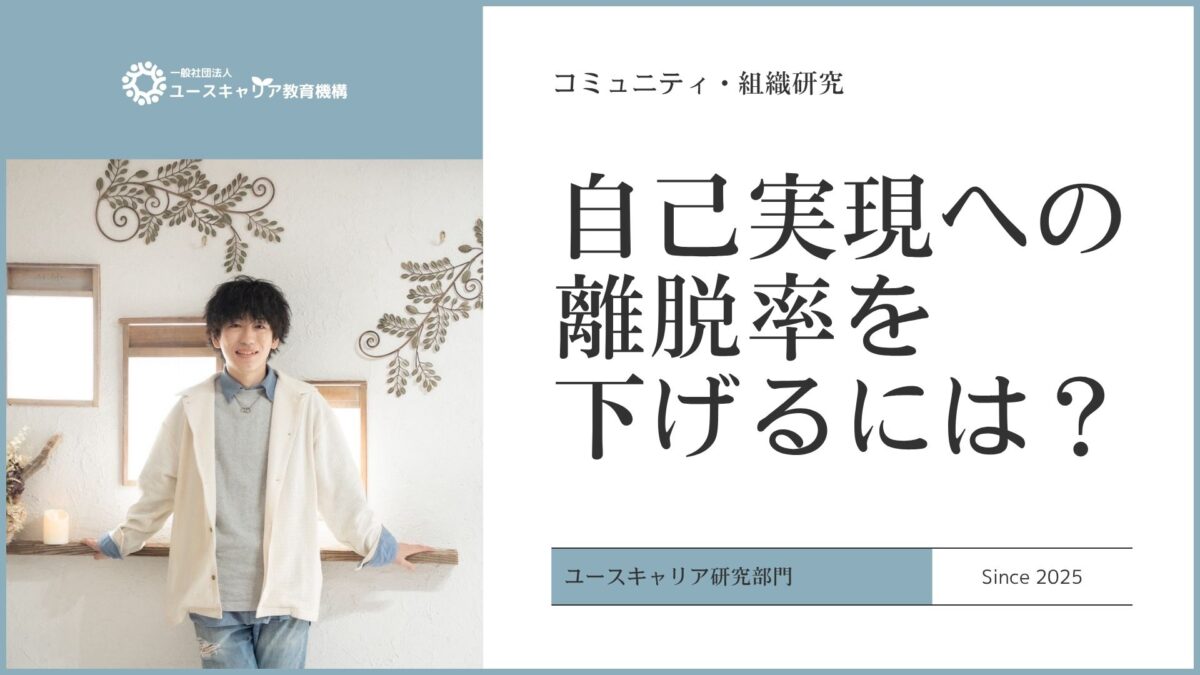現場で体感したThe specialistのノリ
一般社団法人ユースキャリア教育機構・研究員の井上寛人です。
先月からスタートした本連載企画の、第2回目となります!
前回記事はこちら▽
第2回のテーマは、「コミュニティのノリを意識したうえで、どう自己表現していくか?」です。
The specialistの土曜日のコンテンツ(定例勉強会)に継続的に参加する中で、ここならではの“コード”があるなと感じてきました。
僕の印象では、ちょっと男子校っぽいノリ。上下関係はありつつも、お互いをいじったりツッコんだりする距離感があって、それが逆に新鮮で。
僕自身は、中高時代にあまり上下関係がしっかりした環境にいなかったので、この雰囲気にはいつも新しい刺激をもらっています。
コードってなんだろう?
「コード」とは、ある環境の中で「こうするのが普通」と、暗黙のうちに共有されている行動や言葉、ふるまいのこと。たとえば、レストランでのドレスコードや、就活の場面でスーツを着るのが当たり前になっていることも、コードの一例です。
つまり、コミュニティや場の雰囲気によって自然と成立している“規範”のようなものです。「コード」だと少し堅く聞こえるので、ここからは「ノリ」という言葉で進めていきます。
ノリを読み取る力が、コミュニケーションをラクにしてくれる

The specialistに限らず、どんな組織やコミュニティにも「この場ではこうするのが適切そう」という雰囲気がありますよね。
そして、そのノリを適切にキャッチできると、ぐっとコミュニケーションが取りやすくなります。なぜかというと、同じ行動でも、場が違えばまったく違う受け止められ方をするからです。
たとえば、昔は先生が厳しく怒鳴ったり体罰をすることが、教育の一環として当たり前のように扱われていた時代もありました。でも今では、そういった関わり方はNGになっていますよね。
つまり、「どこで、誰と、いつ関わるか」によって、望ましいふるまいは変わってくる。だからこそ、「この場ではどんなふるまいが歓迎されるのか?」とノリを意識する視点が大切になってきます。
コミュニティのノリを知るヒント:「みかえり」に注目する
「でも実際、どうやってその場のノリを読むの?」
ヒントになるのが、「きっかけ・行動・みかえり」という3つの要素です。これは「行動分析」という学問における基礎的なフレームワークです[1]。
私たちはなにかの「きっかけ」を受けて「行動」を起こします。そして「行動」の結果、得られる「みかえり」が、それ以降の「行動」に影響を与えます。その場のノリを知るためには、この「みかえり」に注目してみましょう。
たとえば、先輩から「自己紹介してよ」と言われたとします(きっかけ)。ちょっと勇気を出して、一発ギャグを添えて自己紹介してみたら(行動)、場がドッと盛り上がった(みかえりA)としましょう。そんなときは、「この場ではユーモアが歓迎されるんだな」と感じられるでしょう。
逆に、誰も反応してくれなかったとしたら(みかえりB)、「この空気ではあのノリは通じないかも」と学べるかもしれません。
もちろん、自分が動かなくても、他の人の行動とそれに対する周りの反応を見るだけでも、場のノリを把握するヒントになります。
そうして得た「みかえり」から、その場のノリを察することができると、その場において望ましいとされる「行動」を選択しやすくなります。
場のノリに「合わせる」だけが正解じゃない

ここで大切にしたいのが、「いつでもその場のノリに合わせなきゃいけないわけじゃない」という視点です。
自分の目指す方向や、やりたい表現と照らし合わせたときに、「今このノリに合わせるのはちょっと違うな」と感じることもあると思うんです。
そんなときは、その規範から少しずらした自己表現をするのも、“あえて”破ってみるというのもありだと思います。
たとえば、起業家やリーダーを目指している方にとっては、場に合わせることよりも、自分なりの表現を行う方が自己実現につながる場面もきっとあるはずです。
今いる環境が「すべて」ではない

いま皆さんが身を置いている環境——たとえば起業家コミュニティや、経営に関心のある仲間が集う場——は、日本全体から見ればとても珍しい場所かもしれません。
だからこそ、そこでの「当たり前」や「正解」が、必ずしも世の中すべてに通じるわけではないことも、どこか頭の片隅に置いておいてもらえるといいなと思います。
もしその環境の雰囲気が合わないなと感じたら、無理してなじもうとしなくても大丈夫です。逆に、めちゃくちゃ居心地がよくて楽しいなら、思いっきりその空間を楽しんじゃってください!
大切なのは、「ここだけが世界のすべてじゃない」「それぞれの場所には、それぞれのノリがある」ということを知っておくこと。その視点があるだけで、ずいぶん心が軽くなると思います。
視野を広げるために、外の世界へ

コミュニティのノリや文化は千差万別です。だからこそ、自分が属している界隈に閉じこもっていると、「ここでの価値観が当たり前」と思い込みやすくなるのではないでしょうか。するとあなたが世界を見る視野は狭まり偏り、信念が凝り固まってしまいます。
中学・高校時代、クラスのノリやスクールカーストが“世界のすべて”のように思えた経験はありませんか?その後、大学に入って視野が広がると、それが“無数にある価値観の中のひとつ”だったと気づくように、大人になってもその”井の中の蛙現象”は起こります。SNSにおけるフィルターバブルも、それに近い現象と捉えることもできるでしょう。
そうして強化された「信念」が合理的な場合はよいのですが、非合理的だった場合、それはメンタルヘルスに負の影響をもたらす恐れがあります。

アメリカの臨床心理学者アルバート・エリスは、「イラショナル・ビリーフ」という概念を提唱しました。これは、『「現実に則さない非合理な信念」、「ねばらない」「べきである」といった要求・命令・絶対的な思考パターン』のことをいいます[3]。イラショナル・ビリーフは不安、抑うつ、敵意との関連[4]や自尊心との負の関連[5]があると言われています。
例えば、私が通っていた高校では『17歳までに彼氏彼女ができなった人は、生きた化石=シーラカンスになる。だからそれまでに恋人を作らなければならない。』という半分冗談、半分本気な不合理な信念がありました(笑)合理的に考えれば、必ずしも17歳までに恋人がいなくても人生は不幸にはならないと思うのですが、当時の私たちはこのタイムリミットにしっかり怯えていました。
そんなイラショナル・ビリーフの沼にハマらないためにも、積極的にさまざまな場に足を運び、違う文化と触れてみるのはいかがでしょう。そうして異文化に触れた分だけ、あなたの「世界を見る視点」が増えていきます。すると、世界そのものや自身の価値観をより相対的に見られるようになる。その結果、関係性やカルチャーに応じてコミュニケーションスタイルを使い分けられる、より柔軟なリーダーになれるはずです!

<ユースキャリア メンターコメント>
逆に、いまユースキャリアのメンバーでは無い方にとっては、ユースキャリアが「外の世界」にあたるかなと思います。
今のままでは自分の人生が開けない…と感じる方は、視野を広げるために、一度うちに遊びに来てもらうのは大歓迎です!
ノリを“つくる側”としての意識

ここからは、ノリを「読み取る」立場ではなく、「つくる」立場としての視点に少し目を向けてみたいと思います。
この記事を読んでくださっている方の中には、すでに何らかのコミュニティでリーダー的役割を担っている方もいらっしゃると思います。あるいはこれから、自分のコミュニティやプロジェクトを立ち上げようとしている方もいるのではないでしょうか。
そういった立場になると、自分が無意識のうちに「その場の雰囲気」や「ふるまいの基準」をつくっていく側になることがあります。
たとえば、高校の部活で先輩が引退し、新しい代になったとたん部の雰囲気が変わった…なんて経験をされた方もいるかも。あれって、まさにリーダーや影響力のある人が変わることで、自然と“場のノリ”も変わっていきます。
つまり、「リーダーになる」ということは、気づかぬうちに周囲の行動の基準を形づくっているということでもあるのです。
自分の組織をつくる上で大切にしたいこと
リーダーには、それぞれの魅力的な個性があります。なのでチームや組織がその方の雰囲気に染まっていくのは、自然なこと。
そのうえで、どんなカラーのチームであっても、「これだけは意識できるといいな」と思っているのが、“チームの心理的安全性”です。
心理的安全性って?
心理的安全性という言葉は、ハーバード大学の心理学者エイミー・エドモンソンが提唱した概念で、「チームの中で対人関係におけるリスクをとっても、大丈夫だ、というチームメンバーに共有される信念のこと」と定義されています[5]。
石井(2020)は、現場でより使いやすいように心理的安全なチームの定義を「メンバー同士が健全に意見を戦わせ、生産的でよいしごとをすることに力を注げるチーム・職場のこと」と言い換えました[1]。
たとえば、「あの案、ちょっと違うと思うな」とか、「こういうのもアリじゃない?」といった言葉を、遠慮なく・委縮せずに言えるかどうか。そんな雰囲気があるチームは、心理的安全性が高いと言えます。
Googleの研究によると、心理的に安全なチームほど、パフォーマンスと創造性が向上し、メンバーの離職率も低く、収益性が高く、多様なアイデアを効果的に活用することができるとのこと[6]。つまり、「いいチーム」をつくるための土台になってくれるとても大切な要素なんです。
心理的安全性を高める4つの因子
では、心理的安全な場をどのようにしてつくればいいのでしょうか?
僕の大学院の先輩でもある石井遼介さんの著書『心理的安全性のつくりかた』(2020年)によると、心理的安全性を構築するための日本ならではの4つの因子があるみたい[1]。私なりの具体例を添えて紹介させていただきます!
- 「何を言っても大丈夫」話しやすさ因子
あの先輩、しごできなのにめちゃくちゃ話しやすい!失敗をしてしまった報告をしても、まずは「ナイストライ!」って褒めてくれてから、建設的なフィードバックをしてくれる。話しやすいわ~
- 「困ったときはお互い様」助け合い因子
同期のAは、同志でありライバル。お互い日々切磋琢磨してる。でも、私が困っているとき、彼女は自身の強みで私の弱みをカバーしてくれる。まじでいいやつ。私も彼女が困ってるとき絶対サポートするって決めた! - 「とりあえずやってみよう」挑戦因子
この場はいつも前向きな雰囲気。やりたいアイデアを思いついたら、「いいね。とりあえずやってみよう!」と応援してくれる。これまでは「自分のやりたい」を伝えるのに委縮してたけど、ここでは安心して宣言できる! - 「異能、どんと来い」新奇歓迎因子
俺は「なんか普通じゃないよね」って腫れもの扱いにされることが多かった。でもこの場は「その人らしさ」を面白がってくれるから、ありのままの自分でいられる!この個性は俺の武器だ。どんどんやってやる!
いかがだったでしょうか。これらの要素をリーダー自身の個性や世界観に沿って意識的に取り入れていくことで、心理的安全性の高い組織文化を育てていくことができます。

<ユースキャリア メンターコメント>
「何でも話しやすい」
「困ったときこそ手を差し伸べる」
「挑戦を歓迎する空気」
「奇人変人歓迎!!」
という空気があるチームは長続きしやすいなあと、この数年色々な組織を見ていて感じます。
現場的にも、秀逸な分類だなと思います!とても大事。
あなたの行動が、メンバーの未来を変える
最後に、ひとつお伝えしたいことがあります。
「組織文化」と聞くと、ちょっと大げさなことのように感じるかもしれません。でも実際は、毎日の小さなふるまいや言葉の積み重ねが、自然とその場の文化をつくっていくんです。
誰かの挑戦に「いいね!」って一言返したり、誰かがちょっと勇気を出した瞬間に寄り添ったり。そんな日々のやりとりが、その人にとっての「ここは安心できる場所なんだ」っていう感覚につながっていきます。
それが、その場に集う人々の行動や心理、成長、挑戦を大きく左右する“土壌”となっていきます。
その土壌が、柔軟性と安全性を備えているほど、メンバーは安心して自己表現ができ、時にそのノリから逸脱することすらも許容される。そんな組織こそ、しなやかで強いチームになっていくはずです。
ぜひ、あなたらしさを大切にしながら、安心して意見が言える、そんなチームやコミュニティを一緒につくっていけたら嬉しいです!
[1] 石井 遼介(2020)『心理的安全性のつくりかた 「心理的柔軟性」が困難を乗り越えるチームに変える』日本能率協会マネジメントセンター
[2] 中田(北出) 薫(2006)”イラショナル・ビリーフと感情の体験様式との関連 ―感情体験尺度作成の試みを通して”パーソナリティ研究 2006 第 14 巻 第 3 号 241–253
[3]Goldfried, M. R., & Sobocinski, D(1975) ”Effect of irrational beliefs on emotional arousal” Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43, 504–510.
[4] Daly, M. J., & Burton, R. L. (1983) “Self-esteem and irrational beliefs: An exploratory investigation with implications for counseling” Journal of Counseling Psychology, 30, 361–366.
[5]Edmondson, A. (1999) “a shared belief held by members of a team that the team is safe for interpersonal risk taking.” Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative science quarterly, 44(2), 350 – 383.
[6]ガイド:「効果的なチームとは何か」を知る-Google re :Work