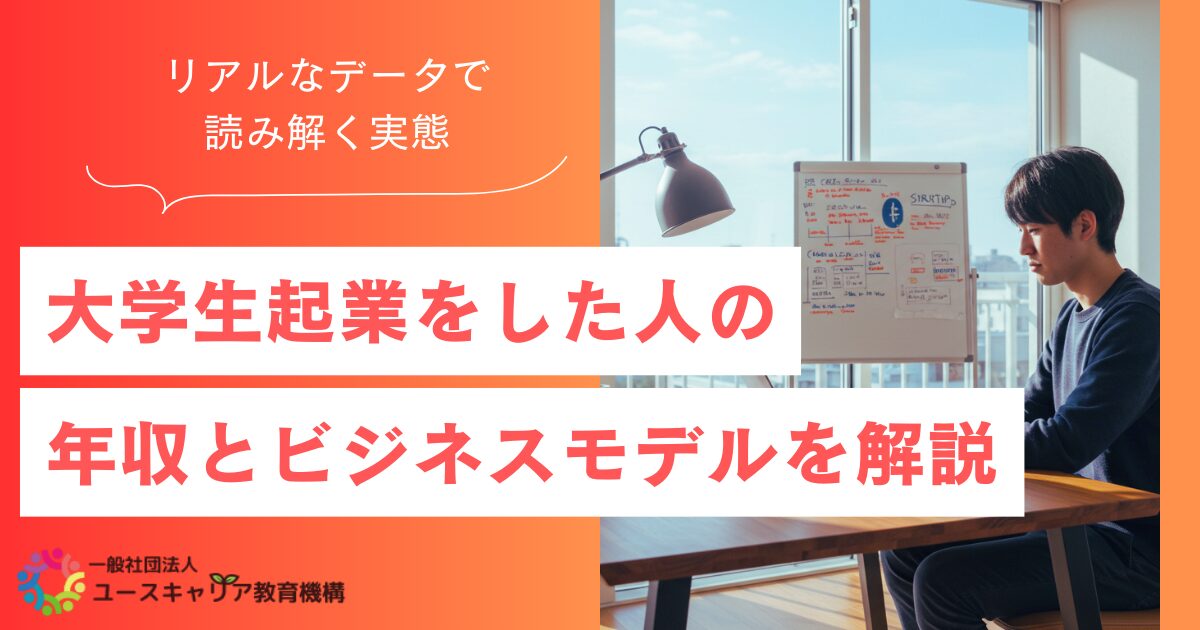起業に挑戦する大学生が増える中で、気になるのはやはり「収入」や「将来の年収」のこと。
SNSでは「月収100万円」など華やかな投稿が目立ちますが、それがすべてではありません。
この記事では、様々な大学生起業家の年収や共通点、大学生が起業で得られるその他の価値についてわかりやすく解説します。
起業に興味はあるけど、「実際どれくらい稼げるの?」という疑問を持つ方に、リアルなヒントをお届けします。
✅ 学生起業家の平均年収や収入の分布を把握できる
✅実際に稼いでいる学生起業家の事例がわかる
✅ 起業で得られる収入以外の成果や価値を知ることができる
✅起業に向けた一歩の踏み出し方についてヒントを得られる

大学生起業における「年収」の定義

経営において、お金の流れに関する単語は以下のようなものがあります。
- 年収:役員報酬など、個人に入ってくるお金
- 収入:事業全体で得た売上や報酬などを広く含む
- 可処分所得:自由に使えるお金(個人所得や、経費を使える範囲など)
- 営業利益:会社の本業で得た純粋な利益
- 経常利益:営業利益に加え、本業以外の収益も含めた利益
今回の記事では「年収=個人に入ってくる金額」と定義して話を進めていきます。
統計で見る大学生起業家の年収の実態

近年、起業に取り組む大学生は少しずつ増えてきていますが、全体から見ればまだ少数派であるのが実情です。
調査のデータによれば、実際に起業している大学生の割合はわずか1.5%にとどまっており、大学生全体から見れば「起業」はまだ特別な選択肢といえます(参考:GUESSS 日本事務局「GUESSS 2021 Japanese National Report」)。
一方で、「将来は起業してみたい」「ビジネスをやってみたい」と興味を持っている学生の割合は着実に増えています。2023年の調査では、起業に関心がある大学生の割合は12.4%、高校生では14%と、むしろ高校生のほうが関心度が高いという興味深い傾向も見られました(参考:株式会社ペンマーク「【高校生13万人調査】高校生の起業志望率は約14%、大学生(約12.4%)を上回る。」)。
Z世代の若者たちは、社会課題への関心やSNS発信への慣れ、自由な働き方への憧れなどから、「会社に就職する以外の選択肢」を早くから視野に入れるケースが増えています。
大学生が実際に取り組んでいるビジネスには、初期費用が少なく、個人でも始めやすい業種が多く見られます。特に、スキルや時間を活かして自由に働けるスタイルが支持されており、在学中でも取り組みやすいのが特徴です。
たとえば、以下のようなビジネスがよく選ばれています。
- SNS運用代行:企業や店舗のInstagramやX(旧Twitter)を代わりに運用し、集客や発信をサポートする
- アフィリエイト:自分のブログやSNSで商品を紹介し、成果報酬を得る仕組み。スキルと継続力が求められます
- 物販:フリマアプリやECサイトを活用し、仕入れた商品を販売。中古品や海外輸入商品を扱う学生も増えています
- Web制作やデザイン:HTMLやWordPressを使ってホームページを制作したり、バナーやロゴデザインを受注するビジネス
- オンライン講座:英語やプログラミング、イラストなど、自分の得意分野を教材化して販売したり、Zoomなどでレッスンを行う
- 教育系サービス(家庭教師・学習支援など):自分の得意科目を活かして、小中高生に学習指導を行う。対面・オンライン両方で展開可能
これらはいずれも、「身近なスキル」「少ない初期投資」「すぐに実行できる環境」が揃いやすいため、大学生にとって挑戦しやすいジャンルといえます。
また、アルバイトでは得られない裁量や経験が積めることも、学生にとっての魅力となっています。
一方で、これらのビジネスは競争も激しく、収益を安定させるまでには時間がかかる場合も多くあります。

<ユースキャリアメンターコメント>
Z世代の学生は、“就職かフリーランスか”といった二択ではなく、“自分らしい働き方を自分で作る”という視点で動き始めている印象があります。
大学の授業では学びきれない、試行錯誤を繰り返すリアルな経験を、起業を通じて掴もうとする姿勢が広がってきています。
年収数万円から数億円超まで!大学生起業家の事例を紹介

学生起業と一口にいっても、その収入の幅は非常に大きく、人によってまったく異なります。
ここでは、実際の事例を年収帯別に紹介しながら、起業家たちがどのような道を歩んできたのかやその特徴を解説します。
【事例①】株式会社タイミー 小川嶺さん
| 大学生時代の活動 | 立教大学2年のときに最初の会社を立ち上げ、いくつかの事業を経て、現在の「タイミー」の原型となるアイデアにたどり着いた。 |
| 起業のきっかけ | 高校3年の冬、尊敬する祖父の死と家業の廃業をきっかけに「家業を復活させたい」という想いが芽生え、起業を決意。 |
| 事業内容 | 「スキマ時間」に働きたい人と、すぐに人手が欲しい企業をマッチングする事業。 |
| 起業当初の課題・つまずき | サービス立ち上げ初期は、現場の声やユーザーニーズを十分に理解しないままプロダクトにこだわりすぎてしまった。 |
| 大学生時の年収 | 数千万円 |
| 支えてくれた人・リソース | エニグモ代表・須田将啓氏:最初のアイデア披露や投資相談の相手であり、起業家ネットワークの入り口となった。 サイバーエージェント藤田晋社長:資金調達時に「1億円ください!」と直談判し、熱意を伝えて出資を得た。 創業メンバーやエンジニア:自身もプログラミングを学びつつ、仲間と試作を重ねてサービスを形にした。 |
【事例②】株式会社Rover 後上航さん(ユースキャリア教育機構OB)
| 大学生時代の活動 | 慶應義塾大学理工学部に在学中の2022年3月、株式会社Roverを設立。授業と並行しながら複数の案件に対応し、組織体制の構築や業務改善にも注力した結果起業に成功。 |
| 起業のきっかけ | 大学在学中にWebマーケティングや教育関連の活動に取り組む中で、感謝や期待の声を受け取り、自分の価値を届ける場を増やしたいと感じたこと。 |
| 事業内容 | Webコンサルティング事業、DX推進・AI活用支援事業 |
| 起業当初の課題・つまずき | 案件の急増により自身の業務量が逼迫し、寝る時間がないことも多々あった。 |
| 大学生時の年収 | 1000万円~1500万円 |
| 支えてくれた人・リソース | ユースキャリア教育機構:先輩経営者のメンタリングを受けながら経営を実践的に学んでいた。 |
【事例③】Tさん(仮名)|関東の大学生 フリーランスWebデザイナー
| 大学生時代の活動 | 授業の合間や休日を使って、1件あたり5〜15万円のWebサイト・LPデザインを月3〜4件受注。SNSでポートフォリオを発信し、クチコミで仕事を広げた。 |
| 起業のきっかけ | 大学1年のとき、SNSで知り合ったフリーランスからバナー制作を依頼されたことをきっかけに、自身のスキルを活かして仕事を受け始めた。 |
| 事業内容 | 個人事業主や中小企業向けにWebサイトやLP(ランディングページ)をデザイン・制作。ブランド設計からビジュアル表現まで一貫して手がける。 |
| 起業当初の課題・つまずき | SNSやクラウドソーシングに登録してみたものの、実績ゼロの状態ではなかなか信頼を得られず、提案文を送っても返信が来ない日々が続いた。 時間管理にも課題があり、大学の課題やサークル活動との両立が難しく、納期ギリギリになることも多かった。 |
| 大学生時の年収 | 400〜450万円 |
| 支えてくれた人・リソース | 同じゼミにいた先輩デザイナー:デザインの添削や提案文の書き方を直接アドバイスしてもらえるようになり、徐々に受注率も上がっていった 学生起業支援制度:小規模な補助金とコワーキングスペースの利用も可能になり、活動場所と金銭面の負担が軽減された |
【その他の多数派】月3〜5万円規模の副業型学生起業
この層の学生は、あくまで本業は「学業」としつつ、空いた時間やスキルを活かして、月3〜5万円ほどの収入を安定的に得ることを目指しているケースが主流です。
よくある取り組みとしては、
- noteなどを使った有料記事の販売(自分の学びや考察を文章にして発信)
- LINEスタンプやイラストのデジタル販売(イラストが得意な人の趣味×収益化)
- 小規模な個別指導塾・家庭教師サービスの立ち上げ(学力と信頼を活かした教育ビジネス)
といった、比較的低コストかつ個人のスキルや趣味を活かした“スモールビジネス”が中心です。これらの活動の多くは、「一度きりの収益」ではなく、月に数千円〜数万円の収入を継続的に得ることを目的としています。
継続的な更新や改善を重ねながら、徐々に顧客やファンを増やしていくスタイルで、「まずはやってみる」「経験を積む」ことに価値を置いているのが特徴です。
- 年収数千万円〜億超えの学生は、実際に存在しますが、決して多数派ではありません。
- 多くの学生起業家は、数万円〜数十万円程度の副業的スタートを切り、そこからスキルや人脈を積み上げていくケースが一般的です。
- 大切なのは、「どれだけ稼げるか」よりも、「どのように継続し、成長につなげていくか」という視点です。

<ユースキャリアメンターコメント>
年収や成果に違いが出る背景には、“戦略の差”があります。
どんな市場を選び、どうポジショニングし、誰に届けるかを真剣に考えた人ほど、成果に再現性があるのです。
一見似たような活動でも、戦略の設計と修正を繰り返せる人が、継続的な成果を手にしています。
事例を読むときは、どんな選択がその結果につながったのか、その“構造”に目を向けてみてください。

学生起業がもたらす多様な成果とは|年収以外に得られる価値

「学生起業」と聞くと、まず注目されるのはやはり金銭面かもしれません。
ですが、実際に起業を経験した大学生たちが口を揃えて語るのは、お金以上に得られた「成長」や「人との出会い」です。
ここでは、学生起業によって得られる“年収以外の価値”についてご紹介します。
実践的なビジネススキルが身につく
起業を通じて得られるスキルは、机上の知識とはまったく異なります。
マーケティング、営業、交渉、資金管理、契約の基本など、実務の中でしか学べない“生きたスキル”を、肌で感じながら習得できます。
これらは、起業に限らず将来あらゆるキャリアの場面で活かせる力になります。特に自分で責任を持って意思決定をする経験は、どんな職種でも通用する強みになります。
社会人とも対等に関わる「人脈」ができる
起業すると、同世代だけでなく、メンターやクライアント、起業家仲間など、社会人との接点も一気に広がります。
学生でありながら「ひとりの経営者」としてビジネスの現場に関わることで、実践的な学びや、思考の深さを体感できるのは大きな魅力です。
信頼できる人と出会い、支え合える関係を築くことが、起業を長く続ける上での大きな支えにもなります。
自信と主体性が育つ
大学生のうちに起業に挑戦することで、「自分のアイデアや行動が誰かの役に立った」という実感を得ることができます。
誰かに喜ばれたり、お金をいただいたりする経験は、単なる達成感ではなく、「自分は価値を生み出せるんだ」という自己信頼(自己効力感)を育てます。
また、うまくいかないことに向き合い工夫しながら改善していくプロセスを重ねることで、少しずつ「自分で考えて動ける」という主体性が身についていきます。この力は、将来どんな進路を選ぶにしても、大きな支えとなってくれるはずです。
キャリアの選択肢が広がる
起業経験は、就職活動においても大きなアピールポイントになります。
WILLFU(学生起業スクール)や中小企業基盤整備機構の調査でも、「起業経験が面接やエントリーシートで非常に評価された」という声が多数報告されています。
実際に、ビジネスを自ら立ち上げた経験は、「行動力・企画力・実行力」を証明する確かな実績となり、一般企業からも高い評価を受けることが多いです。
学生起業で得られるのは、単なる一時的な収入ではなく、将来のキャリアを形づくる“土台となる経験”です。スキル・人脈・自信・可能性 ー こうした要素こそ、学生起業を経験した人たちが長く活かしていく“本当の資産”だと言えるでしょう。

<ユースキャリアメンターコメント>
学生が起業を通して得られる価値は、単なる“スキル習得”や“実績作り”にとどまりません。
現場で多くの挑戦を見てきましたが、ビジネスの現場で社会人と関わりながら信頼を得たり、自分のサービスで誰かに喜ばれたりする中で、考え方や人間関係、キャリア観までガラッと変わっていくのを感じます。
起業は“実践を通じて社会とつながる経験”そのものなんです。
学生起業で収入が伸び悩む典型的なパターン

学生起業は自由度が高く、柔軟に挑戦できる一方で、つまずきやすい落とし穴も多くあります。
特に収入面で苦戦する学生起業家には、以下のような共通した課題や思考パターンが見られます。
リサーチ不足
「これ面白そう」「自分がやってみたい」といった気持ちだけでサービスを立ち上げてしまい、十分なリサーチをせずに進めてしまう学生起業家は少なくありません。
アイデアそのものにワクワクするのは悪いことではありませんが、「誰が必要としているのか」「本当にお金を払ってまで欲しいと思われるか」といった視点が欠けていると、まったく売れないという事態に直面します。
せっかく時間と労力をかけて準備しても、反応がなければ自信を失い、モチベーションが急速に下がってしまうのもよくあるパターンです。
起業の初期こそ、友人や想定顧客へのヒアリング、類似サービスの調査など、市場のニーズと競合環境を丁寧に把握することが不可欠です。
ほんの少しのリサーチだけで、売れ行きや反応が大きく変わることもあります。起業の成否は、スタート前の準備にかかっていると言っても過言ではありません。
収益構造が曖昧
「売上が立っているのに、なぜかお金が手元に残らない」というのは、学生起業家に多く見られる典型的な失敗です。
原因として多いのが、広告費や外注費、仕入れコストなど、目に見えにくい経費が想定以上にかかっているケースです。特に初心者は、「売れた=成功」と考えてしまい、利益や継続性を十分に意識しないまま事業を続けてしまう傾向があります。
しかし、ビジネスは「売上」よりも「利益」が残らなければ継続できません。固定費と変動費の違いや、利益率、キャッシュフローといった基本的な視点を理解するだけでも、収支のバランスを見直すきっかけになります。赤字で気づかずに走り続ける前に、一度立ち止まり、ビジネスモデルをシンプルに見直すだけで、黒字化に転換できる可能性は十分にあるのです。
学業との両立ができない
学生起業でよくある悩みのひとつが、学業との両立の難しさです。
レポートやテスト、グループワークなどの課題に追われて事業に手が回らなくなったり、逆に起業にのめり込みすぎて授業に出なくなり、単位を落としてしまったりするケースも少なくありません。
「どちらも頑張りたい」と思っていても、時間の使い方を誤ると学業も起業も中途半端に終わってしまうことになりかねません。特に起業の初期は、やることも覚えることも多く、忙しさに押し流されてしまいやすい時期です。
だからこそ、週ごとの予定を見える化して余白を確保したり、「緊急ではないが重要なこと」を見極めて計画に落とし込んだりといったタイムマネジメントの工夫が不可欠です。
起業を成功させるためには、ビジネスのスキルだけでなく、時間をデザインする力も重要な経営能力のひとつです。
発信力・広報力の不足
学生起業において、「いいサービスなのに知られていない」というケースは非常に多く見られます。商品やサービスそのものは魅力的でも、それを必要としている人に届けられなければ、存在していないのと同じです。
SNSやブログを活用した情報発信、知人やコミュニティへの紹介など、広報活動は「売る」以前の前提条件ともいえます。
発信は「自己PR」ではなく、「誰かに届くきっかけを増やす行動」です。それを地道に続けることが、信頼や成果につながっていきます。
孤立している
周囲に相談できる仲間や先輩がいないまま、一人で悩みを抱え込んでしまうと、モチベーションも落ち、方向性も見失いがちです。
「もうダメかも…」と思っていたことが、たった一言のアドバイスで解決することもあります。小さなことでも気軽に話せる相手を持つことは、収益以上の価値があります。
これらの失敗は、どれも決して特別なものではなく、多くの学生が一度は経験するものです。重要なのは、失敗を避けることではなく、早く気づいて次の行動に活かすこと。試行錯誤のスピードと柔軟さが、収入の伸びにも直結していきます。
年収を伸ばしている学生起業家の共通点

収入を安定的に伸ばしている学生起業家には、いくつかの共通した特徴があります。派手なスタートを切るのではなく、堅実に着実に力をつけながら前に進んでいることが多いのがポイントです。
スモールスタート思考:小さく始めて、少しずつ積み重ねる
最初から大きな売上や事業規模を目指すのではなく、自分ができる範囲で商品やサービスを試し、小さな一歩から始めるスタイルです。
身近な人に試してもらう、SNSで反応を見てみるといった地道な取り組みの中で、改善を重ね、徐々に顧客が増えていきます。
その結果、プレッシャーに追われることなく収益を伸ばすことができ、無理なく継続できる事業として定着していくのが特徴です。スモールスタートは、失敗のリスクを最小限に抑えながら、学びと成長を最大化できる起業の入り口として非常に有効です。
自分の強み×ニーズ:得意な領域と市場のニーズを重ねて挑戦
学生起業で成果を出している人の多くは、「自分の強み」と「相手のニーズ」の重なりに注目しています。
単に「やりたいこと」だけで突き進むのではなく、自分の得意なことや好きなことを活かしながら、それが誰かの困りごとや欲しい価値とどうつながるかをしっかり考えているのが特徴です。たとえば、イラストが得意なら「子ども向け教材のデザイン」など、得意分野をニーズに沿って展開する工夫が見られます。
このように、自分視点と相手視点の両方を持てることが、持続的な価値提供と信頼獲得につながっていきます。
継続的な発信:SNSやブログで実績を可視化し、信頼を獲得
学生起業家の中には、SNSやブログ、ポートフォリオサイトなどを使って、自分の活動や実績をこまめに発信し続けている人が多くいます。
継続的な情報発信によって、「この人は何をしているのか」「どんな思いで取り組んでいるのか」が可視化され、自然と信頼性が高まっていきます。この“見える実績”が、新たな仕事の依頼や口コミ、コラボのきっかけにつながることも少なくありません。
特に学生という立場では、社会人と比べて実績が少ないからこそ、発信を通じて「人となり」や「姿勢」を伝えることが大きな武器になります。
支援環境の活用:メンターや仲間の存在により、方向修正が早い
成果を出している学生起業家に共通するのが、信頼できるメンターや仲間とつながっていることです。
一人で悩みを抱え込まず、壁にぶつかったときにすぐ相談できる相手がいることで、課題の早期発見と修正が可能になります。
自分だけでは気づけない視点をもらったり、方向性を見直したりすることで、無駄な遠回りを避け、失敗のリスクも減らせます。また、仲間同士で進捗を共有し合うことがモチベーション維持にもつながり、結果として行動のスピードと学びの深さが加速していきます。
どんなに優れたアイデアがあっても、孤立した状態では成長に限界があるからこそ、支援環境を上手に活用できる力も起業家にとって重要な資質といえます。

<ユースキャリアメンターコメント>
成果を出している学生は、背伸びをせずに“自分にできること”をベースに、試して・発信して・周囲に相談しながら、着実に前に進んでいます。
強みを活かしつつニーズを見極め、地道な積み重ねを続けられる人が、最終的に収入や信頼を伸ばしていく。派手さよりも、コツコツ続けられる力が何より大事だと感じます。
学生起業のリアルを読んだあなたが考えるべきこと

年収や売上といった数値は、学生起業の一部を表す指標です。ただし、それだけで起業の価値を測ることはできません。多くの学生は、起業を通じて「スキルの習得」「視野の広がり」「実践的な人間関係構築」など、将来につながる経験を得ています。
起業の目的は人によって異なります。就職に活かしたい人もいれば、自分のアイデアを形にしたい人、社会課題に取り組みたい人もいます。そのため、収入の多さだけで判断せず、自分にとって何が重要かを整理しておくことが重要です。
もし今の段階で迷っているなら、いきなり事業を始める必要はありません。情報収集や小さな行動から始めてみることが、次の選択肢を見つけるきっかけになるはずです。
ユースキャリア教育機構の無料説明会へのご案内

「やってみたいけど、何から始めればいいか分からない」
「起業に興味はあるけど、1人で動くのは不安」
そんな人こそ、一歩目を“環境”に頼ってみてください。
ユースキャリア教育機構では、すでに800人以上の若者が、起業というテーマに向き合い、試行錯誤を重ねています。
同じ志を持つ仲間と出会い、先輩から実践的な学びを得て、想像もしなかった未来を描き始めたメンバーがたくさんいます。
興味を持った方は無料説明会にお申込みください!